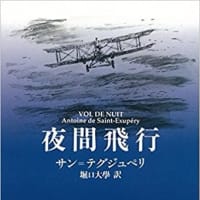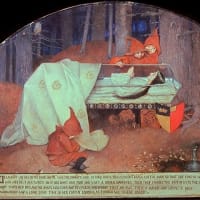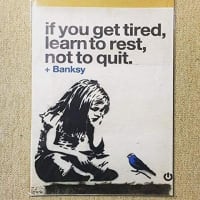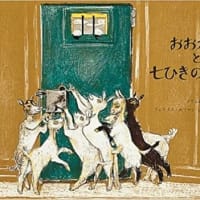『南方郵便機」は1926年に出版された、
『南方郵便機」は1926年に出版された、
サン=テグジュペリのデビュー作。
このとき、26歳。
サハラ砂漠モーリタニアにある中継基地、キャップ・ジュピーの飛行場長として、
砂漠のなかで生活する間に執筆されたものだそうだ。
 ジャック・ベルニスというヒコーキ野郎が主人公。
ジャック・ベルニスというヒコーキ野郎が主人公。 ……語り手である僕の、寄宿学校以来の友だちだ。
ジャックは郵便の入った袋を3袋積んで フランスのトゥールーズを飛び立った。
ところが、アフリカのポール・エティエンヌを過ぎたあと、消息を絶つ。
飛行機が創成期のころの話。
パイロットの息遣いが聞こえそうだし、描写はキラキラしている。
 堀口大學という名翻訳者が訳した本だけれど、
堀口大學という名翻訳者が訳した本だけれど、 その堀口大學さんにしてからが、「精読をしなければ…」と言っている。
要はこの本の構成がややこしく、読み解きづらいということなんじゃない?
実際、一人称、二人称、三人称がムチャクチャに切り替わるし、
時間の経緯も、過去と現在を行ったり来たり。
「僕ら」と、友人と自分のことを言っているけれど、
その経験の分別がつきづらく、 二人が余りに密着しているので、
本当は二人ではなく一人なのではと疑ってしまったり。
煩雑な展開で、時間の経緯と地図をノートに整理して
やっと全体像がつかめたという感じだった。
でも、何もそんなことをしなくても、
一読すると胸にジーンとくるものがある。
生きることについて深く考えさせられる硬質の文学。
 “ヒコーキ野郎”が誕生したのは20世紀に入ってからだ。
“ヒコーキ野郎”が誕生したのは20世紀に入ってからだ。 ヒコーキ野郎 は、まるで星の間を縫うようにして移動する特別な人たちだ。
彼らが描く文学は
(もちろん「優れた」という形容詞がつけられる文学に限るけど)
躍動感と詩に満ち溢れている。
大地に生活していては体験しえないものを文章にして見せてくれるのだ。
それだけでも素敵なのに…。
サン=テグジュペリは第二次世界大戦のさなか、
飛行機とともに海に落ちて、伝説になった。
だからなおさら、残された小説やエッセイは
不滅の輝きを帯びていると言えるんじゃないかなー。
残念に思えるのは、
堀口大學さんの翻訳は名文といわれるし、詩情豊かなのだけれど、
古っぽいこと。
村上春樹さんが言うように、原作の文章は古びないが、
翻訳の文章は古くさくなる。
そろそろ『星の王子さま』の新訳でいい感じだった河野万里子さんあたりに
新訳をお願いしたい。
そうなったらいいのに、と思うのだ。