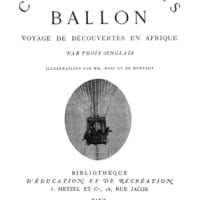ドイツの児童文学作家、エーリヒ・ケストナーの『飛ぶ教室』を読み返していて気づいたこと。
ドイツの児童文学作家、エーリヒ・ケストナーの『飛ぶ教室』を読み返していて気づいたこと。
子どもにとっても、人生は苛酷。
 もちろん、そうでない場合もあるかも。
もちろん、そうでない場合もあるかも。
環境に守られてスクスク育ってきた。
そういうことのほうが多いかもしれないけれど、
それでも、ままならないのが人生だということを、
ケストナーは冒頭の前書きから、読者に伝えようとしている。
つい先を急いで、
わかりやすいがじつは哲学的な部分は咀嚼せずに読み進めてしまうけれど、
(「ふうん、そうなんだ」くらいの軽いうなづきで過ぎてしまう部分だと思う)
読み返してみると、前書きのメッセージの深みが心に落ちる。
 『飛ぶ教室』が出版されたのは1933年。
『飛ぶ教室』が出版されたのは1933年。
ヒトラーがドイツの首相に就任し、思想弾圧に乗りだした年だ。
5月10日には、反ナチ作家たちの本25000冊が焚書にされた。
ケストナーの本も、児童書以外は燃やされたそうだ。
そんな時代背景は、本にはこれっぽっちも登場しないけれど、人生のせちがらさはメッセージとして、しっかり織り込まれている。
 「待てよ!」と思ったのは前書きの部分のヨナタン(ヨーニー)・トロッツの生い立ちについて。
「待てよ!」と思ったのは前書きの部分のヨナタン(ヨーニー)・トロッツの生い立ちについて。
この部分は過去、「気の毒に」と思うくらいで、それ以上は深くこだわらずに読み飛ばしていた。
★どうしておとなはそんなにじぶんの子どものころをすっかり忘れることができるのでしょう?
そして、子どもは時にはずいぶん悲しく不幸になるものだということが、どうして全然わからなくなってしまうのでしょう。
この人生では、なんで悲しむかということはけっして問題ではなく、どんなに悲しむかということだけが問題です。
子どもの涙はけっしておとなの涙より小さいものではなく、おとなの涙より重いことだって、めずらしくありません。
とケストナーはいう。
それからヨーニー・トロッツの身のうえは、「少年の涙が小さいものでないことを示すにふさわしいと思います」とも。
どんな身の上かというと、ヨーニー・トロッツの両親はアメリカで出会ったのだ。
おかあさんはアメリカ人で、おとうさんはドイツ人。
ヨーニーはニューヨーク生まれ。
ところが夫婦仲が悪く、おかあさんはとうとう家出をしてしまう。
察するに、おかあさんはほかに恋人を作り、子どもを捨てて家を出たのではないかなあ。
子どもを父親に押し付けて行ってしまった。
父親にしてみれぱ、仕事をしながら、幼い子どもを男手で育てろと言われても、無理だったんじゃないかなー。
(ここら辺はかってに想像している。)
どちらにしても、愛情のこまやかさは望めない両親だったようで。
ヨーニー・トロッツは4歳のときに、大西洋を横断してドイツのハンブルクまで航海する客船に乗せられた。
たった一人で。
祖父母がハンブルクに迎えにきているから、一人旅になるけれどよろしくと船長にお願いしたのだ。
4歳のヨーニーはひとりぼっちで一週間の船旅。
ところがハンブルクに到着すると、迎えに来ているはずの祖父母の姿はどこにもなかった。
そりゃそうなのだ。何年も前に死んでいるのだから。
★おとうさんはただ子どもをふり捨てようと思って、ドイツに送ったのであって、そのさきのことは考えようとしなかったのです。
その当時ヨーニーは、じぶんがどんな目にあわされたかがまだよくわかりませんでしたが、大きくなってから、夜、まんじりともしないで泣きあかすことが、いくどもありました。
四つの時に加えられたこの悲しみを、彼は一生のあいだ忘れることができないでしょう。
けっきょく船長がヨーニーを引き取り、妹のところに預け、10歳になると高等中学の寄宿舎に入れてくれたというわけ。
そして、その高等中学が舞台になって、この『飛ぶ教室』の物語が始まる。
 たしかに、
たしかに、
子どもにとっても、人生はなかなか厳しい。
(どんな子どもであっても、なにかしらはあるに違いない。)
それを大人もしっかりわかってないといけないよなーと、
前書きの部分で(胸の痛みとともに)思ったのだ。
★どうして大人はそんなにじぶんの子どものころをすっかり忘れることができるのでしょう?
そして、子どもの時にはずいぶん悲しく不幸になるものだということが、どうして全然わからなくなってしまうのでしょう?
(この機会に私はみなさんに心の底からお願いします。みなさんの子どものころをけっして忘れないように! と。それを約束してくれますか、ちかって?)
(★印の部分はすべて、岩波書店・高橋健二訳より抜粋)