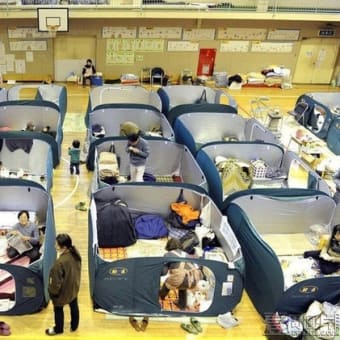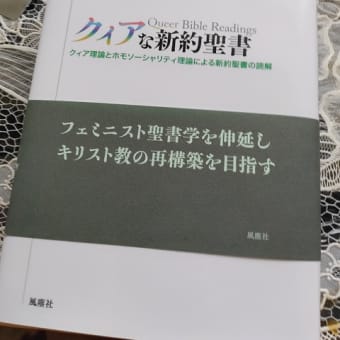まず森会長を非難する一部の人に対して、「差別(discrimination)をするな」と言っておくことにしたい。
「老害!」と批判する人だ。これは差別だ。年齢による差別であるからエイジズム(ageism)。性差別(sexism)に反対するなら、エイジズムにも当然反対するべきだろう。
年齢や性差による傾向は確かにあるだろう。しかし個人に焦点を当てれば、老人でも性差別をしない人は当然いるし、若者に性差別する人はこれまた当然いる。
差別とは、「(1)個人の特性によるのではなく、ある社会的カテゴリーに属しているという理由で、(2). 合理的に考えて状況に無関係な事柄に基づいて、(3 )異なった(不利益な)取扱いをすること」と定義される。(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1418/00121109/02_kyozai_9_ronbun.pdf)より
⑵⑶に焦点を当てがちだが、そもそも「ある社会的カテゴリーに属している」こと自体が政治的な態度を内包する。僕はこのような政治を勝手に「意識の政治」と名付けている。
人は個人をそのまま見ることがなかなかできない。概念である社会的カテゴリー(概念)を通して見てしまう。その時、ある社会的カテゴリーは[男と女(それ以外のジェンダーもあるので単純ではない)]、[若者と老人(これもまた色々な年齢による位位置付けがあるので単純ではない)]と本来の人間のあり方を単純化する。この概念による単純化は政治的な意識を作り出す。政治的というと日常的な実感からは遠い感じがあるので、文化的でもいい。
さらにこの政治的・文化的“区分”は、この区分にある属性に優劣や上下関係を想定してしまう。これが社会的カテゴリーの設定自体が政治的であるという土台の上にさらに優劣・上下関係という政治を行っているので、差別的な認識が二重構造化してしまう。これが差別の根本構造になるだろう。
さらにいえば、このような差別構造は自明になり規範となってしまう。規範とは、人々の行動に指針をあたえる価値基準や行動の基準であり、それに同調した考えに褒美かあたえられ、それに反する行動をとった者には罰が当てられる。だから、このような規範は人々の判断基準であり、人々はそれに従いながら生きていくことになる。
だからこそ、我々は差別的な意識をどこかに抱えているのであり、そこからは逃れられないのだ。哲学的な理解を持ち出せば、概念を持ちうる人間は必然的に差別的になる。しかしながら、その差別が正義ではないと我々は知っている。
森会長の発言を考えるのには、いろいろな角度がありうるのだが、この自明となっている規範に焦点を当てるほうがいいだろう。そこで森会長が言う「わきまえろ」と言う言葉が持つ規範性に焦点を当ててみようかと思う。
(つづく)