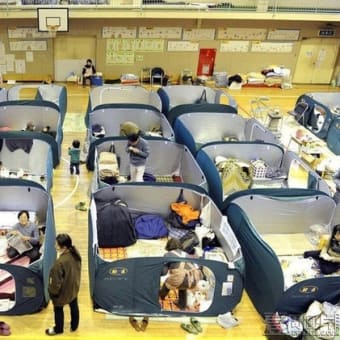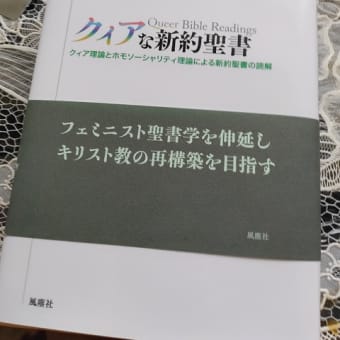衆院予算委で「Go toはコロナ感染拡大」と指摘され、菅首相が「経済を回さねば」として、「暮らしを守らないと命も守れなくなる」と答えた。「もっともだ」と思うのだろうか、それとも「もっともらしい」と思うだろうか。
順番が逆でしょう。暮らしと命、どちらが先か、自明だ。ゆえに「命を守らないと暮らしも守れない」が正しい。でも、僕たちのリアリティに菅首相の言葉が訴えてくるのだろう。それゆえ、「おかしい」と感じない。共犯というか、同じ価値意識を持っているということだろう。
ちょうど自宅近くの調布駅前で、ゲゲゲの鬼太郎のフェアをやっていた。ネットで調べてみると、「ゲゲゲ忌2020」というイベントだ。調布市の主催のようだ。なんと多くの人だかりだろうか。
たまたま買い物に行ったときに遭遇したのだが、野外で検温するなどしながら、子供も含めて人々は楽しんでいるようだった。そう、僕たちはこのような現代的な「消費の殿堂」を楽しむことを喜びとする。そういう風にインプリンティングされているのだろう。それを幸せであると刷り込まれている。
コロナ真只中でも、このような幸せを求めて人々は行動する。このイベントを楽しむことが「暮らしを守」ることである。しかしながら、人が集まっているわけだから、コロナのリスクは上がっている。僕はその風景を見て「怖いな」と思いながら通り過ぎた。
哲学者のアドルノは「アウシュビッツ以降、詩を書くことは野蛮である」と言った。これは単にアウシュビッツという悲惨をのみ反省しようとの言葉ではない。アウシュビッツは野蛮の象徴。詩は文明あるいは文化の象徴。つまり文化は野蛮を抱えているという事実、文明は野蛮抜きには決して成立しないことを表現した言葉なのである。進歩には必ず退行が伴うのだ。だが、人は進歩のみを見てしまう。そこにアドルノの難解さと慧眼がある。
僕には調布のイベントに集まる人々、Go toトラベルで楽しむ人々にアドルノが見た風景の小さな世界があるように思えてしまう。この小さな喜び、消費することを幸福感とすることは人間の進歩であると同時に、それに伴う野蛮であると見えてしまう。
他ならぬ文化自体が人間の野蛮であり、消費を楽しむこと、イベントを楽しむことの延長線上にあるその小さな現象をまとめる「経済を回すこと」との大きな価値規範を見てしまう。そしてこの価値規範は近代が作り上げたものである。アドルノの哲学では、これらは野蛮である。
アドルノは、文化は人間にふさわしい社会を在りもしないのに在るかのように見せかけたり、かりそめの慰めや満足を与えると言う。それが経済、近代社会に規定された劣悪な生存条件を維持するとも。さらにそれが劣悪だとも気づかないとも。
アドルノと同様フランクフルト学派のベンヤミンはこのような状況を「経験の貧困化」と言う。イベントに集まる人々、Go toを楽しむとは、何を経験しているのだろう。