我的三国演義~第四巻『流浪の英雄、呂布』
この巻の主な出来事です。
191年(初平2年) 『袁紹』、「公孫瓚」を破り“冀州”を手に入れる。
『曹操』、「東郡」の“太守”となる。
192年(初平3年) 『呂布』「王允」、『董卓』を暗殺。
『孫堅』が暗殺され、『孫策』が跡を継ぐ。
『曹操』、“青州”の“黄巾賊”を降伏させ“兗州牧”になる。
193年(初平4年) 『曹操』、“徐州牧”「陶謙」を攻め、領民十万を殺す。
194年(興平元年) 『曹操』が“徐州”遠征中、“兗州”で『呂布』「張邈」らが反乱する。
『劉備』、「陶謙」没後“徐州牧”となる。
195年(興平2年) 『曹操』、「定陶」と「鉅野」で『呂布』を破る。
『呂布』、『劉備』を頼り“徐州”へ。
さて、『董卓』が暗殺された後、各地の群雄たちはどうなったのか…。
 呂布奉先(生年不詳 - 198年)
呂布奉先(生年不詳 - 198年)
『董卓』を暗殺した『呂布』は「李カク」らに「長安」を追われ、「南陽」の『袁術』を頼ろうとしますが拒否されました。
その後「張燕」ら黒山賊と戦う河北の『袁紹』に助太刀しました。
『呂布』の軍は強く、精強を誇った黒山賊を撃破しました。
しかし『呂布』はその後『袁紹』に兵力の補充を要求し、『呂布』の引き連れる兵も略奪などを行いました。
これが『袁紹』の忌むところとなり、『呂布』もそれを察して『袁紹』の下を離れました。
さらに『袁紹』は『呂布』に刺客を送りますが、これは失敗しました。
『呂布』は河内の「張揚」を頼りましたが、『呂布』を恐れる『袁紹』が大軍を出して駆逐し、他の勢力も『呂布』を畏怖して保護しようとはしませんでした。
そういった逃亡の中で、ある日『呂布』は「陳留」を通過し、『曹操』の旧友であり、信頼の厚い“太守”「張邈」に厚くもてなされました。
まもなく「張邈」は時の権力者『袁紹』がお尋ね者とする『呂布』を歓待したことで、『袁紹』の命令の下『曹操』に攻撃されることを恐れました。
193年には、『曹操』の部下でありながら彼に不満を持つ「陳宮」に説得され、『呂布』を盟主として“兗州刺史”とし、『曹操』に反旗を翻しました。
 孫堅文台(156年 - 192年)
孫堅文台(156年 - 192年)
191年『孫堅』は「荊州」の「劉表」を攻撃しました。
これは『袁紹』と『袁術』兄弟が仲違いしたために、「袁」兄弟の代理戦争として起こったものです。
“冀州”を手に入れた『袁紹』に対し、『袁術』は馬1000頭を要求しますが、これを無視されたことで仲が悪くなったと言われています。
『袁紹』-「劉表」 『袁術』-『孫堅』という構図で始まったこの戦は『孫堅』が「劉表」軍の将「黄祖」が放った流れ矢に当たって死ぬという思いがけない結末で幕を引きました。
『袁術』-『孫堅』という構図で始まったこの戦は『孫堅』が「劉表」軍の将「黄祖」が放った流れ矢に当たって死ぬという思いがけない結末で幕を引きました。
『孫堅』の死因については異説もあります。
『孫堅』は武装も固めず、騎馬で「劉表」の武将「呂公」を追って山伝いに進んでいましたが、「呂公」軍の兵士が落とした大石が頭に当たり、即死したともいわれています。
これにより息子の『孫策』が17歳で跡を継いでいます。
 劉備玄徳(161年 - 223年)
劉備玄徳(161年 - 223年)
『劉備』は191年「公孫瓚」に加勢し、『袁紹』軍と戦い、その後「平原」の“相”になりました。
 曹操孟徳(155年 - 220年)
曹操孟徳(155年 - 220年)
『曹操』は、191年「東郡」“太守”に任命されていました。
192年“青州”の“黄巾賊”100万が“兗州”に侵入すると、“兗州”を統治していた「鮑信」は、『曹操』に応援を要請し、見返りに“兗州牧”の地位を約束しました。
『曹操』はこの“黄巾賊”の精鋭30万を「青州兵」として配下にし、彼らを降伏させたのでした。
この兵力増強は『曹操』躍進の原動力となりました。
 袁紹本初(生年不詳 - 202年)
袁紹本初(生年不詳 - 202年)
『袁紹』は「第三巻」に書いた通りですが、191年に“冀州”を奪い、「公孫瓚」と抗争を続けていましたが、とりあえず『董卓』の仲裁によって「公孫瓚」と和睦しました。

“青州”の“黄巾賊”を降伏させ、“兗州牧”におさまった『曹操』は、193年に父「曹嵩」をはじめ一族を呼び寄せることにしました。
その頃の「曹嵩」は「瑯邪国」に疎開していました。
「瑯邪国」は今の「山東省臨沂市」辺りで『諸葛亮』の故里もこの「瑯邪国」なのです。
『諸葛亮』は192年に父「諸葛珪」を亡くし、194年(14歳の時)に弟の「諸葛均」と共に従父の「諸葛玄」に連れられ南方へ移住しています。
それは後に書きますが、『曹操』の“徐州”侵攻も大きな原因だったのでしょう。
“徐州牧”の「陶謙」は「曹嵩」一行の護衛にと200名(“三国演義”では500名)ほどの兵をつけました。
「曹嵩」一行は途中で激しい雨のため、とある古寺に立ち寄りました。
一族と従者は堂内で休んだのに対し、「陶謙」の兵は回廊で休まされました。
このとき、ずぶ濡れになった兵士たちの不満が爆発しました。
この兵士たちは元は“黄巾賊”の出の者であり、彼らは「陶謙」の命に背き、一行を皆殺しにして財物を奪って逃走しました。
「曹嵩」は便所に隠れていたところを殺されたといいます。
 三国史跡紹介・其之十一~曹嵩墓壁(未到達)
三国史跡紹介・其之十一~曹嵩墓壁(未到達)
「山東省沂南県磚埠鎮汪家庄」には「曹嵩墓」は既に無いものの、「墓壁」は残っているようです。
『諸葛亮』の故里から北西に約3Kmの地にあるらしく、「曹嵩」はそこで殺害されたんでしょうかね?
…以上。
この報せを受けた『曹操』の怒りは凄まじく、即座に100万の兵を率いて“徐州”攻撃に向かいました。
『曹操』軍はすべての兵卒が白装束で、大旗には“報讐雪恨”と記されていました。
“徐州”で『曹操』軍が通過したところでは、多くの罪のない住民が殺害されたそうです。
194年、このとき『劉備』は“青州刺史”の「田楷」とともに「斉」(恐らく今俺が住んでる所に近いと思う)に駐屯していましたが、「陶謙」からの報せを受けた『劉備』は「陶謙殿に責めはないはず」と「田楷」とともに救援に向かいました。
“三国演義”では、このとき『劉備』は「公孫瓚」から2000の兵と『趙雲』を借り受けたことになっています。
『趙雲』は元は『袁紹』の配下でしたが嫌気がさし、故郷“冀州”に帰る途中で『袁紹』軍と交戦中の「公孫瓚」を救い、食客として「公孫瓚」に力を貸していたのです。
 三国史跡紹介・其之十二~趙雲故里(詳しくは2008年1月29日のブログを参照してね)
三国史跡紹介・其之十二~趙雲故里(詳しくは2008年1月29日のブログを参照してね)
『趙雲子龍』(生年不詳 - 229年)の故里は「河北省石家荘市正定県」です。


「石家荘市正定県」には「趙雲廟」があります。
石家庄火車站前から201路バスで正定まで行けます。
正定の汽車站からは1路バスに乗って、終点近くで下車します。
俺は石家庄火車站前から201路バスが見つけられず、「趙雲廟」までタクシーで行くハメになってしまいましたが…
所要時間は石家庄火車站から1時間あれば行けます。
「趙雲廟」の入場料は15元です。
到達難易度は「C」かな。
1路バスで降りる場所さえ分かれば簡単ですが、「廟」前を通らないので運転手に「趙雲廟」付近で降ろしてもらえば良いでしょう。
正定汽車站から「趙雲廟」までの途中の公園には、『趙雲』像があります。
降りるバス停名は分かりませんが、ここの『趙雲』像はカッコいいぞ
…以上。
『曹操』が“徐州”の城を次々に落としていたとき、『曹操』の根拠地“兗州”では一大事が起きようとしていました。
「陳留郡」の“太守”「張邈」と『曹操』は盟友ともいえる間柄でしたが、“徐州”での『曹操』の蛮行を耳にするにつれ、「張邈」は友に恐怖心を抱くようになってきました。
そこへやって来たのが『呂布』でした。
「張邈」と『呂布』はすっかり意気投合しました。
これに目をつけたのが「陳宮」でした。
「陳宮」は「張邈」に「向かうところ敵なしの呂布と立てば、天下も夢ではありません。まずこの兗州を奪うのです」とささやきました。
「陳宮」は『曹操』が『董卓』暗殺に失敗して逃走していた際に『曹操』を助けて以来、『曹操』の幕閣として手腕を発揮していましたが、「陳宮」自身に天下を取る野望はありませんでした。
しかし「陳宮」には、覇王を意のままに操りたいという野心がありました。
ですが『曹操』は「陳宮」が操れるような男ではありません。
そこに『呂布』という豪傑が現れたのです。
「呂布なら思いのままに操れる」と考えた「陳宮」は、野望を実現するため「張邈」と『呂布』を誘い込んだのです。
「張邈」はさっそく『呂布』を迎え入れて“兗州牧”に任命すると「濮陽」に立てこもりました。
「横山光輝」の“三国志”では、“徐州”に援軍として入った『劉備』は、圧倒的な兵力の差で勝ち目は到底無いので、停戦の使者を『曹操』に出しました。
私怨による進軍を止め、まず国難を救うべき…という書状を『張飛』に託しました。
それを読んだ『曹操』は怒りましたが、ちょうどその時“兗州”に『呂布』軍が攻め込んでいる情報が入りました。
『曹操』は『劉備』が提案した停戦に応じたふりをして、すぐ“兗州”に引き返しました。
『呂布』は『曹操』が“徐州”に進軍している間に、「陳宮」の入れ知恵で空き家同然の“兗州”を奪おうとしていたのです。
その年(194年)「陶謙」没後、『劉備』は“徐州牧”になりました。



『呂布』 VS 『曹操』
194年、『曹操』は『呂布』軍がこもる「濮陽」を包囲し、『呂布』の騎馬隊と激突しましたが、さすがに『呂布』は強く、『曹操』自慢の“青州兵”も突き崩される有様でした。
“三国演義”では、雨のように射られる矢の中で『曹操』軍の「典韋」は命からがら『曹操』を救っています。
ところが「濮陽」の豪族「田」氏が『曹操』に内通して開城させました。
『曹操』軍は中に入ると門に火をつけ、自ら退路を絶ちました。
城内は激しい戦になりましたが『曹操』は『呂布』の騎兵に捕らえられてしまいました。
『曹操』が観念したとき、敵兵が『曹操』に向かって「曹操はどこか?」と尋問しました。
『曹操』はとっさに「黄色の馬に乗って逃げて行くのが曹操だ!」と言い逃れ、ようやく城を出ることが出来ましたが、『曹操』はこのとき火傷を負っています。
こうして100日あまりにわたって「濮陽」城をめぐる激しい攻防戦が繰り広げられました。
ところが、そこに“いなご”の大群が発生しました。
稲も畑の作物もすべてを食い尽くされ、穀物は高騰し、植えた人々は互いの肉を食い合うほどだったと“正史”はその惨状を伝えています。
こうなっては、戦どころではなくなり「濮陽」で対峙していた『曹操』と『呂布』も一時休戦になりました。
“三国演義”では、この戦のさなか「許褚」という武将を得ています。
賊から村を守っていた「許褚」と『曹操』の親衛隊長「典韋」はぶつかり合いますが、終日戦い続けても決着がつきませんでした。
それを見た『曹操』は一目で「許褚」を気に入り、策を用いて「許褚」を捕らえました。
以後『曹操』は、虎のような武勇と質朴な「許褚」の人柄をこよなく愛し、「虎痴」と呼んで重用しました。
翌195年、『曹操』は再び兵を挙げると、「定陶」と「鉅野」で『呂布』を破り、“兗州”を奪還します。
勝ち目がないと見た「陳宮」や『呂布』らは夜にまぎれて逃走し、“徐州”の『劉備』を頼ることにしました。
194年『劉備』は「陶謙」の病死によって“徐州牧”になっていました。
『劉備』はこの“徐州牧”の要請になかなか応じませんでしたが、「陶謙」の部下の「麋竺」らに根負けして承諾したのです。
このとき『劉備』は「麋竺」と「孫乾」という2人の逸材も譲り受けています。
後に「麋竺」の妹は『劉備』の妻になっています。
 孫策伯符(175年 - 200年)
孫策伯符(175年 - 200年)
一方、父『孫堅』の突然の死(191年)から3年の歳月が経ち、「孫」家を継いだ『孫策』は、「寿春」に拠点を移したばかりの『袁術』を頼り、その配下に加わっていました。
「孫策のような息子がおれば、いつ死んでもよい」と言われ、一時は『袁術』に大変気に入られていました。
しかし『袁術』は『孫策』に「九江」の“太守”を約束していたにもかかわらず、他の者を任命したりしたため、『孫策』は『袁術』にすっかり幻滅し、密かに独立の機会をうかがうようになりました。
さて『袁術』が拠点としていた「寿春」は、もともと“揚州刺史”の役所が置かれていた所でしたが、そこを『袁術』が占拠したため、“揚州刺史”に任命された「劉繇」はやむなく長江を渡った「曲阿」に州都を構えていました。
このとき「劉繇」は「曲阿」の南「丹陽」にいた『孫策』の叔父「呉景」と、従兄弟の「孫賁」に圧力をかけて2人を追い出し、さらに配下の将を長江の岸に配置して『袁術』の南下を牽制していました。
そこで『孫策』は『袁術』に「劉繇」討伐を願い出ました。
「横山光輝」の“三国志”では、父『孫堅』が以前「洛陽」で手にした「玉璽」との交換を『孫策』が提案し、『袁術』から兵3000、馬500頭を借りています。
その後「張昭」と「張鉱」という二賢人を味方に付けています。
『孫策』が江東(呉)へ軍を挙げると(194年)『周瑜』もこれに付き添って功績を挙げています。
そして「劉繇」軍との戦で「太史慈」を捕らえ、配下にしています。
それからは着々と江東に独自の地盤を築き、江東の小覇王と呼ばれるまでになりました。
 三国史跡紹介・其之十三~劉備廟(詳しくは2008年1月30日のブログを参照してね)
三国史跡紹介・其之十三~劉備廟(詳しくは2008年1月30日のブログを参照してね)

この「劉備廟」があるのは「山西省陽泉市郊区蔭営鎮坪上村」です。
「陽泉市」内から5路バスに乗り、「車管所」で下車します。
「劉備山」の頂上に、この「劉備廟」があります。
言い伝えによれば、『劉備』『関羽』『張飛』が卜占を行った地とされ、後世になって「劉備廟」が建てられたそうです。
ここ「山西省陽泉市」が「後漢」の時代には“冀州”に属していたか“并州”に属していたかは、よく分かりませんが、『劉備』らがここに来たとしたら『劉備』が“徐州牧”になる194年以前の事だろうと思います。
「陽泉市」内から5路バスで「車管所」まで約30分、山頂までの登山に約1時間半掛かります。
到達難易度は「B」かな…。
「車管所」までは簡単に行けますが、麓からちゃんとした登山路が無いので山頂に見える廟を頼りに崖をよじ登ったのと、下山するときは最後まで登山路を下りて行ったら「車管所」では無く、全然分からない所に辿り着いてしまったという恐怖の登山でありました…
「劉備山」は、1272.6mあるらしいですが…そんな高さの山をよじ登って…1時間半は無理だと思うけどな…。
俺は超人じゃないし…

下山時に見たこの岩ですが、ブログ掲載時(2008年1月30日)には何か分かりませんでしたが、後の調査でこれは「関公試刀石」という事が判明しました。
『関羽』が「青龍偃月刀」で真っ二つに斬ったのか

さて「第五巻」では、“徐州”の『劉備』の下に身を寄せた『呂布』、そして『呂布』から“兗州”を取り返した『曹操』、『董卓』亡き後「長安」を治める「李カク」と「郭」、そして『袁紹』『袁術』『孫策』…まだまだ群雄が割拠していた時代を綴っていきます。
この巻の主な出来事です。

191年(初平2年) 『袁紹』、「公孫瓚」を破り“冀州”を手に入れる。
『曹操』、「東郡」の“太守”となる。
192年(初平3年) 『呂布』「王允」、『董卓』を暗殺。
『孫堅』が暗殺され、『孫策』が跡を継ぐ。
『曹操』、“青州”の“黄巾賊”を降伏させ“兗州牧”になる。
193年(初平4年) 『曹操』、“徐州牧”「陶謙」を攻め、領民十万を殺す。
194年(興平元年) 『曹操』が“徐州”遠征中、“兗州”で『呂布』「張邈」らが反乱する。
『劉備』、「陶謙」没後“徐州牧”となる。
195年(興平2年) 『曹操』、「定陶」と「鉅野」で『呂布』を破る。
『呂布』、『劉備』を頼り“徐州”へ。
さて、『董卓』が暗殺された後、各地の群雄たちはどうなったのか…。
 呂布奉先(生年不詳 - 198年)
呂布奉先(生年不詳 - 198年)『董卓』を暗殺した『呂布』は「李カク」らに「長安」を追われ、「南陽」の『袁術』を頼ろうとしますが拒否されました。
その後「張燕」ら黒山賊と戦う河北の『袁紹』に助太刀しました。
『呂布』の軍は強く、精強を誇った黒山賊を撃破しました。
しかし『呂布』はその後『袁紹』に兵力の補充を要求し、『呂布』の引き連れる兵も略奪などを行いました。
これが『袁紹』の忌むところとなり、『呂布』もそれを察して『袁紹』の下を離れました。
さらに『袁紹』は『呂布』に刺客を送りますが、これは失敗しました。
『呂布』は河内の「張揚」を頼りましたが、『呂布』を恐れる『袁紹』が大軍を出して駆逐し、他の勢力も『呂布』を畏怖して保護しようとはしませんでした。
そういった逃亡の中で、ある日『呂布』は「陳留」を通過し、『曹操』の旧友であり、信頼の厚い“太守”「張邈」に厚くもてなされました。
まもなく「張邈」は時の権力者『袁紹』がお尋ね者とする『呂布』を歓待したことで、『袁紹』の命令の下『曹操』に攻撃されることを恐れました。
193年には、『曹操』の部下でありながら彼に不満を持つ「陳宮」に説得され、『呂布』を盟主として“兗州刺史”とし、『曹操』に反旗を翻しました。
 孫堅文台(156年 - 192年)
孫堅文台(156年 - 192年)191年『孫堅』は「荊州」の「劉表」を攻撃しました。
これは『袁紹』と『袁術』兄弟が仲違いしたために、「袁」兄弟の代理戦争として起こったものです。
“冀州”を手に入れた『袁紹』に対し、『袁術』は馬1000頭を要求しますが、これを無視されたことで仲が悪くなったと言われています。
『袁紹』-「劉表」
 『袁術』-『孫堅』という構図で始まったこの戦は『孫堅』が「劉表」軍の将「黄祖」が放った流れ矢に当たって死ぬという思いがけない結末で幕を引きました。
『袁術』-『孫堅』という構図で始まったこの戦は『孫堅』が「劉表」軍の将「黄祖」が放った流れ矢に当たって死ぬという思いがけない結末で幕を引きました。『孫堅』の死因については異説もあります。
『孫堅』は武装も固めず、騎馬で「劉表」の武将「呂公」を追って山伝いに進んでいましたが、「呂公」軍の兵士が落とした大石が頭に当たり、即死したともいわれています。
これにより息子の『孫策』が17歳で跡を継いでいます。
 劉備玄徳(161年 - 223年)
劉備玄徳(161年 - 223年)『劉備』は191年「公孫瓚」に加勢し、『袁紹』軍と戦い、その後「平原」の“相”になりました。
 曹操孟徳(155年 - 220年)
曹操孟徳(155年 - 220年)『曹操』は、191年「東郡」“太守”に任命されていました。
192年“青州”の“黄巾賊”100万が“兗州”に侵入すると、“兗州”を統治していた「鮑信」は、『曹操』に応援を要請し、見返りに“兗州牧”の地位を約束しました。
『曹操』はこの“黄巾賊”の精鋭30万を「青州兵」として配下にし、彼らを降伏させたのでした。
この兵力増強は『曹操』躍進の原動力となりました。
 袁紹本初(生年不詳 - 202年)
袁紹本初(生年不詳 - 202年)『袁紹』は「第三巻」に書いた通りですが、191年に“冀州”を奪い、「公孫瓚」と抗争を続けていましたが、とりあえず『董卓』の仲裁によって「公孫瓚」と和睦しました。

“青州”の“黄巾賊”を降伏させ、“兗州牧”におさまった『曹操』は、193年に父「曹嵩」をはじめ一族を呼び寄せることにしました。
その頃の「曹嵩」は「瑯邪国」に疎開していました。
「瑯邪国」は今の「山東省臨沂市」辺りで『諸葛亮』の故里もこの「瑯邪国」なのです。
『諸葛亮』は192年に父「諸葛珪」を亡くし、194年(14歳の時)に弟の「諸葛均」と共に従父の「諸葛玄」に連れられ南方へ移住しています。
それは後に書きますが、『曹操』の“徐州”侵攻も大きな原因だったのでしょう。
“徐州牧”の「陶謙」は「曹嵩」一行の護衛にと200名(“三国演義”では500名)ほどの兵をつけました。
「曹嵩」一行は途中で激しい雨のため、とある古寺に立ち寄りました。
一族と従者は堂内で休んだのに対し、「陶謙」の兵は回廊で休まされました。
このとき、ずぶ濡れになった兵士たちの不満が爆発しました。
この兵士たちは元は“黄巾賊”の出の者であり、彼らは「陶謙」の命に背き、一行を皆殺しにして財物を奪って逃走しました。
「曹嵩」は便所に隠れていたところを殺されたといいます。

 三国史跡紹介・其之十一~曹嵩墓壁(未到達)
三国史跡紹介・其之十一~曹嵩墓壁(未到達)「山東省沂南県磚埠鎮汪家庄」には「曹嵩墓」は既に無いものの、「墓壁」は残っているようです。
『諸葛亮』の故里から北西に約3Kmの地にあるらしく、「曹嵩」はそこで殺害されたんでしょうかね?
…以上。
この報せを受けた『曹操』の怒りは凄まじく、即座に100万の兵を率いて“徐州”攻撃に向かいました。
『曹操』軍はすべての兵卒が白装束で、大旗には“報讐雪恨”と記されていました。
“徐州”で『曹操』軍が通過したところでは、多くの罪のない住民が殺害されたそうです。
194年、このとき『劉備』は“青州刺史”の「田楷」とともに「斉」(恐らく今俺が住んでる所に近いと思う)に駐屯していましたが、「陶謙」からの報せを受けた『劉備』は「陶謙殿に責めはないはず」と「田楷」とともに救援に向かいました。
“三国演義”では、このとき『劉備』は「公孫瓚」から2000の兵と『趙雲』を借り受けたことになっています。
『趙雲』は元は『袁紹』の配下でしたが嫌気がさし、故郷“冀州”に帰る途中で『袁紹』軍と交戦中の「公孫瓚」を救い、食客として「公孫瓚」に力を貸していたのです。
 三国史跡紹介・其之十二~趙雲故里(詳しくは2008年1月29日のブログを参照してね)
三国史跡紹介・其之十二~趙雲故里(詳しくは2008年1月29日のブログを参照してね)『趙雲子龍』(生年不詳 - 229年)の故里は「河北省石家荘市正定県」です。


「石家荘市正定県」には「趙雲廟」があります。
石家庄火車站前から201路バスで正定まで行けます。

正定の汽車站からは1路バスに乗って、終点近くで下車します。
俺は石家庄火車站前から201路バスが見つけられず、「趙雲廟」までタクシーで行くハメになってしまいましたが…

所要時間は石家庄火車站から1時間あれば行けます。
「趙雲廟」の入場料は15元です。
到達難易度は「C」かな。
1路バスで降りる場所さえ分かれば簡単ですが、「廟」前を通らないので運転手に「趙雲廟」付近で降ろしてもらえば良いでしょう。

正定汽車站から「趙雲廟」までの途中の公園には、『趙雲』像があります。
降りるバス停名は分かりませんが、ここの『趙雲』像はカッコいいぞ

…以上。
『曹操』が“徐州”の城を次々に落としていたとき、『曹操』の根拠地“兗州”では一大事が起きようとしていました。
「陳留郡」の“太守”「張邈」と『曹操』は盟友ともいえる間柄でしたが、“徐州”での『曹操』の蛮行を耳にするにつれ、「張邈」は友に恐怖心を抱くようになってきました。
そこへやって来たのが『呂布』でした。
「張邈」と『呂布』はすっかり意気投合しました。
これに目をつけたのが「陳宮」でした。
「陳宮」は「張邈」に「向かうところ敵なしの呂布と立てば、天下も夢ではありません。まずこの兗州を奪うのです」とささやきました。
「陳宮」は『曹操』が『董卓』暗殺に失敗して逃走していた際に『曹操』を助けて以来、『曹操』の幕閣として手腕を発揮していましたが、「陳宮」自身に天下を取る野望はありませんでした。
しかし「陳宮」には、覇王を意のままに操りたいという野心がありました。
ですが『曹操』は「陳宮」が操れるような男ではありません。
そこに『呂布』という豪傑が現れたのです。
「呂布なら思いのままに操れる」と考えた「陳宮」は、野望を実現するため「張邈」と『呂布』を誘い込んだのです。
「張邈」はさっそく『呂布』を迎え入れて“兗州牧”に任命すると「濮陽」に立てこもりました。
「横山光輝」の“三国志”では、“徐州”に援軍として入った『劉備』は、圧倒的な兵力の差で勝ち目は到底無いので、停戦の使者を『曹操』に出しました。
私怨による進軍を止め、まず国難を救うべき…という書状を『張飛』に託しました。
それを読んだ『曹操』は怒りましたが、ちょうどその時“兗州”に『呂布』軍が攻め込んでいる情報が入りました。
『曹操』は『劉備』が提案した停戦に応じたふりをして、すぐ“兗州”に引き返しました。
『呂布』は『曹操』が“徐州”に進軍している間に、「陳宮」の入れ知恵で空き家同然の“兗州”を奪おうとしていたのです。
その年(194年)「陶謙」没後、『劉備』は“徐州牧”になりました。



『呂布』 VS 『曹操』
194年、『曹操』は『呂布』軍がこもる「濮陽」を包囲し、『呂布』の騎馬隊と激突しましたが、さすがに『呂布』は強く、『曹操』自慢の“青州兵”も突き崩される有様でした。
“三国演義”では、雨のように射られる矢の中で『曹操』軍の「典韋」は命からがら『曹操』を救っています。
ところが「濮陽」の豪族「田」氏が『曹操』に内通して開城させました。
『曹操』軍は中に入ると門に火をつけ、自ら退路を絶ちました。
城内は激しい戦になりましたが『曹操』は『呂布』の騎兵に捕らえられてしまいました。
『曹操』が観念したとき、敵兵が『曹操』に向かって「曹操はどこか?」と尋問しました。
『曹操』はとっさに「黄色の馬に乗って逃げて行くのが曹操だ!」と言い逃れ、ようやく城を出ることが出来ましたが、『曹操』はこのとき火傷を負っています。
こうして100日あまりにわたって「濮陽」城をめぐる激しい攻防戦が繰り広げられました。
ところが、そこに“いなご”の大群が発生しました。
稲も畑の作物もすべてを食い尽くされ、穀物は高騰し、植えた人々は互いの肉を食い合うほどだったと“正史”はその惨状を伝えています。
こうなっては、戦どころではなくなり「濮陽」で対峙していた『曹操』と『呂布』も一時休戦になりました。
“三国演義”では、この戦のさなか「許褚」という武将を得ています。
賊から村を守っていた「許褚」と『曹操』の親衛隊長「典韋」はぶつかり合いますが、終日戦い続けても決着がつきませんでした。
それを見た『曹操』は一目で「許褚」を気に入り、策を用いて「許褚」を捕らえました。
以後『曹操』は、虎のような武勇と質朴な「許褚」の人柄をこよなく愛し、「虎痴」と呼んで重用しました。
翌195年、『曹操』は再び兵を挙げると、「定陶」と「鉅野」で『呂布』を破り、“兗州”を奪還します。
勝ち目がないと見た「陳宮」や『呂布』らは夜にまぎれて逃走し、“徐州”の『劉備』を頼ることにしました。
194年『劉備』は「陶謙」の病死によって“徐州牧”になっていました。
『劉備』はこの“徐州牧”の要請になかなか応じませんでしたが、「陶謙」の部下の「麋竺」らに根負けして承諾したのです。
このとき『劉備』は「麋竺」と「孫乾」という2人の逸材も譲り受けています。
後に「麋竺」の妹は『劉備』の妻になっています。
 孫策伯符(175年 - 200年)
孫策伯符(175年 - 200年)一方、父『孫堅』の突然の死(191年)から3年の歳月が経ち、「孫」家を継いだ『孫策』は、「寿春」に拠点を移したばかりの『袁術』を頼り、その配下に加わっていました。
「孫策のような息子がおれば、いつ死んでもよい」と言われ、一時は『袁術』に大変気に入られていました。
しかし『袁術』は『孫策』に「九江」の“太守”を約束していたにもかかわらず、他の者を任命したりしたため、『孫策』は『袁術』にすっかり幻滅し、密かに独立の機会をうかがうようになりました。
さて『袁術』が拠点としていた「寿春」は、もともと“揚州刺史”の役所が置かれていた所でしたが、そこを『袁術』が占拠したため、“揚州刺史”に任命された「劉繇」はやむなく長江を渡った「曲阿」に州都を構えていました。
このとき「劉繇」は「曲阿」の南「丹陽」にいた『孫策』の叔父「呉景」と、従兄弟の「孫賁」に圧力をかけて2人を追い出し、さらに配下の将を長江の岸に配置して『袁術』の南下を牽制していました。
そこで『孫策』は『袁術』に「劉繇」討伐を願い出ました。
「横山光輝」の“三国志”では、父『孫堅』が以前「洛陽」で手にした「玉璽」との交換を『孫策』が提案し、『袁術』から兵3000、馬500頭を借りています。
その後「張昭」と「張鉱」という二賢人を味方に付けています。
『孫策』が江東(呉)へ軍を挙げると(194年)『周瑜』もこれに付き添って功績を挙げています。
そして「劉繇」軍との戦で「太史慈」を捕らえ、配下にしています。
それからは着々と江東に独自の地盤を築き、江東の小覇王と呼ばれるまでになりました。
 三国史跡紹介・其之十三~劉備廟(詳しくは2008年1月30日のブログを参照してね)
三国史跡紹介・其之十三~劉備廟(詳しくは2008年1月30日のブログを参照してね)
この「劉備廟」があるのは「山西省陽泉市郊区蔭営鎮坪上村」です。
「陽泉市」内から5路バスに乗り、「車管所」で下車します。

「劉備山」の頂上に、この「劉備廟」があります。
言い伝えによれば、『劉備』『関羽』『張飛』が卜占を行った地とされ、後世になって「劉備廟」が建てられたそうです。
ここ「山西省陽泉市」が「後漢」の時代には“冀州”に属していたか“并州”に属していたかは、よく分かりませんが、『劉備』らがここに来たとしたら『劉備』が“徐州牧”になる194年以前の事だろうと思います。
「陽泉市」内から5路バスで「車管所」まで約30分、山頂までの登山に約1時間半掛かります。

到達難易度は「B」かな…。
「車管所」までは簡単に行けますが、麓からちゃんとした登山路が無いので山頂に見える廟を頼りに崖をよじ登ったのと、下山するときは最後まで登山路を下りて行ったら「車管所」では無く、全然分からない所に辿り着いてしまったという恐怖の登山でありました…

「劉備山」は、1272.6mあるらしいですが…そんな高さの山をよじ登って…1時間半は無理だと思うけどな…。
俺は超人じゃないし…


下山時に見たこの岩ですが、ブログ掲載時(2008年1月30日)には何か分かりませんでしたが、後の調査でこれは「関公試刀石」という事が判明しました。

『関羽』が「青龍偃月刀」で真っ二つに斬ったのか


さて「第五巻」では、“徐州”の『劉備』の下に身を寄せた『呂布』、そして『呂布』から“兗州”を取り返した『曹操』、『董卓』亡き後「長安」を治める「李カク」と「郭」、そして『袁紹』『袁術』『孫策』…まだまだ群雄が割拠していた時代を綴っていきます。











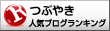





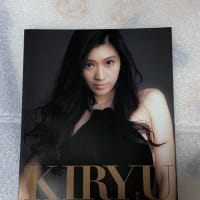





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます