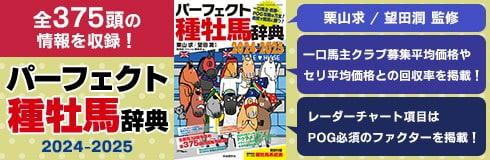たとえばステイゴールドやダイワメジャーの産駒なんかをみると、Lady Angela3×2のノーザンテーストが及ぼす影響力を今でも実感できるわけですが、笠シショーが「サラブレ」の連載で書いていたように、Hyperion3×2のHighlightとか、Nearco3×3のロイヤルサッシュとか、Blue Gay≒Revoked1×2のBlue Burstとか、Balladier≒Blue Larkspur3・4×3のMy Bupersとか、Busanda≒Striking2×3のNumbered Accountとか、2×3ぐらいの強いインブリードが名牝系の礎となっているケースは極めて多いのです
だからSadler's Wells≒Nureyev3×2とかDance Number≒Numbered Account2×3とか、そういうことを今も狙ってやらなければならないし、同時に強力な緊張を緩和できるMonsunとかメジロマックイーンのようなアウトサイダーな名血も遺していかなければならないし取り入れていかなければならない
内外の大レースの勝ち馬の血統表をしみじみ眺めていると、けっきょく配合史のあとがきに書いてあるような、血統論の基本の基本に立ち返ることになります
私が配合史的血統論を考え方の幹としているのは、St.SimonもDominoもNearcoもLady JosephineもNasrullahもNorthern Dancerも、サンデーサイレンスもノーザンテーストもブライアンズタイムも、みんな同じ切り口で、「3/4と1/4」の概念で斬れるからに他なりません
それこそが幹であって、○○と××はニックスやとか、△△と▲▲はニアリーやとか、☆☆のクロスは重が巧いんやとか、そういうのは枝の話にすぎないんですよね~
でもG1の予想とか、POGの馬選びとか、そういう日常の競馬のお仕事においてはどうしても枝の話中心になってしまうわけで、血統に興味を持っていただくには枝のほうがとっつきやすいのもたしかなのですが、そこから幹に導く説明能力や証明能力が相変わらず足りんよなあ…と自省する日々でもあります
今週は「血統クリニック」はお休み(水曜にガンガン飲めるぞ~)、本日18時更新のNETKEIBA「重賞の見どころ」では大阪杯とダービー卿CTの有力馬の血統解説を書いています
今週は2場開催で重賞は二つだけなので、3頭ずつ書こうかな~