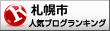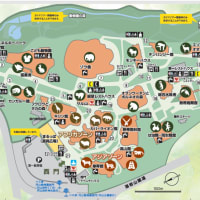鏝絵
鏝絵
浦賀(神奈川県横須賀市)と言うと「ペリー来航」をすぐ連想しますが、
色々調べていくうちに、注目すべきものが他にもあることが分かってきました。
その1つが「鏝絵(こてえ)」です。
初めて聞くものだったのですが、一体、「鏝絵」って何なのでしょう。
 鏝絵とは
鏝絵とは
日本で発展した漆喰を用いて作られるレリーフのことである。
左官職人がこて(左官ごて)で仕上げていくことから名がついた。
題材は福を招く物語、花鳥風月が中心であり、着色された漆喰を用いて極彩色で表現される。
これは財を成した豪商や網元が母屋や土蔵を改築する際、
富の象徴として外壁の装飾に盛んに用いられたからである。
(ウィキペディアより)
さらに「横須賀本」によれば、干鰯問屋と廻船問屋で栄えた浦賀には土蔵造りが盛んであったことから、
漆喰壁を塗る左官職人も多く、「三浦の善吉」と全国的に知られた石川善吉という名人もいたそうです。
これでレリーフを作るんですか?
ちょっと信じられないのですが、だからこそ、ものすごく見てみたくなりました。
今回街歩きの目的の1つとなりました。
 ウォーキングマップ
ウォーキングマップ
「京急線で行く旅(2) 浦賀・燈明堂への旅 その1」にて参照のこと。
 ウォーキングスタート
ウォーキングスタート
4.旧浦賀道へ


浦賀コミュニティセンター分館を出た後、旧浦賀道に進みます。
新旧様々な建物が建ち並び、静かな通りです。




街のあちこちに観光案内の説明板が立てられているため、楽しく散策できます。

「へぇー、ほぉー」と言いながら歩いているうちに西叶神社に到着します。
5.西叶神社


創建 : 養和元年(1181)
祭神 : 誉田別尊(応神天皇)、比売大神、息長帯比売命(神功皇后)など
正式名称は「叶神社」。
東浦賀にも叶神社があり、区別するため「西叶神社」と呼んでいます。
文覚上人が源頼朝のために源氏再興を発願し、石清水八幡宮を勧請・創建し、
源氏再興成就した頼朝が文治2年(1186)に叶大明神と尊称したことがこの神社の由緒となっています。

現在の社殿は天保13年(1842)に再建されました。
欄干や天井に施された彫刻は安房国(千葉県)の彫工・後藤利兵衛によるもので、
横須賀市民文化資産に指定されています。

香山栄左衛門永孝の碑(左)。栄左衛門は中島三郎助と共に米艦に乗り、応対・談判を行ったそうです。
写真右は海上安全を願って奉納された碇。

明治天皇が観音崎に行幸の際、西叶神社で休憩されたということで建てられた碑(左)と西叶神社の絵馬(右)。
願い事がものすごく叶いそうです。

そして、社務所にある「鏝絵」。「三浦の善吉」こと石川善吉の作品です。
中国北宋の「司馬温公」が描かれています。
木に登り、誤って大きな水瓶に落ちた童子を近くにいた温公が機転を利かし、
石で水瓶を割って助け出した場面を描いたものだそうです。
なんて繊細な作品なんでしょう。手先の器用さだけで作れる作品とは思えません。
本当にあの「鏝」で作るのだろうかと、ものすごく感心しながら次の「鏝絵」作品を見に行きます。
6.東福寺
西叶神社でお参りを済ませ、東福寺に向かいます。
こちらにも「鏝絵」があります。

浦賀奉行が就任すると必ず参拝したという東福寺。
海難除けの観音様として信仰を集めました。
階段を頑張って上がっていくと本堂があり、そちらに「鏝絵」があります。

鶴・亀・虎・飛天など8点が飾られています。岩田辰之助による昭和7年の作品です。
高い所にあるので近づいて見ることはできませんが、作品が並んだ様子は迫力があって見惚れてしまいます。
(なので先にお参りをしました。)
一度はぜひ見ておきたいアート作品です。
それにしてもどうやって作るのでしょう。
制作過程も見てみたいです。
 お世話になった資料
お世話になった資料
-
横須賀美術館てづくりおさんぽマップ
-
別冊歴史読本54「横須賀歴史読本」
-
「歴史のまち・浦賀 散策の手引き」、「浦賀奉行所と与力・中島三郎助」
(いずれも浦賀コミュニティセンター分館でいただいたもの) -
エイムック3103「横須賀本」
大手旅行ガイドブックさん、浦賀散策コース作って損はないと思いますよ!
次回につづく≫