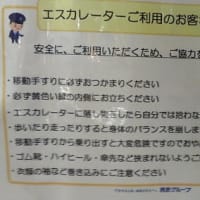7月7日(月)フランス 国立リヨン歌劇場公演
オーチャードホール
【演目】
オッフェンバック/「ホフマン物語」


【配役】
ホフマン:レオナルド・カパルボ/オランピア、アントニア、ジュリエッタ、ステッラ:パトリツィア・チョーフィ/リンドルフ、コッペリウス、ミラクル博士、ダペルトゥット:ロラン・アルバロ/ミューズ、ニクラウス:ミシェル・ロジエ/アンドレ、コシュニーユ、フランツ、ピティキナッチョ:シリル・デュボア/ルーテル、クレスペル:ピーター・シドム/ヘルマン、シュレーミル:クリストフ・ガイ/ナタナエル、スパランツァーニ:カール・ガザロシアン/アントニアの母:マリー・ゴートロ
【演出・衣装】ロラン・ペリー 【舞台】シャンタル・トマ 【照明】ジョエル・アダン
【演奏】
大野和士 指揮 フランス国立リヨン歌劇場管弦楽団 /同合唱団
先月のマリボール歌劇場の「カルメン」に続きオーチャードホールでのオペラ公演は、リヨン歌劇場の「ホフマン物語」。席は先月とほぼ同じ3階Lのバルコニーだが、値段はマリボールの倍! それでもこの値段の差を凌ぐ充実感と大きな感動を味わった。我らがマエストロ、大野和士率いるリヨン歌劇場の公演は、オペラに関わる全ての要素で突出したレベルを聴かせ、見せてくれた。
絶賛したいことだらけの中でも、最初から最後まで心を捉えて離さなかったのは、一つのオベラ作品としての密度の濃さと瑞々しさだ。この多くは指揮の大野和士の手腕に帰するところが大きい。歌心、ドラマ性、繊細さ… 様々な表現が素晴らしいだけでなく、その場に即した的確なタイミングでつなげて行く進行の見事さ。大野はこの大作の隅から隅までを知り尽くし、爪先の小さな動きから全体像に至るまで、あらゆるものを自らのコントロール下に置き、そこに命ある息吹を吹き込む。
こんな大野の意図を演奏陣は余すところなく実現した。その最たるものがオーケストラ。なんと言う芳醇な響きと歌心! 地の底から沸き上がる底力もただものではないし、ウィットに富んだ軽妙な語り口も堂に入り、終始ほれぼれ。
歌手陣のレベルの高さと充実ぶりにも目を見張った。なかでも印象に残ったのは、悪魔の4役をこなしたロラン・アルバロ。凄みのある太い声と冷徹で執拗な歌の表情に身震いした。
この日のホフマン役は、前評判の高かったジョン・オズボーンではなくレオナルド・カパルボ。でもこれがまたスゴイ。張りと存在感に憂いを秘めた声で、最後の最後までスタミナを切らすことなく、憧れ、情熱、狂気を歌い、演じ、聴き手の心を掴み取った。パトリツィア・チョーフィは、艶と潤いのある声で陰と陽を使い分け、4人の女を見事に歌って演じ、ホフマンを虜にした。
その他、どの役も素晴らしかったが、シリル・デュボアが歌ったフランツのクプレとシェーナの洒脱で乗りがよく、巧妙な歌い回しに聴き惚れた。合唱もリアルな表現がストレートに伝わってきて胸を打つ。
オペラのもう1つの要素といえば演出だが、これほど演出で感動することは珍しい。可もなく不可もない演出はオペラの邪魔にはならないが面白くはない。「これどういう意味?」といった思わせぶりだらけの演出や、意表を突くアイディアは時として公演にマイナスに働く。ロラン・ペリーによる今回の舞台は、全てがオペラのストーリーと音楽的効果を高めるために貢献していた。(以下ネタバレ注意)
ペリーの基本コンセプトは、3次元空間の最大限の有効活用にあると言える。その好例が合唱の配置。場面ごとに合唱は1か所に集められたり、左右に分かれたり、更には上下に配置されたり… これらの配置どれをとっても美しく、オペラの情景にしっくり合っていて効果的。第2幕、オランピアの縦横無尽の滑らかな動きも、空間をフル活用したものと言える。或いは、第3幕でミラクル博士が舞台のあらゆる場所から神出鬼没のごとく登場してアントニアを追い詰めていく場面は、見ていていたたまれなくなった。絶大な効果。
舞台の美しさも特筆に値する。全幕通して色彩は暗いモノトーンで統一され、そこに巧みな照明効果で人物が浮かび上がるシーンは絵画的。第3幕はピカソの「青の時代」を思わせるブルーが基調で、これが孤独感や叶わぬ夢を増幅していたし、第4幕では天井から垂れ下がる柔らかなカーテンの波が、水の都ヴェネチアのたゆたう情景を連想させた。
ソロ、合唱、オケ、演出全てが一つのオペラ作品を築き上げることに総動員されて実現した舞台が、今夜の「ホフマン物語」と言っていい。そこには、単なる茶番劇でも夢物語でも、ほのぼのした癒しのお芝居でもなく、情念、妬み、狂気、渇望といった、普段あまり表には出てこない心の奥底に秘めたドロドロしたものが、必要悪としてオペラの底辺をゆっくりと流れていることが示唆され、しかしそれが観る者を突き放すのではなく、全体が「愛」で包まれて潤いがあり、観た後に何とも言えない充実感を残す。
そう、このオペラの極めて印象的な幕開けの演出、真っ暗闇のなか、ハープの調べに導かれて歌われたドンナ・アンナのアリア「おっしゃらないで、愛しい人よ」は、もちろん劇中でオペラのステージに立つステッラを想定してのことだが、それだけでなく、数奇な運命を背負ったドンナ・アンナが歌う美しくも哀しく、気高い歌が、このオペラの全てを物語っているようにも思えた。
オーチャードホール
【演目】
オッフェンバック/「ホフマン物語」



【配役】
ホフマン:レオナルド・カパルボ/オランピア、アントニア、ジュリエッタ、ステッラ:パトリツィア・チョーフィ/リンドルフ、コッペリウス、ミラクル博士、ダペルトゥット:ロラン・アルバロ/ミューズ、ニクラウス:ミシェル・ロジエ/アンドレ、コシュニーユ、フランツ、ピティキナッチョ:シリル・デュボア/ルーテル、クレスペル:ピーター・シドム/ヘルマン、シュレーミル:クリストフ・ガイ/ナタナエル、スパランツァーニ:カール・ガザロシアン/アントニアの母:マリー・ゴートロ
【演出・衣装】ロラン・ペリー 【舞台】シャンタル・トマ 【照明】ジョエル・アダン
【演奏】
大野和士 指揮 フランス国立リヨン歌劇場管弦楽団 /同合唱団
先月のマリボール歌劇場の「カルメン」に続きオーチャードホールでのオペラ公演は、リヨン歌劇場の「ホフマン物語」。席は先月とほぼ同じ3階Lのバルコニーだが、値段はマリボールの倍! それでもこの値段の差を凌ぐ充実感と大きな感動を味わった。我らがマエストロ、大野和士率いるリヨン歌劇場の公演は、オペラに関わる全ての要素で突出したレベルを聴かせ、見せてくれた。
絶賛したいことだらけの中でも、最初から最後まで心を捉えて離さなかったのは、一つのオベラ作品としての密度の濃さと瑞々しさだ。この多くは指揮の大野和士の手腕に帰するところが大きい。歌心、ドラマ性、繊細さ… 様々な表現が素晴らしいだけでなく、その場に即した的確なタイミングでつなげて行く進行の見事さ。大野はこの大作の隅から隅までを知り尽くし、爪先の小さな動きから全体像に至るまで、あらゆるものを自らのコントロール下に置き、そこに命ある息吹を吹き込む。
こんな大野の意図を演奏陣は余すところなく実現した。その最たるものがオーケストラ。なんと言う芳醇な響きと歌心! 地の底から沸き上がる底力もただものではないし、ウィットに富んだ軽妙な語り口も堂に入り、終始ほれぼれ。
歌手陣のレベルの高さと充実ぶりにも目を見張った。なかでも印象に残ったのは、悪魔の4役をこなしたロラン・アルバロ。凄みのある太い声と冷徹で執拗な歌の表情に身震いした。
この日のホフマン役は、前評判の高かったジョン・オズボーンではなくレオナルド・カパルボ。でもこれがまたスゴイ。張りと存在感に憂いを秘めた声で、最後の最後までスタミナを切らすことなく、憧れ、情熱、狂気を歌い、演じ、聴き手の心を掴み取った。パトリツィア・チョーフィは、艶と潤いのある声で陰と陽を使い分け、4人の女を見事に歌って演じ、ホフマンを虜にした。
その他、どの役も素晴らしかったが、シリル・デュボアが歌ったフランツのクプレとシェーナの洒脱で乗りがよく、巧妙な歌い回しに聴き惚れた。合唱もリアルな表現がストレートに伝わってきて胸を打つ。
オペラのもう1つの要素といえば演出だが、これほど演出で感動することは珍しい。可もなく不可もない演出はオペラの邪魔にはならないが面白くはない。「これどういう意味?」といった思わせぶりだらけの演出や、意表を突くアイディアは時として公演にマイナスに働く。ロラン・ペリーによる今回の舞台は、全てがオペラのストーリーと音楽的効果を高めるために貢献していた。(以下ネタバレ注意)
ペリーの基本コンセプトは、3次元空間の最大限の有効活用にあると言える。その好例が合唱の配置。場面ごとに合唱は1か所に集められたり、左右に分かれたり、更には上下に配置されたり… これらの配置どれをとっても美しく、オペラの情景にしっくり合っていて効果的。第2幕、オランピアの縦横無尽の滑らかな動きも、空間をフル活用したものと言える。或いは、第3幕でミラクル博士が舞台のあらゆる場所から神出鬼没のごとく登場してアントニアを追い詰めていく場面は、見ていていたたまれなくなった。絶大な効果。
舞台の美しさも特筆に値する。全幕通して色彩は暗いモノトーンで統一され、そこに巧みな照明効果で人物が浮かび上がるシーンは絵画的。第3幕はピカソの「青の時代」を思わせるブルーが基調で、これが孤独感や叶わぬ夢を増幅していたし、第4幕では天井から垂れ下がる柔らかなカーテンの波が、水の都ヴェネチアのたゆたう情景を連想させた。
ソロ、合唱、オケ、演出全てが一つのオペラ作品を築き上げることに総動員されて実現した舞台が、今夜の「ホフマン物語」と言っていい。そこには、単なる茶番劇でも夢物語でも、ほのぼのした癒しのお芝居でもなく、情念、妬み、狂気、渇望といった、普段あまり表には出てこない心の奥底に秘めたドロドロしたものが、必要悪としてオペラの底辺をゆっくりと流れていることが示唆され、しかしそれが観る者を突き放すのではなく、全体が「愛」で包まれて潤いがあり、観た後に何とも言えない充実感を残す。
そう、このオペラの極めて印象的な幕開けの演出、真っ暗闇のなか、ハープの調べに導かれて歌われたドンナ・アンナのアリア「おっしゃらないで、愛しい人よ」は、もちろん劇中でオペラのステージに立つステッラを想定してのことだが、それだけでなく、数奇な運命を背負ったドンナ・アンナが歌う美しくも哀しく、気高い歌が、このオペラの全てを物語っているようにも思えた。