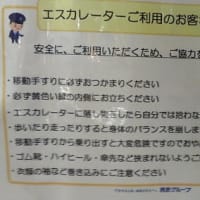11月8日(木)ラドゥ・ルプー(Pf)
東京オペラシティコンサートホールタケミツメモリアル
【曲目】
1.シューベルト/16のドイツ舞曲 D783, Op.33
2.シューベルト/即興曲集 D935, Op.142
3.シューベルト/ソナタ第21番変ロ長調 D960(遺作)
【アンコール】
1. シューベルト/ソナタ第19番ハ短調 D958~第2楽章
2. シューベルト/楽興の時 第1番ハ長調
ルプーが弾くシューベルトやブラームスのCDには愛聴盤がたくさんあるし、以前はリサイタルにもよく出かけた。久々にルプーのリサイタルのチラシを見たと思ったら、何と11年振りの来日リサイタルとのこと。CD録音もずっと行っておらず、伝説のピアニスト化していた。そんなルプーのリサイタル、僕にとっては94年以来17年振りになるが、シューベルトの中でもルプーの魅力がとりわけ発揮されそうな曲が並んだ。暗めに照明を落としたステージにルプーが登場し、3階からなのでよくは見えないが、すっかり白髪でだいぶ歳を取った様子。 ピアノに向かって座った横顔は、ブラームスがビアノを弾いている有名な肖像画を思わせる。
最初の「16のドイツ舞曲」が始まって、音の濃厚さ、重量感がいかにもルプーと感じた。重力に逆らわずに重心を移動させつつ躍りのステップを巧みに踏んでいる様子が、節回しに独特の民族臭を与えていた。スマートな演奏とは対極にあるような味のあるシーン。
パイプ椅子に座ったまま次の即興曲集が始まった。ここではルプー臭を更に濃厚に漂わせ、心の奥底に仕舞い込まれた歌を紡ぎ出していった。元々哀愁を帯びた音楽だが、ルプーの演奏を聴いていると諦念、郷愁、追憶、慰め、などといった内向きなイメージが浮かんでくる。高音のキラキラした装飾は、天から降り注ぐというより、これも内面へと深く沈みこんでいってしまうよう。暗い照明が似つかわしいナイーブで、自分を表にさらけ出すことのない、しかし、聴くものをそんな内面の世界へと引っぱっていく不思議な力の存在を感じた。
後半の遺作のソナタ、ルプーは益々現実の世界を離れ、内面へ内面へと入り込み、魂の世界とでも言える領域に達してしまった感じ。これを聴き手としてどう受け止めていいのか正直戸惑いも覚えた。訥々とした語り口、強音が鳴るはずのところが弱音で弾かれ、クレッシェンドするはずのところが弱々しく減衰する。「魂の世界に達した」とは必ずしもポジティブな意味ではない。ある意味、死を前にした老人が、力なく過去を振り返って、心は既にこの世にあらず、というイメージさえ漂わせている。
まだ60代半ば過ぎ。多少のほころびはあったが、ピアノの腕前が衰えたというほどではないし、充実した響きや、透明な輝きも持ち合わせている。それなのにその演奏が伝えてくるものが、老いと強く結びついてしまうのはどうしてだろう。この遺作のソナタと2曲のアンコールからは、こうした後ろ向きなものをやたらと感じてしまった。こうした演奏を素晴らしいと感じる人が大勢いてもおかしくはないとは思ったが…
ところで、今夜の会場では「16のドイツ舞曲」の途中から「即興曲集」の後半に至るまでずーっと補聴器のハウリングの音が止まなかった。休憩に入る直前に注意を促すアナウンスが入ったが、これだけで音が止む保証はない。休憩時間にホールの人に何とかしてほしいと伝えたら、同じことを言いに来た人が他にもいた。係の人の、何とか音源を突き止めて静かにさせるという熱意が伝わってきて、実際後半の開始直前には、音源が疑われるあたりでスタッフが一生懸命呼びかけて注意を促していた。その甲斐あってか、後半は幸い音は止んだ。もちろん補聴器を着けている本人が十分注意すべきことだが、耳が遠いとハウリングの音はわからないだろうし、こういう場合は近くの人が指摘すべきだろう。演奏会の静寂はみんなで注意しあって実現したいものだ。
東京オペラシティコンサートホールタケミツメモリアル
【曲目】
1.シューベルト/16のドイツ舞曲 D783, Op.33

2.シューベルト/即興曲集 D935, Op.142

3.シューベルト/ソナタ第21番変ロ長調 D960(遺作)
【アンコール】
1. シューベルト/ソナタ第19番ハ短調 D958~第2楽章
2. シューベルト/楽興の時 第1番ハ長調
ルプーが弾くシューベルトやブラームスのCDには愛聴盤がたくさんあるし、以前はリサイタルにもよく出かけた。久々にルプーのリサイタルのチラシを見たと思ったら、何と11年振りの来日リサイタルとのこと。CD録音もずっと行っておらず、伝説のピアニスト化していた。そんなルプーのリサイタル、僕にとっては94年以来17年振りになるが、シューベルトの中でもルプーの魅力がとりわけ発揮されそうな曲が並んだ。暗めに照明を落としたステージにルプーが登場し、3階からなのでよくは見えないが、すっかり白髪でだいぶ歳を取った様子。 ピアノに向かって座った横顔は、ブラームスがビアノを弾いている有名な肖像画を思わせる。
最初の「16のドイツ舞曲」が始まって、音の濃厚さ、重量感がいかにもルプーと感じた。重力に逆らわずに重心を移動させつつ躍りのステップを巧みに踏んでいる様子が、節回しに独特の民族臭を与えていた。スマートな演奏とは対極にあるような味のあるシーン。
パイプ椅子に座ったまま次の即興曲集が始まった。ここではルプー臭を更に濃厚に漂わせ、心の奥底に仕舞い込まれた歌を紡ぎ出していった。元々哀愁を帯びた音楽だが、ルプーの演奏を聴いていると諦念、郷愁、追憶、慰め、などといった内向きなイメージが浮かんでくる。高音のキラキラした装飾は、天から降り注ぐというより、これも内面へと深く沈みこんでいってしまうよう。暗い照明が似つかわしいナイーブで、自分を表にさらけ出すことのない、しかし、聴くものをそんな内面の世界へと引っぱっていく不思議な力の存在を感じた。
後半の遺作のソナタ、ルプーは益々現実の世界を離れ、内面へ内面へと入り込み、魂の世界とでも言える領域に達してしまった感じ。これを聴き手としてどう受け止めていいのか正直戸惑いも覚えた。訥々とした語り口、強音が鳴るはずのところが弱音で弾かれ、クレッシェンドするはずのところが弱々しく減衰する。「魂の世界に達した」とは必ずしもポジティブな意味ではない。ある意味、死を前にした老人が、力なく過去を振り返って、心は既にこの世にあらず、というイメージさえ漂わせている。
まだ60代半ば過ぎ。多少のほころびはあったが、ピアノの腕前が衰えたというほどではないし、充実した響きや、透明な輝きも持ち合わせている。それなのにその演奏が伝えてくるものが、老いと強く結びついてしまうのはどうしてだろう。この遺作のソナタと2曲のアンコールからは、こうした後ろ向きなものをやたらと感じてしまった。こうした演奏を素晴らしいと感じる人が大勢いてもおかしくはないとは思ったが…
ところで、今夜の会場では「16のドイツ舞曲」の途中から「即興曲集」の後半に至るまでずーっと補聴器のハウリングの音が止まなかった。休憩に入る直前に注意を促すアナウンスが入ったが、これだけで音が止む保証はない。休憩時間にホールの人に何とかしてほしいと伝えたら、同じことを言いに来た人が他にもいた。係の人の、何とか音源を突き止めて静かにさせるという熱意が伝わってきて、実際後半の開始直前には、音源が疑われるあたりでスタッフが一生懸命呼びかけて注意を促していた。その甲斐あってか、後半は幸い音は止んだ。もちろん補聴器を着けている本人が十分注意すべきことだが、耳が遠いとハウリングの音はわからないだろうし、こういう場合は近くの人が指摘すべきだろう。演奏会の静寂はみんなで注意しあって実現したいものだ。