いや、今朝も起きしがら図書館から借りて来ている図書で関裕二君の’京都の闇’これを読む。大抵の歴史家は、歴史の捉え方(整理)もよくできず、あやふやな認識で歴史を語り、自分なりの図書として世に送り出している節もあるが、この関君の図書はそれを少し越え、なかなか自分なりの答えは出せずとも、歴史に対し、何故?のような疑問を自らもって解こうとするまあ最初の取っ掛かりとなる歴史認識に対する数々の課題は、自分なりに設けていると言うそんな段階の一書に見える。まあよって、自分なりの疑問が詰まった書と言う事で(答えは出ない)、見るに面白い感じを受ける。
最初の項に、
:何故、古墳時代は京都から始まらなかったのだろう??
と言う自分なりの問い掛けがある。
ん~、僕が当たり前のように知るまあこの日本の歴史史観からすると、関君は(厳しい言い方をするが)未だこの問い掛けもクリアできかねる一青年と言う事になるが、確かに、関君が本文の中にその心情を吐露しているように、
関君:いつも不思議に思っていたことがある。何故、古墳時代は京都から始まらなかったのか?
この、最初の出だしの一文である。そう、関君は、世にある全ての事象物が不思議でならないわけだ!(逆に、弥生時代の終焉とその後の建国事業が何故京都の地ではなく、奈良の地で始まったのか?とも言う)
関君は、始めの取っ掛かりの段階で、水陸の要(要所)となる京都の地が初めに選ばれず、単なる盆地と言う奈良の地が選ばれているか?として、僕が関君が疑問に思っている、古墳国家の時に京の地が何故選ばれないか?に答えようとしている。世の中の大旗と言うのはあって、関君等、歴史家はそこが掴み辛いわけだ!まあどうしても逆転的な目線になるだろうが、小さい目線的にこの問題を解いてゆこうとし、関君はそれを奈良と京都の土地柄として考えてみるも、やはりそれでは上に言うように、
’どうして水陸両用に長ける京の地を始めから使っていれば良かったではないか?
と言う矛盾する結論に至ってしまう。
流石に、これではダメなので、意図も関君はこの難問に見える問いにもう一度やり直し、結論を出さねばならないが、無論今の段階でその答えが出る事はなかなかないのだろう。(いやいや、勉強ばかりしていてもダメだ!)
いやいや、極端に僕がこの著書関裕二君が辿り着けない問題に口を挟むとすれば、やはりこう言うことが言える。関君が次の項に口を出し、問いを解こうと苦闘する中に「古事記」等に連ねられる神話とその天皇と言うものから見る神武東征、この言葉が出て来る箇所がある。普段一般のものからすれば、「古事記」に乗っかる神武東征と言う歴史(神話)はおぼろげな何だか空想っぽい史実で、実際にそんなことがあるのだろうか?と眉を潜めたくなるような案件かもしれない。実は、ほぼ多くの学者が思っているようにこの「古事記」等が見せる神話に見える話しが一つ厄介なのだろう。実際、僕が言うには「古事記」等に厳然と語られる神話と言う話し、これについてのしっかりとした結論が出せないと(認識ができないと)、関君が自分の思考力も導く結論もうろ覚えなもの、そこから意図も脱せず、歴史史観において、全くの自信を持って語ることの出来ない一輩、これで終わってしまうと言う関君の無念は晴らせないであろう。
いや、太安万侶が書いた「古事記」と言う文献は確かにあって僕らの前に立ち出でるが、太安万侶が言うように’神話’と言うのは、あるわけだ!(理解できる人がいるとすれば良いだろうか?)もはや、日本の歴史(平安期)で超の付く天才児太安万侶級の天才でなければ、絵空事にも見える「古事記」等の神話は理解できないかもしれないが、それでも歴史を持って自らの存在を架けようとするのであれば、意図も挑戦せねばならないだろう。
いや、当然歴史家は思っていて、
’神話とは何だろう?’
この問い掛け(謎)は持っている!いや、解決の糸口となる常識的な手法はあって、教える事は出来ず自分で探らねばならないが、いや歴史家は、単なる知的欲求を満たす歴史の史観を持っているだけではダメで、そのほぼ多くの人々が陥る’単なる知的欲求と言う上辺だけに見える好奇心を脱するには、やはり自らに煩悩として支配しているだろうお金あるいは逆○○からやって来る一切自分のことは考え見ない、その生活態度を改めることから始めねばならないのだろう。今で分かり易く言うには、ガリ勉・ガリ仕事だけやって、自分は何でもできた!と、己惚れる自分を止めると言う事だ!
さて、人間にはやることがある。それに向かうとこのような問題から脱することが出来るのだが、いやまだまだ人間自らが持つ根源の生きる道これに真っ向進もうとしない輩は多い。よって、歴史一つ学ぼうとも、簡単には答えを出すことはできないであろう。(浅知恵を披露しているだけだろう)
では、少し前進し、自分の問い掛けは持って文章を書く関君の一書「京都の闇」に対するここでの一感想はここまで!
さようなら~!
最初の項に、
:何故、古墳時代は京都から始まらなかったのだろう??
と言う自分なりの問い掛けがある。
ん~、僕が当たり前のように知るまあこの日本の歴史史観からすると、関君は(厳しい言い方をするが)未だこの問い掛けもクリアできかねる一青年と言う事になるが、確かに、関君が本文の中にその心情を吐露しているように、
関君:いつも不思議に思っていたことがある。何故、古墳時代は京都から始まらなかったのか?
この、最初の出だしの一文である。そう、関君は、世にある全ての事象物が不思議でならないわけだ!(逆に、弥生時代の終焉とその後の建国事業が何故京都の地ではなく、奈良の地で始まったのか?とも言う)
関君は、始めの取っ掛かりの段階で、水陸の要(要所)となる京都の地が初めに選ばれず、単なる盆地と言う奈良の地が選ばれているか?として、僕が関君が疑問に思っている、古墳国家の時に京の地が何故選ばれないか?に答えようとしている。世の中の大旗と言うのはあって、関君等、歴史家はそこが掴み辛いわけだ!まあどうしても逆転的な目線になるだろうが、小さい目線的にこの問題を解いてゆこうとし、関君はそれを奈良と京都の土地柄として考えてみるも、やはりそれでは上に言うように、
’どうして水陸両用に長ける京の地を始めから使っていれば良かったではないか?
と言う矛盾する結論に至ってしまう。
流石に、これではダメなので、意図も関君はこの難問に見える問いにもう一度やり直し、結論を出さねばならないが、無論今の段階でその答えが出る事はなかなかないのだろう。(いやいや、勉強ばかりしていてもダメだ!)
いやいや、極端に僕がこの著書関裕二君が辿り着けない問題に口を挟むとすれば、やはりこう言うことが言える。関君が次の項に口を出し、問いを解こうと苦闘する中に「古事記」等に連ねられる神話とその天皇と言うものから見る神武東征、この言葉が出て来る箇所がある。普段一般のものからすれば、「古事記」に乗っかる神武東征と言う歴史(神話)はおぼろげな何だか空想っぽい史実で、実際にそんなことがあるのだろうか?と眉を潜めたくなるような案件かもしれない。実は、ほぼ多くの学者が思っているようにこの「古事記」等が見せる神話に見える話しが一つ厄介なのだろう。実際、僕が言うには「古事記」等に厳然と語られる神話と言う話し、これについてのしっかりとした結論が出せないと(認識ができないと)、関君が自分の思考力も導く結論もうろ覚えなもの、そこから意図も脱せず、歴史史観において、全くの自信を持って語ることの出来ない一輩、これで終わってしまうと言う関君の無念は晴らせないであろう。
いや、太安万侶が書いた「古事記」と言う文献は確かにあって僕らの前に立ち出でるが、太安万侶が言うように’神話’と言うのは、あるわけだ!(理解できる人がいるとすれば良いだろうか?)もはや、日本の歴史(平安期)で超の付く天才児太安万侶級の天才でなければ、絵空事にも見える「古事記」等の神話は理解できないかもしれないが、それでも歴史を持って自らの存在を架けようとするのであれば、意図も挑戦せねばならないだろう。
いや、当然歴史家は思っていて、
’神話とは何だろう?’
この問い掛け(謎)は持っている!いや、解決の糸口となる常識的な手法はあって、教える事は出来ず自分で探らねばならないが、いや歴史家は、単なる知的欲求を満たす歴史の史観を持っているだけではダメで、そのほぼ多くの人々が陥る’単なる知的欲求と言う上辺だけに見える好奇心を脱するには、やはり自らに煩悩として支配しているだろうお金あるいは逆○○からやって来る一切自分のことは考え見ない、その生活態度を改めることから始めねばならないのだろう。今で分かり易く言うには、ガリ勉・ガリ仕事だけやって、自分は何でもできた!と、己惚れる自分を止めると言う事だ!
さて、人間にはやることがある。それに向かうとこのような問題から脱することが出来るのだが、いやまだまだ人間自らが持つ根源の生きる道これに真っ向進もうとしない輩は多い。よって、歴史一つ学ぼうとも、簡単には答えを出すことはできないであろう。(浅知恵を披露しているだけだろう)
では、少し前進し、自分の問い掛けは持って文章を書く関君の一書「京都の闇」に対するここでの一感想はここまで!
さようなら~!













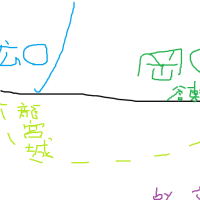

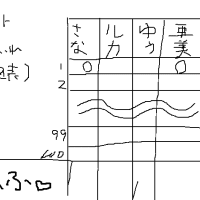




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます