
今月の文楽は、
新作 不破留寿之太夫(ふぁるすのたいふ)
「ヘンリー四世」「ウィンザーの陽気な女房たち」を原作とするシェイクスピア劇の文楽版、
鳴り物入りでの上演でした。
座談会や特設のブログなどで前評判上々、
文楽関係者の力の入れようが痛々しいまででした。
邪念なしで直球で新作を観たかったので、
新聞時評1つだけ見ただけで、
出かけて行きました。
わたしは、
冒頭の舞台装置と、三味線・大小二つの琴の音色、そして胡弓
それだけですっかり魅了されてしまいました。
あの小さいほうの琴は和琴なのでしょうか、
シェイクスピア劇によく似合う
ハープシコードを和風にしたような、
三味線弾きの若手が奏でるあの音色、
それに導かれて、英太夫が語ります、
人の命はやがて消ゆる束の間の灯
誉れありといへども命果つれば益なし
真の武勇は分別にあり
戦せぬこそ分別なり
(床本より)
よくできていると思います。
出だしのこの語りがすべてを物語っています、
それがわかるのは、
物語の結末、主人公ファルスの独白
名誉など所詮浮世の泡沫
名誉とはなんじゃ 言葉じゃ
言葉は空気じゃ 空しいものじゃ
これぞシェイクスピア、名セリフ、
ただ如何せん、春宮=ハル王子=名君といわれたヘンリー5世、
これが日本版の人物に肉薄されてない、しにくいのはわかるが、
どうも彼の三行半、絶縁に説得力がない、
喜劇はたんに滑稽で終わらせないところに喜劇、そして悲喜劇がある、
それには、人物造型の深さが加わらないと…ね
舞台としてはとても面白かった、
上部の空間をフルに生かした居酒屋の場面、
終盤、下駄まで黒衣で覆って客席まで降りて花道を去っていくファルス
―これは杉本文楽での経験から生れた画期的な手法ですね―
 不破留寿之太夫ブログより
不破留寿之太夫ブログより
総じて、文楽一座をあげての意欲的な取り組みに拍手です。
鶴澤清治=監修・作曲
河合祥一郎=脚本
石井みつる=美術
尾上菊之丞=所作指導
藤舎呂英=作調
於:国立小劇場 2014/9/22観劇
追記
小さいほうの琴を和琴では?と思いましたが、
高い音でしたので、雅楽で今に残る和琴は低くかったと思います。弦も多いですし…
どうも二弦琴、チターのような音で大きさもかなり小さいようですので、
こちらでしょうね。
また
胡弓とばかり思っていたものは、文楽固有の奏法?…
太棹を胡弓の弓で弾く大弓(おおきゅう)というものだそうです。
新作 不破留寿之太夫(ふぁるすのたいふ)
「ヘンリー四世」「ウィンザーの陽気な女房たち」を原作とするシェイクスピア劇の文楽版、
鳴り物入りでの上演でした。
座談会や特設のブログなどで前評判上々、
文楽関係者の力の入れようが痛々しいまででした。
邪念なしで直球で新作を観たかったので、
新聞時評1つだけ見ただけで、
出かけて行きました。
わたしは、
冒頭の舞台装置と、三味線・大小二つの琴の音色、そして胡弓
それだけですっかり魅了されてしまいました。
あの小さいほうの琴は和琴なのでしょうか、
シェイクスピア劇によく似合う
ハープシコードを和風にしたような、
三味線弾きの若手が奏でるあの音色、
それに導かれて、英太夫が語ります、
人の命はやがて消ゆる束の間の灯
誉れありといへども命果つれば益なし
真の武勇は分別にあり
戦せぬこそ分別なり
(床本より)
よくできていると思います。
出だしのこの語りがすべてを物語っています、
それがわかるのは、
物語の結末、主人公ファルスの独白
名誉など所詮浮世の泡沫
名誉とはなんじゃ 言葉じゃ
言葉は空気じゃ 空しいものじゃ
これぞシェイクスピア、名セリフ、
ただ如何せん、春宮=ハル王子=名君といわれたヘンリー5世、
これが日本版の人物に肉薄されてない、しにくいのはわかるが、
どうも彼の三行半、絶縁に説得力がない、
喜劇はたんに滑稽で終わらせないところに喜劇、そして悲喜劇がある、
それには、人物造型の深さが加わらないと…ね
舞台としてはとても面白かった、
上部の空間をフルに生かした居酒屋の場面、
終盤、下駄まで黒衣で覆って客席まで降りて花道を去っていくファルス
―これは杉本文楽での経験から生れた画期的な手法ですね―
 不破留寿之太夫ブログより
不破留寿之太夫ブログより総じて、文楽一座をあげての意欲的な取り組みに拍手です。
鶴澤清治=監修・作曲
河合祥一郎=脚本
石井みつる=美術
尾上菊之丞=所作指導
藤舎呂英=作調
於:国立小劇場 2014/9/22観劇
追記
小さいほうの琴を和琴では?と思いましたが、
高い音でしたので、雅楽で今に残る和琴は低くかったと思います。弦も多いですし…
どうも二弦琴、チターのような音で大きさもかなり小さいようですので、
こちらでしょうね。
また
胡弓とばかり思っていたものは、文楽固有の奏法?…
太棹を胡弓の弓で弾く大弓(おおきゅう)というものだそうです。











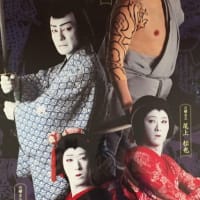



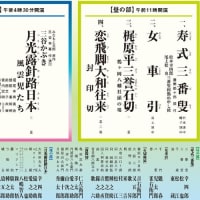

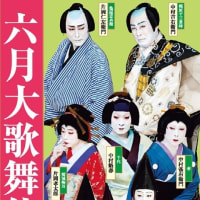


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます