
↑和泉式部
和泉式部が帥宮の思い人として、宮中に住まいしたところは、北の方の住む同じ屋敷、
正妻への配慮ゼロ、
帥宮は、皇子とはいえ、第4 子だからそれほど大きな屋敷はもらえてなかった、
ということでしょうか。
(でも、兄が亡くなっているので、冷泉帝の皇子として東宮となる可能性少なくなかったらしいのですが)
おさまらないのは藤原氏血筋の正妻、
世間の物笑いになったと、宮をなじる様子が、和泉式部日記にあります。
結局恋中の二人には勝てない敗者の正妻、実家に戻ってしまいます。
和泉式部はそこで日記を終えています。
その後、実家に戻った北の方は結局離婚。
式部たち二人は、晴れて堂々一つの御車に乗って葵祭見物、となるわけであります。
大鏡の記述がその典拠ですが、
藤原公任の別荘を二人して花見に出かけ、歌を詠み合う、
当代随一の文化人の集いが催された、
ということもあったようですので、
こういう風雅をふたりは共有していた、
式部はもはや当時の召人という身分を超絶していた存在だった、証拠ですね。
たとえ、東宮后の姉がいるとはいえ、北の方は到底叶わないわけです。
しかし、式部の絶頂はここまで。
この4 年あとには帥宮薨去、宮中をさらざるを得なくなります。
式部のその後は、決して華やかでも平穏でもない、どんな最期を遂げたか、もわからない、
平安期の多くの女性はそうしたものですね。
さて、ここで注目したいのは、正妻だったほうの藤原済時の中の君のその後、
実家に戻ったとはいえ、父親済時はすでに亡くなっており、
姉の後見といっても限界があり、
しかも相続した所領をだまされて失ってしまい、
すっかり零落れてしまいます。
これも大鏡の記述ですが、
恥も外聞もなく、夜中に、当時訪問の礼儀である、人を介することもなく、
しかも貴族とは思えない、牛車に乗らずに、徒歩で(裸足で出歩くのと同じ感覚)…、
門番に物乞いのようなあしらいを受けても意に介することなく、
時の権門道長にすがりついてきたのでした。
かの末摘花がじり貧になっても人々が次々と去っていっても、
叔母がなにを言ってきても、頑として自分を曲げようとしなかったのと対照的です。
紫式部は、零落れた姫君の成れの果ての例に、事欠かなかった当時、
だからこそ、末摘花のような皇室系統の姫君を描きだしたのでしょうね。
因みに、道長はこのなりふり構わぬこの姫の所領を取り戻してあげたそうです。
なんでも懇願してみるものです、と大鏡は言いながら、
あきれ果てた姫君の有様を皮肉ってみせている、ようです。











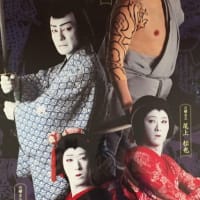



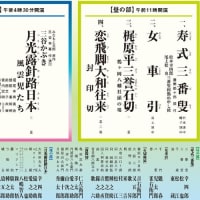

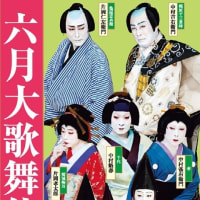


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます