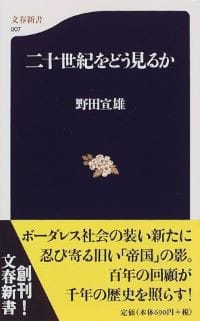 文春新書007とナンバリングされた『二十世紀をどう見るか』は、私の記憶違いでなければ文春新書創刊時にラインナップされた中の1冊である。奥付には「平成10年10月20日 第1刷発行」とあり、このレビューを書いている令和4(=平成34年)年4月12日から見ると23年半ほど前、つまり四半世紀ほど前に出された本、ということになる。
文春新書007とナンバリングされた『二十世紀をどう見るか』は、私の記憶違いでなければ文春新書創刊時にラインナップされた中の1冊である。奥付には「平成10年10月20日 第1刷発行」とあり、このレビューを書いている令和4(=平成34年)年4月12日から見ると23年半ほど前、つまり四半世紀ほど前に出された本、ということになる。
この本は中世まで遡った歴史的背景を踏まえて20世紀という時代を再考し、来たるべき21世紀の世界を展望するという趣旨で書かれたものだ。この中で野田宣雄が主張しているのは、今後の世界の変化の基調にあるのは「中世への回帰」あるいは「新しい中世」であり、その具体的な形が「帝国の再興」だという。ただし、ここで言う「帝国の再興」とは、かつてあった帝国の姿をなぞるように政治権力が凝集する動きを指す。
20世紀末、社会主義体制が次々に崩壊し、ベルリンの壁も壊される中、世界は熱に浮かされたように「もうイデオロギーによる対立の時代は終わった。これからは軍事ではなく経済によって各国が競い合う時代になる。新しいルネサンスが始まる!」といった論調が飛び交っていたが、その「新しいルネサンス」という言葉に私は大きな違和感を感じていた。「ルネサンスとは中世という長い準備期間を経て辿り着いたものだが、我々は新しいルネサンスを生み出すための準備期間を経ていない。だとしたら始まるのは『新しいルネサンス』ではなく、次のルネサンスのための『新しい中世』であるはずだ」と(そして、その考えは今も変わっていない)。
そんなわけで、「中世への回帰」をうたうこの本を、刊行当時、私は飛びつくようにして読んでいた。そして、しばらく前から改めて読んでみたいとずっと思っていた。ただ別の本を読んでいたりして、それが果たせずズルズル来てしまったのだが、ロシアによるウクライナ侵攻(侵略)を受けて再読を決めた次第。
言うまでもなく、四半世紀も前の本なので今となっては的外れな部分も少なからずある。けれども、今でこそこの本の真価を感じる部分もまた少なくない。特にこの本の核心とも言える「第四章 文明と帝国の復活」から「第五章 帝国への志向──ロシアの場合」、ドイツを扱った「第六章 「中欧帝国」の浮上」、そして最終章となる「第七章 中華帝国と日本」は今読んでも遜色ない、というか、むしろ今読むべき内容だと言える。例えば…ということで引用したい箇所は非常に多いが、収拾がつかなくなってしまうので、まずロシアについて記述された内容の一部をピックアップしてみると
(前略)以上のように見てくれば、今世紀初めのロシア革命と今世紀末のソ連邦崩壊という二つの事件が、民族主義的な遠心運動による多民族帝国の解体という意味で、相互にいちじるしい共通性を持っていることが分かるだろう。しかし、両者の共通性は、はたして、この点にとどまるのだろうか。実は、いったん解体をとげた多民族帝国としてのロシアが、分散した領土をかき集めてふたたび多民族帝国として復活をはたすという点でも、二十世紀の初めと終わりにユーラシア大陸の北辺で起こった二つの出来事は、どうやら、互いに似通ってきているように見えるのである。
(前略)こういった一連の動向をつなげてみると、ソ連邦崩壊後のロシアもまた、ちょうどロシア革命後のソヴィエト政権と同様、いったん解体した多民族帝国の再建をめざしていることが知られてくるであろう。レーニンやスターリンといったソヴィエト政権の指導者が「ツァー帝国の領土の回収」を実行したように、エリツィン以下のロシア連邦の指導者は、目下、「ソ連帝国の領土の回収」に乗り出してくると見てよいであろう。
また中国については野田は、東洋史、特に近世中国外交史を専門にした矢野仁一が大正十二年(1923年)に刊行した『近代支那論』を引いて、こう述べる。
矢野によれば、中国には、もともと国境という観念がない。なぜなら、中国はみずからを「世界的帝国」(「ユニヴァーサル・エンパイア」)とみなし、世界はすべて中国の領土と心得ているからである。
もちろん、実際には、中国の政治の及ぶ範囲は限られている。だが、中国人の観念からすれば、そのために生ずる境界は「国境」ではなくて「邉彊(へんきょう)」だとされる。近代的な意味での「国境」は、いうまでもなく二国どうしの境界であり、ともかくも二国が併存する状態を前提にしている。これにたいして、中国人のいう「邉彊」は、その向こう側に別の国家の存在を認めるものではない。本来は世界全体を支配すべき中国だが、目下のところは力が及ばないために、たまたま「邉彊」という暫定的な境界が生じている、というわけである。
ここで見逃してならないのが、こうして中国が伝統的な帝国のタイプの支配に戻るとともに、かつて矢野が指摘した中国の「無国境」的な性格も、ふたたび頭をもたげていることである。周辺諸国との境界を一種の「邉彊」に見立て、あわよくばフロンティアの前進をはかろうとする中国の伝統的な傾向が、二十世紀の末に来て意外に現実性をおびはじめているのである。
とはいえ、「帝国の再興」も過去にあった全ての帝国で同じように起こっているわけではない。例えばトルコなどは、確かにトルコ民族の結集をうたう「大トルコ主義」などが語られたりするものの、野田の言うような、かつてのオスマントルコ帝国の再興を彷彿とさせるような動きは見られない。つまり「中世への回帰」→「帝国の再興」は歴史的必然などではなく、さまざまな政治力学や地政学的要因、民族意識などの条件が揃った時に生じるものと見るべきだろう。
もっと言えば、「中世への回帰」が即、帝国(的なもの)への凝集というベクトルだけで語れるわけでもない。例えば日本の中世は、京の朝廷によるある種の中央集権的なシステムからの離脱という形で始まっている。それは大名、小名といった存在が各地で独自の統治システムを持つようになると、より露わになり、明治新政府が新たに中央集権制を敷くまで日本は実質的に独立国の集合体だった。だから日本にとって「中世への回帰」とは凝集ではなく離散のベクトルが働くことであり、大阪都構想や中京都構想などは(それを主張した政治家の真意はともかく)そうした歴史的文脈の中で見なければならないと私は考えている。
※「本が好き」に投稿したレビューを一部修正したもの。
























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます