以前ついていた先生がこうおっしゃっていました。
「イタリア人は年をとると自分では(楽器を)作らない」
っと。
その頃、F,ビソロッティーさん(お父さんです)の1987年製の楽器を購入検討していました。
今でもすばらしい楽器だったと確信しているのですが、
その購入を検討したお店にビソロさんの2001年製の楽器もありました。
私としてはその楽器に興味はなかったのですが、一応比較の為に置かれていたのです。
試奏の際、後で送れてやってきた先生がその2001年製の楽器を見て、
「その楽器は買うの?やめときなさい」っと厳しい意見をおっしゃられました。
私としてはそんな気持ちはみじんもなかったのですけど、、、
その後、私も先生もビソロさんの1987年製の楽器を弾き、購入を思案する事になりました。
結局買わなかったのですけれど、、
今思えば、あの2001年製の楽器は本人の作ではなかったのかもしれません。
お弟子さんの作か、もしくは本当に自分で作ったけど、腕が落ちてきていたのか。
1987年製の楽器はとても魅力的な楽器で音もスーパーパワフルでした。
ただ、これもただ単に私と先生の好みの問題で本当の真贋なんて分かりませんが。
また、とある楽器(ヴァイオリン)を見ました。
その楽器はAという人の2001年製の楽器なのですけど、見た目はどうも40年以上経ってるっぽい雰囲気でした(家の1980年代の楽器はもっと目新しいです)。
そこで、そのAさんの事をちょこっと検索したら、有名なGさんという人のお弟子さんで、そのGさんはよく弟子のAさんに楽器を作らせ自分の楽器として売っていたそうです。
1966年製のAさんの作品を1946年製のGさん本人の作として買ったという人のブログがありました。
その事が発覚した後、購入した人は、お店(日本のお店)にて全額返還させていただけたとか。
そこで、思ったのは私が見たAさんの楽器は本当に2001年製の楽器だったが、そういう(昔やっていた)少し年代が古くみせるように作ってきた技法がほどこされているんだろうと思ったのです。
ちなみに、、、
こういった経験とネットの情報や実際の耳にした事柄などを総合すると、、、
イタリアの弦楽器製作においては、自分で作らず弟子に作らせ(外注し)それを自分の作品として売るのは昔ながらの伝統だと言う事のようです。
例えばですけど、、、
ビソロさんとかモラッシさんがのラベルが貼られ高額な値段がつけられ、製作証明書まであった場合。
私を含めおそらく多くの人は、それはごく普通にその本人が作った物だと思ってしまいます。
どこでどう間違ったのかは分かりませんが、それはこちらの勘違いだったのでしょうか?
しかし、(例えばですけど、、、)日本の楽器店で、ビソロ作の最新作が入荷、ほとばしる云々、、、
っと言った説明が書かれていれば、それは普通本人作だと思っても仕方ないですよね。
そこで、問題なのは、
その楽器が誰が作ったかという事は証明のしようがないという事です。
言い訳はいくらでもたちます。
「弟子に作らせたが、わしがその品質に問題無いと判断したわしの作品じゃ!」
「いや、これはわしが全部作ったものじゃ!」
なんとでも言えますし、、、中には当然本人が全部作った作品もあるかもしれませんし、、、
しかも、こういった事はストラドの時代から、ごくごく当たり前に行われていたらしく、ストラドの作品でも息子さんやお弟子さんの手が多く入っているようです。
ただ、すごく年代が古い話ですし、お弟子さんも超ビッグネームだったりします。
それが現代でもそうだというだけの話なんですけどね。
比較的近い年代ではBisiach工房なんかが良い例で多くの(後に有名になる)製作者がいて彼らの作品をBisiach工房の作品として売り成功を収めたそうです。
弓作りでも同じみたいで、、、私が持っているHill(イギリス製)の弓もHillというブランド名であってお抱えの製作者は複数します。
フランスの弓作りも、多くの職人さんが出たり入ったり、スタンプは押されていても誰が作ったかは素人には判断は不可能です。
竿は本物だけど、フロッグはどうか分からないとか。
もちろん、売ったお店は、
その楽器がお弟子さんの楽器でも、本人の作品でも、それは工房製だとしても、(性能の良し悪しに関わらず)本人作として売られ、また買い取ってくれるであろうとは思います。
ただ、、、
やっぱり本人が1~10まで作った作品と工房製と呼べるものは分けて欲しいなぁ~と普通に思うんです。
そこら辺をこだわるのは日本人だけでイタリア人にすれば、良い楽器かどうかは自分の目と耳で判断しろってことなのかもしれません。
その判断が難しいんですけどね、、、














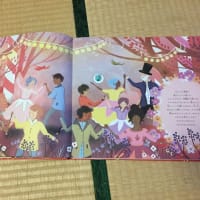
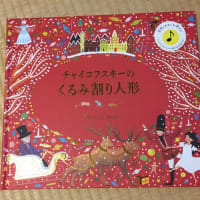




演奏家含め素人がそこら辺を見抜くには、同じ作家の作品を沢山(特に初期)を見るとか(Bはこの頃大病しているから以降の作品は手を出さない・・・)とか情報をしっかり集めて推察するしかありませんね。
ちょっと違うのは「優秀な楽器屋や職人はどこまで本人の手が入っているか、かなり分かっている」という事です。弓もしかりです。弓もラファンの弓鑑定書は「毛箱はオリジナル、ピンは違う」とかちゃんと書きます。なので「なんでも扱う店」「本人の手がしっかり入ったもののみ扱う店」「なんでも扱うがちゃんと説明がある」等、店の傾向も把握するとよいかもです。
そこら辺を把握すると正等な価値や値引き交渉もできるかも・・・!?
なお、ツゲは薬品処理をするので白っぽいのが本来の地肌の色ですよ。この記事は面白いです。
http://shinop.exblog.jp/19327845/
推察の通りなんですね~
>ちょっと違うのは「優秀な楽器屋や職人はどこまで本人の手が入っているか、かなり分かっている」
そのようらしいですね。
私のようなド素人と違い、目のつけどころが違うというか、優秀な楽器屋さん、職人さんは楽器を見る目が違うし、またいろいろな情報を隠し持ってるのだと思います。
楽器に詳しい知り合いの方(プロではないです)が私の弓のピンを外して見て「あっこれギヨームに間違い無いです」というコメントを頂いた事がありました。
本当に私にはさっぱり分かりません、、、
お店の傾向確かにありますね~
私値引きとか交渉が苦手なので、基本買うか買わないかになりますけど、、、
ラファンの鑑定書にはそこまで書いているのですね。
っと言う事は、
そこら辺は書いていない人もいると言う事になりますね。
英語ならなんとなく分かるでしょうから、今後そういう機会があったらよく見てみます。
リンクありがとうございました。
とても面白い記事で参考になりました。
私の楽器に付いているペグも染め直し(?)がなされてない白木の状態なのかもしれませんね。
ただ例えばストラドが手伝ったアマティに文句をつける人は少ないわけで・・・(笑)そう考えると難しいですよね。やはり同じ作者の作品を沢山見て全体のバランスの目を養うしか・・・
コンテンポラリーでも初期の作品は「売れるもの」より「つくりたいもの」を作ってるのでしょうね。売れっ子の前は貧乏で1挺にかける時間もあるはずですし(笑)。
弓に関して言えば、自分は時々メアーを3本触れるチャンスがありますが(cello)うち1本は毛箱はオリジナルでないですがどれもメアーの音します。形は3本とも結構違います。でも長所(欠点)、要素は一緒です。
そういう意味では楽器も弓も、一応同じ作者として出ている真正(といわれるもの)は音の特徴は監修されていると感じます。勿論その中でのランクは違うとは思います。なのでそういった違いがちゃんと値付けに反映されていればOKではないでしょうか。
P,S, ペグの棒部分の穴に合わせて削ったあとの薬品処理は・・・もしかしたらやる人の方が少ないかもしれません。勝手に焼けていくのであまり気にしなくて大丈夫かと思います。
いえ~私はギヨームさんににせ物があるのか無いのか否定も肯定も出来ません。
知り合いの方はその時そのようにコメントされましたので、もしかしたらあるかもしれません。
楽器本体は、
よく聞くお話として初期の頃一生懸命作っている時期と売れっ子で注文殺到の時期とでは、違うと聞きます。
「商売の製作」と「作りたいものを作る熱意での製作」では同じ製作者のラベルが入っていても全然違うらしいと教えてもらいました。
>メアー
とはNicolas Maireさんの事でしょうか?
当方、田舎住まいで楽器にも弓にも見る機会はほとんどないのです。
しかもオールドボウはなかなか目に出来ません。
ですから、弓の性能も真贋もよく分からないのです。
そんな中、
N,Maireさんの弓(Vn)は1本(500万)だけ見たことがあります。
ちゃんと腰の強さがのこって状態は良かったです。
ただ、、あまり良い印象はありませんでした。
後オールドボウっと言える物は、、、
Grand Adam、、、650万以上~でした。すごく腰が強くて楽器をすごく成らすのですが、
弾いていると疲れそうでした。
知り合いのギヨームのGrand Adamコピーにとても似てました。
Charles Peccatte、、、500万でした。腰はちゃんと残っていましたが、剛弓というより飛ばしたりするのに性能を発揮するイメージでした。楽器もけっこう鳴らしました。
E、Sartory、、、これはけっこう良く見かけます。
以前ついていた先生の弓がSartoryの(金?)鼈甲でした。
後は銀黒檀レベルのを数本。
見た弓は、ちゃんと腰が残ってて状態もよかったですけど、そんなに魅力的に感じなかったです。
オリジナルのラッピングが残っているかなにか忘れましたが、一番高いのは600万の値がつけられていて、
お店の人も、(高いと)笑っていました。
ネットでお店を見たり、少ないですが、実際に見たり下中でも、
オールドボウで銀黒檀とかでもけっこうな値段差があり、私には値付けの基準がわかりませんね。
ああいう風に染めるとは全然知りませんでした。
教えていただきありがとう御座いました。
メアーは…そですね、Nicolas Maireです。昔ゲ■ンガスさんに「メイアー」と言っても通じませんでした。きっと「メール」かメアーと言わないといけなかったんだろうかと・・・華奢なのもあればしっかりしたのもあり、パジョーの影響が強いものもあれば形がドミニクに近いのもあり・・・
大体どれもねいろが良く浸透力があります。倍音に歪みがあり・・・そこがまた長所だったりします。足りない魅力とでもいいますか・・・説明は難しいですが。魅惑的系な音です。材料に傾向があるので、確かに好みもあるでしょうね。
Gアダムは素晴らしいと思います。独特の材料。celloだと剛弓が多く飛ばしや扱いに苦労しますが、本当に素晴らしいです。
フランソワはまだ未体験ですが…ドミニクよりシャルルが好きかも(笑)。ドミニクはより機能に重点があり、知り合いは「音は下品」と言っています・・・その方はTルテ所有者なのでかなりハイレベルな意味だとは思いますが・・・
シャルルあたりが本当の意味でギリギリ最後のオールドですね。音もエレガントで尚且つ取り扱いもフレンドリーなので結構プレイヤーは好みます。
Sトリーはモダン弓、最早コンテンポラリーの入り口かと。日本で本当に人気がありますね。棹が強くてまずまず音があるので確かに実用的ですが、個人的にはどうも・・・それでもどうしてもSトリー必要ならジレが得だし。まぁどちらも本来より高すぎると感じます。
…でも1750より前の弓を未体験の人がSトリーを触ったら・・・「これは良い!」と思うと確かに思います。真正オールドが高くなりすぎてプレイヤーの手に渡りにくくなった、時代の流れかと。
本来のオールドは振動が複雑で、握りすぎると倍音が痩せるので握る傾向のソリストやプレイヤーには扱えなかったり毛をパンパンに張らないと弾けなかったりして、それもSトリーが人気あるもう一つの理由かもしれません。扱いはコンテンポラリーbowと同じままで音を持っているという・・・
基準は人気、流通、紙、完品度(棹、毛箱、ボタンが本人か)ですかね。値段差は流通と出所が特に大きいと思います。委託を除き、今はそう簡単に掘り出しモノは・・・
もっとよく弾いてみれば良かったです。
今度機会があればよくよく見てみますね。
Sトリーはすいません。
これはモダンボウでしたね。
ついつい値段が高いので同格に書いてしまいがちです。
ペカットは私もフランソワさんは未体験です。
シャルルさんのほうが好まれるとの事、ぎりぎり最後のオールドボウ世代として価格も少しだけちょっぴり下ですから、お求めやすいのかもしれませんね。
そう言えば、私が見たC,ペカットももともとドイツのプレイヤーが持っていて、ソリストを目指す音大生にコンクールの時にも貸し出していたそうです。
それにしても、なんだか名弓を持ってらっしゃる方が周りにいらっしゃるのですね~~
うらやましいかぎりです。
>・・・でも1750より前の弓を未体験の人がSトリーを触ったら
1750よりまえの弓ってあるのですか?
1850では??
ゴラー、アーマンあたりだと・・・もしかして運がよければ手頃なものに出会えるかもしれません。またドットやタブスあたりも(日本人は仏弓信仰があるので)相対的に手頃かも。
大体1870より以前と以後の作品でははっきり音(の出方)が違う気がします。念頭に置かれると面白いですよ。
また、ふるい弓は「弓の方に自分を合わせる」意識を持つと特に真価を発揮するようです。当時は現代のバランスは要求されてないですので・・・
教えていただきありがとうございます。
>ドットやタブスあたりも・・・
なるほどです。
タブスあたりも古いんですね~
タブスは良くお名前ですし、在庫はわりとありそうです(知りませんが)。
1850年より前の弓を使った事がないと
っというお話は非常に参考になります。
知り合いのプロでも
子供の頃からVnをしているアマチュアの人でも
(たぶん)古い弓の弾き方ではなかったのだと今になって実感しています。
だから私の所有の弓の中でギヨームが「良い」という感想を持たれたのでしょう。
う~ん、、
こんなお話で盛り上がってしまうと、
弓を見たい、欲しい病が発症してしまいそうです(苦笑)
福岡でクラシックフェスタがあるので今度見に(冷やかしに)
行きたくなりました。
いろいろ教えていただきありがとうございます。
とても参考になりました。