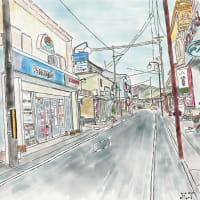周りの景色を見ながら休んでいるところ。



次の地図の黄色の線に沿ってウォーキングを再開します。

天守台から降りて、天守台の北面の石垣のところに行ってみました。
「さかさ地蔵」があります。


天守台の北面石垣の築石として積まれた地蔵で、頭部を奥にうつむきに積み込まれているために「さかさ地蔵」の名で呼ばれています。
郡山城の石垣にはさまざまな転用石材が使われていました。
寺院の礎石、石塔、石仏、日常の石臼などで、石垣の表面だけでも多くのものが確認されています。
石材が乏しかった上に築城を急いだのが原因だと考えられます。
信仰の対象だったものまで容赦なく使うところに、城造りの厳しさが感じられました。
郡山城は、1580年に筒井順慶が初めて城を築きはじめます。
その後、兄の命を受け豊臣秀長が入城します。
その後、徳川譜代大名が続き、最後には柳澤家がずっと続きました。
ここから、もと来た道を戻り、「柳澤文庫」へ向かおうと思います。
戻っていくと、途中で、石垣の修復を行っていました。


ここを過ぎて、次の門をくぐりました。

なにか雰囲気のある門だと感じました。
ここでもすごい石垣が見れます。

修復している石垣が遠くから見れました。


少し歩くと、「柳澤文庫」に来ます。

ここも、月曜日は休館のようでした。
最後の藩主の柳澤保申の跡を継いだ保恵が、明治35年に、同家邸宅の一部を開放して、所蔵する書物などを公開したのが始まりです。
今は、歴代藩主の書画や古文書の展示、地方史の図書館として開かれていました。
閉まっているのは、残念です。(月曜日はどうもダメですね。)

ここから、「市民会館(城址会館)」の方へ行ってみました。

外観は和風ですが、内部は洋風の和洋折衷様式の建物です。
明治41年に、奈良県立図書館として、興福寺境内に建築されました。
昭和45年から大和郡山市市民会館として活用されてきました。
(10年以上前の私のハイキングMAPには、市民会館と記載されています。)
今は、城址会館と呼ばれているようでした。
この辺りでは、イーゼルを立てて、油絵を描く人を数人見かけました。
格好の場所なのでしょう。
ここから、追手門をくぐって外にでます。

目の前に見ているのが「追手門」です。
豊臣秀長が入城した時に築かれたようでした。
門に桐紋(五三桐)がありますが、太閤桐ではないようです。
追手門のすぐ近くに「追手向櫓」がありました。

追手門を守るために造られた櫓です。
反対側の「追手東隅櫓」

物見櫓として使われ、追手門を横矢で守備する重要な櫓でした。
かっては、時を知らせる太鼓が置かれていたようです。
ここから、地図に従って、「三の丸緑地」に向かいます。


近鉄の踏切を渡ります。

三の丸緑地にやってきました。



池の中で、暑さの中、亀もホッとしているようです。

この公園で、お茶を飲んで少し休憩します。
天守台のところから、約50分の時間が経過しました。