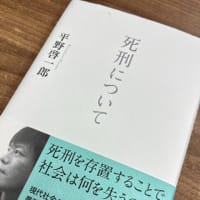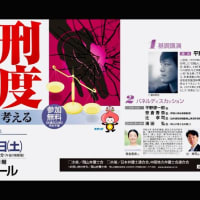このGW、周防正行監督の「それでもボクは会議で闘う」(岩波書店)を読みました。
一般の方にはなじみが薄いと思いますが、厚生労働省の郵政不正事件で明らかとなった大阪地検特捜部の違法捜査、違法取調べを契機として、
取調べの可視化、証拠開示などの刑事司法改革を進めるために、政府の法制審議会に「新時代の刑事司法制度特別部会」というものが設置され、
昨年まで約3年にわたって、議論が行われてきました。
議論の結果は、今年、国会で刑事訴訟法等の改正として実現される予定です。
周防監督は、「それでもボクはやっていない」でちかん冤罪問題を取り上げ、日本の刑事司法の抱える問題点を世に問われたということで、この特別部会にも委員として参加されていました。
この本は、その特別部会での、周防監督の官僚、学者、裁判官、検察官たちとの闘いをレポートしたドキュメンタリーです。
可視化や証拠開示などの法制度、「人質司法」などの刑事司法の問題点など専門的な話も多いのですが、周防監督がわかりやすく説明を加えてくれています。
周防監督や、郵便不正事件で無罪となった厚労省事務次官の村木厚子さんら一般有識者委員が(弁護士以上に)筋を通して奮闘されていたことが良くわかります。
そして、官僚がいかに巧妙であるかも。
本書によれば、特別部会の最後の会議となった2014年7月9日の第30回会議でのこと、
極めて限定的なものとされてしまった可視化について、有識者委員の村木厚子さんが確認のための質問をしたそうです。
その質問とは、
「刑事司法における事案の解明が不可欠であるとしても、そのための供述証拠の収集が適正な手続きの下で行われるべきことは言うまでもないこと」
「公判審理の充実化を図る観点からも、公判廷に顕出される被疑者の捜査段階での供述が、適正な取調べを通じて収集された任意性・信用性のあるものであることが明らかとなるような制度とする必要があること」
この二つの共通認識を踏まえて見直しが行われると受け止めてよいか?
最高検の依命通知によって検察が新たに行うことになった録音・録画制度の運用は、捜査機関による恣意的な録音・録画と言ったものではなく、先に述べた二つの共通認識及び本答申の趣旨に沿うことを目指すものであると理解してよいかどうか?
この質問に対して、法務省選出の吉川幹事は、「村木委員の指摘のとおり受け止めていただいて結構です。」と答え、
最高検選出の上野委員(最高検公安部長)は、「検察の運用につきましても、村木委員のご指摘のとおりご理解いただいて結構でございます。」と答えたそうです。
そして、この答えを受けて、村木さん、周防さんら有識者も、限定された範囲ではあるものの取調べの全過程を録音・録画するという答申案に賛成されたとのことです。
さてさて、その後は・・・・ (ここからは、本書の内容ではありません。)
第30回会議から7か月後の2015年2月12日、最高検は次長検事名で、全国の検事長、検事正に宛てて「取調べの録音・録画を行った場合の供述証拠による立証の在り方等について」(依命通知)を出しました。
その依命通知には、次のようにあります。
「被告人の捜査段階における供述による立証が必要となった場合には、刑事訴訟法322条1項により供述調書を請求する以外に、事案によっては、より効果的な立証という観点から、同項に基づいて、被疑者供述を録音・録画した記録媒体を実質証拠として請求することを検討する。事案の内容、証拠関係、被疑者供述の内容等によっては、当初から記録媒体を同項に基づいて実質証拠として請求することを目的として録音・録画を行っても差し支えない。」
何を言っているかというと、犯罪事実を立証するために、取調室でのやり取りを録音・録画しましょうと、全国の検察官にお触れを出したのです。
えっ!えっ!えっ!
検察庁の録音・録画の運用は、「公判廷に顕出される被疑者供述が、適正な取調べを通じて収集された任意性・信用性のあるものであることが明らかとなるような制度」であって、
「捜査機関による恣意的な録音・録画ではない」と、最高検の上野委員が村木さんに答えたのはどうなったの?
忘れた? 無視? 村木さんや周防さんを騙して賛成させた?
下の根も乾かぬうちに… 二枚舌…
そして、ゴールデンウィーク明けの今日、私が担当する裁判員裁判の2件の公判前整理手続(準備手続)がありました。
どちらの事件でも、検察官が、捜査段階の担当刑事を証人として申請する予定だそうです。
ひとつは被告人がどんな供述をしていたかを立証するため、もう一つは供述調書の任意性を立証するため。
録音録画はもちろんなくて、当時の備忘録・メモ・捜査報告書もないようで、相変わらずの捜査官の証言によって密室での取調べ内容を立証しようと・・・・
特別部会に参加していた検察官や裁判官でさえも、こんな審理は時代遅れ、もはや捜査官の証言では任意性は立証できないと切って捨てていたようなのですが、
京都地裁では、特別部会で否定された旧時代の刑事司法が相変わらず続いています。
まあ、いずれ任意性立証のための警察官の証人尋問なんてすることはなくなっちゃうのでしょうから、最後の記念にお付き合いしましょう。
*捜査官の証人尋問については、結局、被告人との水掛け論にしかならないという批判を受けて、平成17年に刑事訴訟規則が改正され、同規則第198条の4で「検察官は、被告人または被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。」とされました。
特別部会の結論を待つまでもなく、捜査官の証言だけではダメという規則ができているのに、未だに、捜査官を法廷に呼んでくるという旧式な立証しかされていないのが実情です。
*周防さんの本に引用されている、最高裁事務総局刑事局長の今崎委員の発言
「証拠構造上、被害者の供述が鍵となるような事件におきまして任意性が争われた場合には、個々の裁判においては、従来のような取調べ官の証人尋問を中心とした証拠調べではなく、恐らく最も優越した証拠である録音・録画の記録媒体を中心とした証拠調べ、これが行われていくことになるものと思われます。その結果、最終的には、これはもとより個々の裁判ごとの、事案ごとの判断になりますが、録音・録画がない場合には、その取調べで得られた供述の証拠能力に関し、証拠調べを請求する側に現在よりも重い立証上の責任が負わされるという運用になっていくのだろうと思います。この点は、録音・録画義務が課されない事件についても、被疑者の供述が鍵となる事件においては、リスクの意味合いという意味では同様のことが言えるのではないかというふうに考えております。」
要するに、録音録画がない場合に、捜査官を尋問して任意性ありと立証できたなどということは許されなくなりますよということでしょう。
早く国会で法律が成立して、この今崎委員の発言のような時代がくることを期待します。