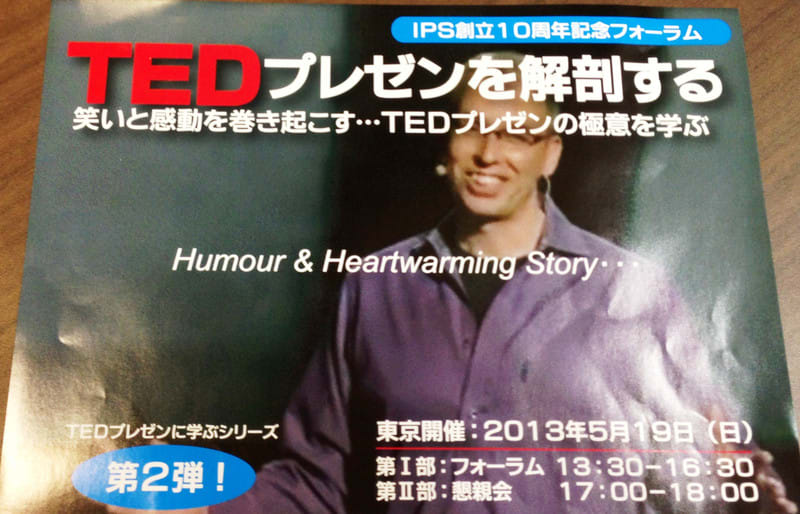4年前、2009年5月21日、刑事裁判を市民の手に取り戻すことが期待され、
裁判員制度が始まりました。
私も、模擬裁判やプレゼン、法廷弁護技術の研究に始まり、ジムに通って体力づくりをしたり、戦略論の研究、オーストラリアの陪審視察、ダイエットにホワイトニング、英会話と様々な取り組みをしてきました。
いくつもの裁判員裁判も経験し、現実の裁判員裁判がどうなのかということが掴めてきたような気がします。
裁判員制度について、報道や最高裁、法務大臣のコメントでは、審理の長期化や裁判員の心理的負担といったことが今後の課題であると言われています。
しかし、そんなことは、大きな問題ではないだろうと思います。
確かに、以前なら起訴されて2ヶ月ほどで終わっていた自白事件が半年近くかかるようになり、その間、被告人が拘束されたままという問題はあります。
遺体写真や殺害時の音声などショッキングな証拠を見せてしまったという問題もあります。
ただ、こうした問題は、裁判員制度というよりも保釈制度の問題であったり、審理のあり方の問題であって、裁判員裁判のそのものの根本的な問題ではありません。
裁判員制度の一番の課題は、
市民のよる裁判が市民の権利を守るための裁判だということの理解が広まっていないこと。
報道や最高裁、法務大臣のコメントは制度の維持だけを考えているように思えてしまいます。
裁判員制度によって実現しようとした刑事裁判、社会のあり方に近づいてきているのか? ということこそ検証されるべきだと思います。

裁判員裁判の弁護人をしてみて感じることは、裁判員となった人たちはとてもよく考えてくれたということです。
そのように考えてくれた裁判員経験者が増えていけば、刑事裁判も社会も変わっていくのではないかと思います。
ただ、裁判員がどのように感じ、どのように考えてくれるかは、法廷にいる裁判官、検察官、そして弁護人次第です。
弁護人がいい加減なことをしていれば、裁判員は、犯罪者はやはり社会から隔離して、排除すべきとしか考えてくれないでしょう。
弁護人がしっかりと説明すれば、裁判員は、犯罪を犯した人でももう一度社会で受け入れることを考えてくれるでしょう。
裁判員裁判を通じて、優しく、寛容な社会をめざしていきたいと思います。