
だれも知らないサンタの秘密
著者:アラン・スノー作 /三辺律子(さんべりつこ)訳
出版社:あすなろ書房
これを見るとサンタの秘密のすべてがわかります!
うちには一応サンタさんが来る事になっています。
上の息子はかなり信じてますが、現実的な下の娘はすでに疑いを持っています。
実は、サンタについては僕も家内も悩んでいるのです。
だって、居ないんですから。
存在しないものをあたかも存在するかのように子供に教えるのは、僕にとっては、ウソをつくことであり、とても心苦しいのです。
肯定的に見れば、子供の頃、サンタさんにわくわくした経験を持つ大人が、自分の子供にも同様のわくわくを与えてあげようという気持ちから、サンタごっこをするわけです。
たしかにそれはそれで良い経験でしょう。
否定的に見れば、子供の物欲を利用した誘導方法だとも言えます。
つまり、「言う事を聞かないとプレゼントがもらえないよ」というものです。
古くドイツ圏では、プレゼントがもらえないばかりか、何らかの罰も用意されていましたから、この手法の歴史も長いですね。
ちなみに、うちでは、言う事をきかないと、サンタの代わりにヨンタが来て、何かショボいもの(食べかけのクッキーとか、枯れ枝など)を置いて行くことになっています。
別に出典はありません。
サンタクロースというのは、イエスの誕生日(とされる日)に、キリスト教の聖人を原型とした架空の人物が、キリスト教と全く関係のない活躍をするという、実に興味深いストーリーです。
その成立の背景は、民俗学的にも実に面白く、また、うちのヨンタのように、「新サンタ伝説」も世界のあちこちで次々と生まれているのです。
今も子供達(特に上の子)が、家内の作ったジンジャークッキーを食べながら、サンタの謎について様々な想像を膨らませています。
まあ、今年のところは良しとしましょうか。
神の謎や矛盾に人はどうしても挑んでしまうのだ。
そして、それが解決された時、人は自らの手で神を殺したことに気付くのだ。
その時にこそ、神は真に顕現するのだ。
などと。
ちなみに、僕のクリスマスはトリの丸焼きです!夜、食べます。楽しみです。
著者:アラン・スノー作 /三辺律子(さんべりつこ)訳
出版社:あすなろ書房
これを見るとサンタの秘密のすべてがわかります!
うちには一応サンタさんが来る事になっています。
上の息子はかなり信じてますが、現実的な下の娘はすでに疑いを持っています。
実は、サンタについては僕も家内も悩んでいるのです。
だって、居ないんですから。
存在しないものをあたかも存在するかのように子供に教えるのは、僕にとっては、ウソをつくことであり、とても心苦しいのです。
肯定的に見れば、子供の頃、サンタさんにわくわくした経験を持つ大人が、自分の子供にも同様のわくわくを与えてあげようという気持ちから、サンタごっこをするわけです。
たしかにそれはそれで良い経験でしょう。
否定的に見れば、子供の物欲を利用した誘導方法だとも言えます。
つまり、「言う事を聞かないとプレゼントがもらえないよ」というものです。
古くドイツ圏では、プレゼントがもらえないばかりか、何らかの罰も用意されていましたから、この手法の歴史も長いですね。
ちなみに、うちでは、言う事をきかないと、サンタの代わりにヨンタが来て、何かショボいもの(食べかけのクッキーとか、枯れ枝など)を置いて行くことになっています。
別に出典はありません。
サンタクロースというのは、イエスの誕生日(とされる日)に、キリスト教の聖人を原型とした架空の人物が、キリスト教と全く関係のない活躍をするという、実に興味深いストーリーです。
その成立の背景は、民俗学的にも実に面白く、また、うちのヨンタのように、「新サンタ伝説」も世界のあちこちで次々と生まれているのです。
今も子供達(特に上の子)が、家内の作ったジンジャークッキーを食べながら、サンタの謎について様々な想像を膨らませています。
まあ、今年のところは良しとしましょうか。
神の謎や矛盾に人はどうしても挑んでしまうのだ。
そして、それが解決された時、人は自らの手で神を殺したことに気付くのだ。
その時にこそ、神は真に顕現するのだ。
などと。
ちなみに、僕のクリスマスはトリの丸焼きです!夜、食べます。楽しみです。















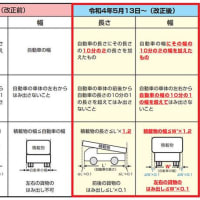




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます