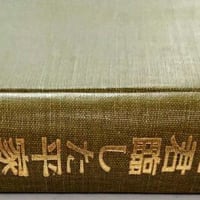沖縄の2つ上にある小さな島の沖永良部島。穏やかな時間が流れるこの島にも、第二次世界大戦時の1944(昭和19)年6月12日に守備隊が派遣され、始めは和泊に駐屯し各学校に宿営していました。7月28日には現地召集(65名)が行われ、守備隊の総員は600名余りになったそうです。
この他にも、機関銃隊と野砲小隊、また原住民で組織する防衛隊員が約300名いて、防衛隊員は陣地構築などに協力したといいます。
武器は十分な装備がなく、数門の野砲、重機関銃、各中隊の軽機関銃、擲弾筒、歩兵銃、手榴弾などで、対戦車爆雷はダイナマイトを探してきて作ったそうです。
防衛隊は玉城地区の黒瀬鍛冶屋で作った粗末な槍で装備し、槍の訓練に励んだといいます。
アメリカ軍の上陸に備えて陣地を構築していきますが、通常は水際で撃滅するのが最良ですが、アメリカ軍は豊富な物資にまかせて上陸地付近を地形が変わるほど猛烈に砲爆撃した後に上陸を敢行するので、海岸や平地での邀撃は不可能なので、越山と大山に洞窟陣地を構築したのだそうです。
住民や防衛隊の絶大な協力によって、戦車豪、攻撃用交通豪、坑道式陣地、機関銃や野砲の掩蓋陣地、蛸壺および兵の待避洞窟などができたそうです。
しかしこれらはコンクリートを使用した堅固な陣地ではないから、敵の砲弾撃には耐えられない。昭和20年4月1日に敵が沖縄上陸した戦闘経過を見ると、玉砕を覚悟しなければならない状況だったようです。
死力を尽くして敵に大きな打撃を与えるために、和泊港で座礁沈没した輸送船から引き揚げたダイナマイトを20センチ立方の木箱に詰め、火縄をつけて戦車爆破用の爆雷を作りました。
1兵1戦車破壊の訓練をし、戦車が来襲しそうな内城入口の三叉路など数か所に、戦車肉薄攻撃陣地も構築したそうです。
戦車肉薄攻撃とは、爆弾を抱えて自ら戦車の下に潜り込んで自分の身体もろとも敵の戦車を爆破させるという恐ろしい手法です。
万が一に備えての陣地と計画ですが、それほど追い詰められた状況になっていたということです。
各中隊の守備分担地域は、越山の東と東北方面を第7中隊が、北西と西方面を内中隊が、残りの世之主神社付近から内城入口方面までを第9中隊が守備しています。
世之主神社付近の谷間に、医務室、第8中隊、第9中隊、機関銃隊、野砲隊などの待避洞窟が30ぐらい、第7中隊の洞窟が楠谷付近に15ぐらい構築されました。
当家のご先祖様が居住していた内城地区は、戦時中はとんでもない状況になっていたのです。
かつて城があった場所も陣地となっていたそうで、そのせいで城があった当時から存在してた石垣なども崩されたりしたようです。
以前に書いた、城跡地(現神社)の下の地下道と東方面に向けての銃眼というのもこの時に作ったものですね。

輸送船の座礁により食料もかなり不足していたようですが、住民は唐芋や野菜を駐屯兵に提出していたそうです。農作業は夜間に行い、昼間は陣営構築から薪運搬などの雑用まで必死に協力し、島の防衛に全力を尽くしたのだそうです。明かりの無い中での夜間の農作業、相当に大変だったと思います。
昼も夜も働きづくめ。自分たちの命を守るために島民は必至だったのでしょう。
そして間もなく8月15日に終戦の玉音放送がラジオから流れました。しかし軍部は事の重大さに驚き、島民に発表しなかったそうです。当時の島には民間にはラジオなどなく、終戦を知らなかったというのです。そのせいで隣の徳之島からの帰還兵を脱走兵と間違える一幕もあったそうです。
終戦が発表されたのは、13日後の8月28日でした。
和泊町誌参照