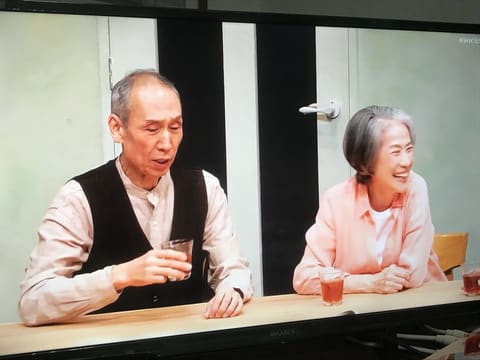■音楽:杉浦英治
■出演:今井朋彦 加藤虎ノ介 川口覚 池岡亮介 小林隆

今回の演目の『4』は、2010年度世田谷パブリックシアター学芸企画<劇作家の作業場>「モノローグの可能性を探る」というワークショップからスタートし、改稿とリーディングを重ね、2012年白井晃氏演出により初演された。その演出は舞台と観客の垣根を取り除き、観客を当事者として巻き込んだ斬新な演出で話題となった。その後、ニューヨークでの英訳版、コペンハーゲンでのデンマーク語訳リーディング上演、韓国では現地カンパニーによる韓国語版上演がソウル演劇祭他にて上演された。
今回放映された作品「4」は、上記の白井演出版ではなく、川村毅劇作40周年記念事業として劇作家川村自らが初めて演出した新演出だ。だが、2020年5月、上演直前にコロナの緊急事態宣言に伴う劇場休館により上演が延期となり、2021年8月にようやく、あうるすぽっと(劇場の名前)で上演になったものを録画したものだ。
この「4」と言う題名は、登場人物の4名(FOUR)に引っかけてある、実際は4+1だが。
F:裁判員
O:法務大臣
U:刑務官
R:確定死刑囚
劇では、4人の俳優が舞台に出てきてくじ引きをする。そして自分の役割が決まる。そして順番に独白(モノローグ)をする。内容は1人の確定死刑囚Rの死刑執行のことについてだ。裁判員はどうして死刑判決にしたのか、法務大臣は死刑執行認可の書面にハンコを押すのか押さないのか、刑務官はこの死刑囚の執行の前に行った別の死刑囚の死刑執行の失敗のことや、自分の役割について、そして死刑囚は自分に死刑執行をしてほしいのかどうかなど。面白いのは一通り独白が終わると、今度はまたくじ引きをしてFOURの役割の変更をして続きをやると言うもの。
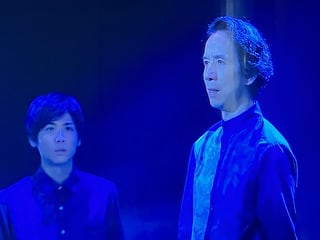
扱っているテーマが重いので、観ていて結局何を言いたいのか、どういう問題提起なのかわかりにくかった。1回観たくらいではわからないのは当然かもしれないが。そして、死刑執行後、最後に+1の男が出てくる。これが死刑囚の父親なのだ。そして父親が独白する。自分も息子を死刑で殺された犠牲者である、と言うようなことを言い、死刑制度のむなしさ、やるせなさ、というようなことを言っているのか。それだけ難しいテーマと言うことだろう。
出演の俳優陣はそれぞれ熱演していた、そして、こんなに長い独白のセリフを暗記するのも大変だろうな、と思った。また、舞台演出であるが、椅子とテーブル、机、死刑囚の座る畳、絞首刑のセットなど非常にシンプルであった。舞台設定より「語り」を重視した演出などであろう。その分、変化に乏しく退屈な印象もした。難しいところだ。
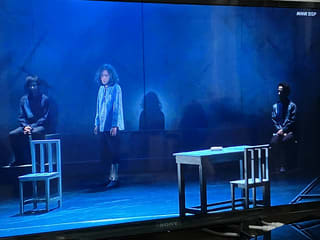
しかし、演劇公演を観ていつも感じるのだが、演劇終了後、カーテンコールで出演者がそろってステージに出てきて「お礼」の挨拶をする時に、なぜ、そろいもそろってしかめっ面をするのだろうか。ほとんどの演劇公演がそうだ。笑顔で手でも振ってもらいたいのだが。