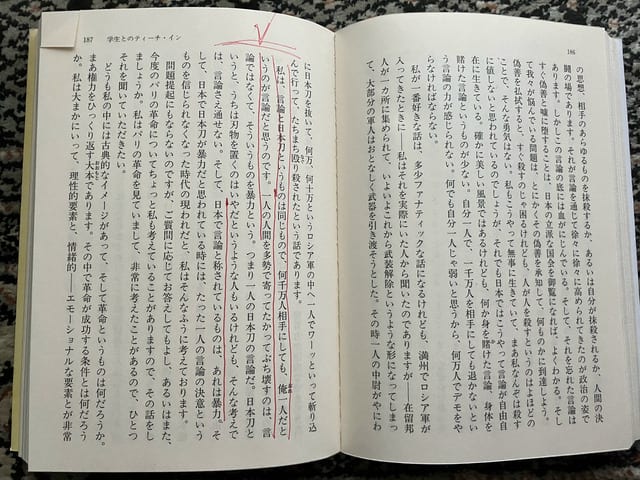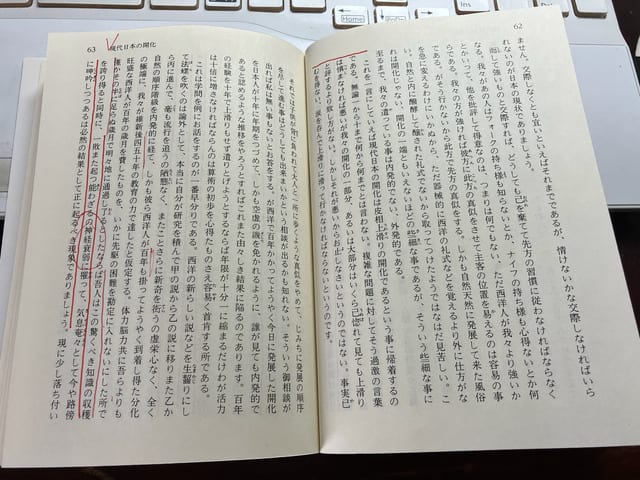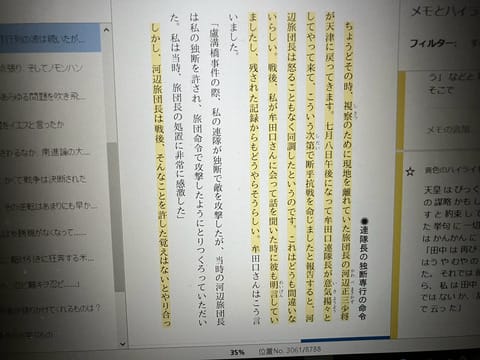宮下奈都著「羊と鋼の森」(文春文庫)をKindleで読んだ。この小説は2015年に刊行され、2016年の本屋大賞を受賞した。
この小説は、調律師をモチーフにした仕事小説であり、主人公の外村(とむら)青年の成長物語である。全然音楽の下地がない外村が、ある日学校の体育館にあるピアノの調律に訪れた板鳥氏の調律を見て衝撃を受け、卒業後、調律の学校に通い、板鳥の勤務する楽器店の調律師になり、周りの先輩たちを見ながら、成長していく物語である。

主人公の外村は幼いころ北海道の山間の集落の中で育った、そして家の近くの牧場で羊が飼われていたことを見てきた。本書の題名「羊と鋼の森」の羊はフェルトの材料、鋼は弦の材料、そして森は外村が育ち、羊が育ってきたところ、というわけだ。
本書を読むまで、ピアノが音を出す仕組みなど詳しく知らなかった。鍵盤を押すと、鍵盤に連動しているハンマーが鋼の弦を打ち、音が鳴る。ハンマーは羊毛を固めたフェルトでできている。ピアノには88の鍵盤があり、それぞれに1本から3本の鋼の弦が張られている、ということも知らなかった。
本書を読んで知ったこと、感じたことなどを書いてみたい
- 最初のほうで上司の調律師の柳と外村が、木の名前の話をし、柳が自分は木の名前など全然知らないが、外村は木の名前だけでなく花の名前も知ってだろう、それはかっこいい、言う場面がある。昔読んだ坂東真理子「女性の品格」(文春文庫)の中で、日本は自然に恵まれた国で、昔から日本人は多くの花や木を愛でてきた、「万葉集」や「古今和歌集」、「枕草子」や「源氏物語」の中には花や木が歌われ、描かれてきたが、現代の日本人はこれらの花や木を知らなくなってきている。そうした木や花の名前を知っているということは、自然をいとおしむ態度につながり、自然を丁寧に観察しているといってよいでしょう、と述べている、これを思いだした。
- 小説の中で、上司の調律師の秋野がどうして調律師になったか話すところがある、彼は、以前はピアニストを目指していたが、あきらめて調律師になったという、そして、外村が担当することになった双子の姉妹もそろってピアノを弾くが、妹は途中でメンタルな理由で弾けなくなり、最後は調律師を目指すという、そのような経歴の人が多いのかなと思った。それはいいことだと思う。最近テレビで「さよならマエストロ」というドラマがあり、その中でマエストロ役の西島秀俊が、指揮者になる人は演奏者の気持ちがわかっていなければならない、何か楽器が弾けなければその気持ちもわからない、と言っていたように思う、そういう意味で調律師もピアニストの気持ちや苦労がわかる人がなるというのはいいことだと思った
- ピアノというのは精密な楽器だということがよく分かった、家庭にあるピアノ、コンサートホールにあるピアノ、結婚披露宴をやるレストランにあるピアノなど、置かれた状況、気象条件など音に影響するいろんな要因を考えて調律しないといい音は出ないというのがよく分かった
- ピアノコンサートを聴きに行く場面があり、上司の秋野がステージに向かって右側に座っている理由が出てくる。私もピアニストの手元が見える左側がいい席だと思っていたし、実際に公演に行っても大体左側の席に多くの観客が座っている、ところが、この小説では、むしろ音に集中するためピアニストが見えないほうが良い、ピアノの大屋根の向きを考えても、音は右手側に伸びると考えるのが自然だ、と外村が考える場面がある。なるほどそういうものかと思った
- 調律師が客の要望を聞き、理解するのはなかなか難しいということがよく分かった、お客さんが、くっきりした音がいい、とか、丸い音がいいとか、その目指す音は人によって感覚が違うので言葉だけで理解するのは難しい、確かにそういうものだろう
- ピアノの音は調律によって変わるが、椅子の高さでも変わること、したがって、調律をするときはお客さんに一度椅子に座って弾いてもらって高さを調整してから調律するという、また、ピアノの脚のキャスターの向きによっても音が変わることが出てくる、実に微妙なものだ
- 上司の板鳥さんが、調律で一番大切なものは、との問いに、「お客さんでしょう」と答えるのは意味深である、確かにそうかもしれない、外村は小説の中で何回か客から、もう来ないでいいとか他の調律師に交代させられている、これはショックだろう、それがなぜなのか小説の中では明らかにされない











調律師の仕事に関して忘れられないのは、むかし、辻井伸行のピアノコンサートに行った時のことだ。コンサートで、突然、ピアノ弾いていた辻井伸行が演奏を中止して、「これは僕の音ではありませんのでこれ以上演奏できません」と言って退場してしまったことだ。観客はみんな呆然として、どうなるのだと驚いた。そのあとどうなったかは覚えていないが、多分、休憩になり、その間に調律師が調律をやり直して、また演奏したのだと思う。本当にびっくりした経験だ。
また、最近でもあったのだが、ピアノの公演に行ってホールに入ると、舞台上で調律師が調律をしている時がある。ということは、調律後の音を確認せずに本番の演奏を始めるということだが、本書を読むと、そんなことがあり得るのかと感じた。そういえば、辻井伸行のケースも確か本番直前まで調律をしていたように思う。調律師が忙しすぎる人気の調律師なのか、何か事情があるのでしょうが、あまり美しい姿でないことは確かだ。
さて、この小説だが、クラシック音楽に興味のある人には読む価値が大きい本であると思うが、純粋に小説として読むと、ストーリーが単調なように感じた。読んでいって意外な展開もなければどんでん返しもない、色恋沙汰も全然ない、もう少し話に起伏があったほうが読んでいて面白いだろうと感じた。











 コメント
コメント