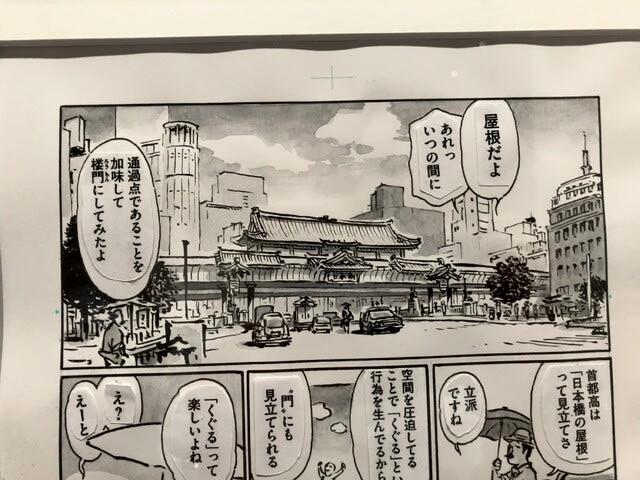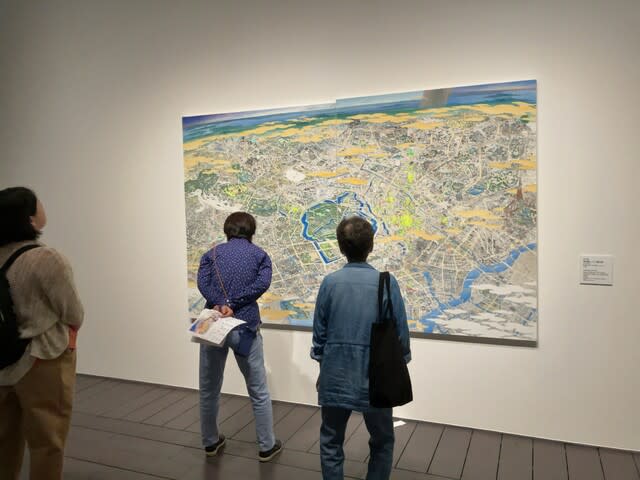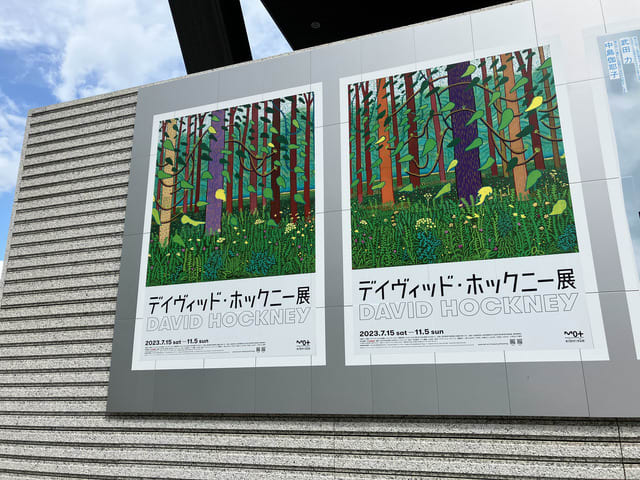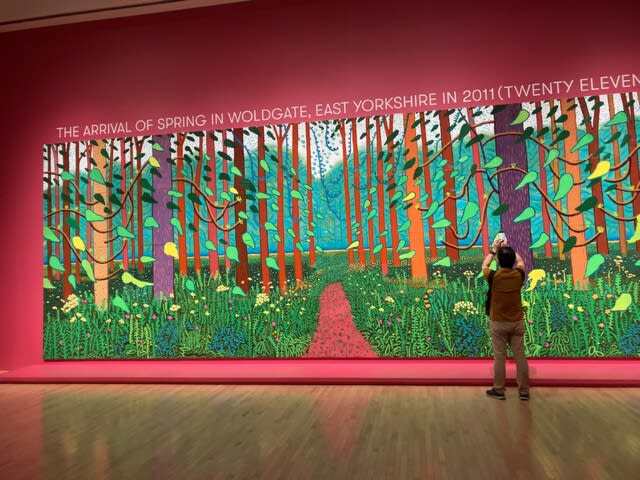当ブログを見ていただいている方の中に、昨日の秋田、青森の大雨による水害にあわれた方がいらっしゃったら、心よりお見舞い申し上げます。これ以上の被害が出ないこと、早急に復旧がなされることを願っています。
港区白金台の松岡美術館に行ってきた。ここは2、3年前に一回来たことがある。

現在は、
- 「江戸の陶磁器 古伊万里展」
- 「モネ、ルノワール 印象派の光展」
などが開催されている。入場料は1,200円、シニア割引はなし。白金台の駅から歩いて10分。大通りからちょっと脇に入ったところにある。美術館に入ってみると来ている人は圧倒的に若いカップルが多かった。白金台という洒落た場所なので若い人たちのデートコースになっているのだろう。シニアは少数派だった。
この美術館は実業家の松岡清次郎氏が1975年に港区新橋にオープンし、その後現在地の松岡氏私邸跡地に新美術館の建設を開始し、1996年に新美術館としてオープンしたもの。松岡氏は若いころから書画骨董を愛し、約半世紀をかけて一大コレクションを築き、80歳を迎えるころ、「優れた美術品は一般に公開し、一人でも多くの美術を愛する人に楽しんでいただこう」という考えでこの美術館を作ったそうだ。


所蔵品はほとんどオークションでの落札によるもので、開館以来、所蔵品のみで展示を行っている。これは蒐集家の審美眼を蒐集作品を通じて観てもらおうとの考えだ。この考えには大いに賛同できる。やはり美術館は創設者らが自腹を切って集めた作品を常設展示するのが基本だと思う。
まず、古伊万里の作品を観た。江戸時代に有田でつくられた磁器を古伊万里という、そして、説明を読むと、江戸時代に約100年にわたって古伊万里は海外にさかんに輸出されたとのこと。それはオランダの東インド会社が中国陶器に代わる商品として大量に注文したためだ。

乳白色の磁肌に清澄な色彩で花鳥や唐人物が絵付けされた「柿右衛門様式」、濃紺の染付に赤と金による桜花や菊など和風な文様が煌びやかな「金襴手様式」は、ヨーロッパの王侯貴族たちを魅了して膨大なコレクションが築かれたそうだ。実際に展示作品を見てみると実に上品で美しい、日本人や花鳥などを書いたものはえも言われぬ美しさがあり好きだ。


柿右衛門様式 や 金襴手様式 に先立ち、有田で焼かれた「初期色絵」は「古九谷様式」ともよばれる、これは古伊万里よりは少し地味であり、大名などに好かれた。さらに、佐賀鍋島藩直轄の窯で焼かれた磁器で、徳川将軍家への献上、諸大名や公家への贈答、そして藩主の自家用の品として、採算を度外視して生産されたのが鍋島焼だ。私は以前、戸栗美術館で開催された鍋島焼の展覧会に行ったことがあるが、鍋島焼の上品な磁器に魅せられた。おくゆかしい気品がある。


次に、印象派の光展だが、モネ、ルノアール、ピサロ、ギヨマン、シニャック、マルタン、リュス、ヴァルタなどの作品が展示されている。印象派の作品は好きだがモネの睡蓮、ルーアン大聖堂の連作は必ずしも好きではない、が、モネの作品には素晴らしいものが多いことは確かだ。また、ピサロなどの風景画も大好きだ。
今日展示されていた作品で良いな、と思ったのは次のものだ。
- 10番:羊飼いの女(ピサロ)
- 12番:カルーゼル橋の午後(ピサロ)
- 34番:水浴の女たち(ヴァルダ)



美術館の中にはこの2つの展覧会の他にあと古代オリエント展もあり、ざっと見たが、入館してから1時間半くらい経つともう疲れて見ていられなくなる。どうして美術館はこう疲れるものなのか不思議だ。じっくり勉強するには半日くらい潰すつもりで、少し観ては少し椅子に座って休み、また観る、というようにすべきなのだろうが、シニアになって時間に余裕ができてもそういう見方ができないのは長年あたふたと働いてきた習性が簡単には変えられない、ということか。
さて、最後にこの美術館の運営面についてコメントしたい
- 松岡美術館は原則として写真撮影OKだ、但し、音の出ない写真アプリを使うことが要求される。これはうれしい。印象派の絵は全部撮影可能となっていた。
- 美術品の展示には作品名、制作年月、制作者などの情報を記載した銘板が添えてある、さらに詳しい情報が書かれている作品もあるが、それらが比較的大きな文字で書かれており、かつ、照明も明るめになっているので非常に見やすかった。特に陶磁器などは照明の制約がないので大変読みやすかった。
- この展示作品説明の銘板だが、さらに素晴らしいと思ったのは、各作品の制作日とともに、その時作者が何歳だったか表示されていることだ。これは大変役に立つ情報である。この美術館のスタッフの方々がきっと自分たちが客として観る場合、何か知りたいかとことん検討している証拠であろう。高く評価したい。
観に行く価値は十分あると感じた。