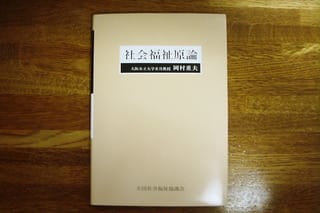
今日の午後のオフ会のことは何度か書きましたが、いよいよ当日になりました。
【現代社会と福祉】
第22回の社会福祉士国家試験からは、従来の「社会福祉原論」という科目に代えて「現代社会と福祉」という科目名に変更になった。この新しい科目は、「社会福祉原論」とはどのように違うのか?
その項目が、厚生労働省から出題基準として示されているが、この具体的な内容を確認できるのは、2010年1月に行われた社会福祉士の国家試験問題である。
昨日、6月11日、介護福祉コース1年生に対する「社会福祉概論」第9講では、第22回の問題27をとりあげた。
この問題に示された選択肢をどのように統合的に理解すればよいのか?最近の文献などを読んで、以下のようなストーリー展開で話した。
○ これまでの「社会福祉」に関する科目(思考方法)では、「高齢者」「児童」といった対象別の縦割り思考に従って学んできたが、これからは、より広く社会問題をとらえる視点が必要だ。それが、「社会的排除」に対応する「社会的包摂」政策という問題の建て方だ。
○ 福祉に関する新しい考え方は、雇用との関連を重視する考え方だ。「ワーク・フェア」に代表される考え方が登場してきた背景を探る。
○ これまで、福祉に関する議論は、財源の問題と切り離して行われてきた。社会保障給付は多ければ多いほど良く、その財源負担(租税と社会保険料)は低い方がよい。
しかし、最近の議論は、「給付付き税額控除」のように、税制と福祉とを一体的に考える方向を目指している。
学生たちが受講後に私のブログに寄せたコメントをみると、この話の展開と、その後での国家試験問題への取組みは難しかったようだ。もう少しわかりやすい話し方を工夫する必要性を痛感した。
【社会福祉の古典を現代に読む】
今日午後、山口県から吉島豊録先生も参加されての「かごしま福祉オフ会」を行います。
私がホストをつとめ、勤務する大学院のセミナー室を借りている。
この先生のブログ「アローチャートでケアマネジメントを」では、最近の先生の研修日程が示されています。
6月 9日 下関市菊川町 社会福祉原論勉強会
6月12日 鹿児島 Twitterオフ会
6月16日 北九州市若松区 アローチャート研修会(基礎編1)
6月16日 下関市 アローチャート事例検討会
6月18日 宇部市 アローチャート研修会(基礎編2)
6月19日 鳥取県米子市 講演
6月23日 北九州市若松区 アローチャート研修会(基礎編2)
6月27日 山口市 介護支援専門員 事前研修会
6月28日 下関市 株式会社セービング職員研修会
7月10日 朝倉市 アローチャート事例検討会(調整中)
7月14日 下関市菊川町 社会福祉原論勉強会
7月16日 大阪府堺市 アローチャート研修会
7月17日 岡山市 アローチャート研修会
7月21日 下関市 アローチャート事例研究会
8月11日 下関市菊川町 社会福祉原論勉強会
8月17日 久留米市 講演会
8月18日 下関市 アローチャート事例検討会
8月20日 宇部市 アローチャート研修会(基礎編3)
8月29日 神奈川県川崎市 アローチャート研修会
8月30日 名古屋 行脚
9月 5日 島根県松江市 アローチャートフォローアップ研修会
9月 6日 島根県浜田市 アローチャートフォローアップ研修会
9月 8日 下関市菊川町 社会福祉原論勉強会
9月11日 山口市 山口県ホームヘルパー協議会研修会
9月15日 下関市 アローチャート事例検討会
9月17日 宇部市 アローチャート研修会(基礎編4)
すさまじい日程です。
この中で、「社会福祉原論勉強会」というのがありますね。
ここでは、岡村重夫『社会福祉原論』(1983年)をテキストにしている。
吉島先生の講義は徹頭徹尾、現場感覚に満ちたものだが(第3736号)、私の頭ではなんどかトライして難しくて読み進めなかったこの『社会福祉原論』と先生の講義のイメージとが結びつかなかった。
2010.06.10
この記事を念頭に、木曜日、本屋さんで本書を見つけて早速購入した。(写真)
【無資格の介護保険施設の管理者】
昨夜の6時間目(18:00~19:30)は、大学院修士課程で「高齢者福祉学」を講義した。講義といっても、聴講者は2名なので、演習形式ですすめています。
昨日、話し合いの中で、議論したのは、
医療機関の管理者は、医師と法律で定められている。
これと同等の重みをもってきた「介護保険施設の管理者」については定めが無い。鹿児島県でよくある事例は、医療法人の理事長であり医療機関の管理者が医師、関連する社会福祉法人の運営する介護保険施設の管理者はその医師の配偶者がなっている。この方は、医師ではないし、社会福祉士や介護福祉士や介護支援専門員でもない。
このような不自然さは何故起きたのか?将来はどうすればよいのか?
こういった議論をしました。
私の頭の中には、漠然とではあるが、介護支援専門員の将来の発展形態こそが、介護保険施設の管理者として法定されるべきでは・・というイメージができてきた。
【縦割りの家族像から総合的な視点で】
昨夜、twitterを読み、ブログで詳しく読んだのは、
想い・思い・おもい ver2 第479回 2010.06.12
の考え方です。
【介護福祉の現場からの視点】
昨日午前の「社会福祉概論」の後半では、「笑わせてなんぼの介護福祉士」の記事を読んでチームごとにコメントをしてもらった。それに対して、ブログ管理者のJUNKOさんから今朝未明に記事の形で再コメントが寄せられています。
笑わせてなんぼの介護福祉士 2010.06.12
【今日午後のオフ会】
今日午後14時に予定しているオフ会には、鹿児島で社会福祉の現場で働く方々が参加される。私や、院生たちは、この議論を聞かせてもらうべく参加します。
ふだん、なかなか自由な本音を聞く機会が無いのですが、私自身は、今日ここで書いたようなことを念頭に参加したいと考えています。
【現代社会と福祉】
第22回の社会福祉士国家試験からは、従来の「社会福祉原論」という科目に代えて「現代社会と福祉」という科目名に変更になった。この新しい科目は、「社会福祉原論」とはどのように違うのか?
その項目が、厚生労働省から出題基準として示されているが、この具体的な内容を確認できるのは、2010年1月に行われた社会福祉士の国家試験問題である。
昨日、6月11日、介護福祉コース1年生に対する「社会福祉概論」第9講では、第22回の問題27をとりあげた。
この問題に示された選択肢をどのように統合的に理解すればよいのか?最近の文献などを読んで、以下のようなストーリー展開で話した。
○ これまでの「社会福祉」に関する科目(思考方法)では、「高齢者」「児童」といった対象別の縦割り思考に従って学んできたが、これからは、より広く社会問題をとらえる視点が必要だ。それが、「社会的排除」に対応する「社会的包摂」政策という問題の建て方だ。
○ 福祉に関する新しい考え方は、雇用との関連を重視する考え方だ。「ワーク・フェア」に代表される考え方が登場してきた背景を探る。
○ これまで、福祉に関する議論は、財源の問題と切り離して行われてきた。社会保障給付は多ければ多いほど良く、その財源負担(租税と社会保険料)は低い方がよい。
しかし、最近の議論は、「給付付き税額控除」のように、税制と福祉とを一体的に考える方向を目指している。
学生たちが受講後に私のブログに寄せたコメントをみると、この話の展開と、その後での国家試験問題への取組みは難しかったようだ。もう少しわかりやすい話し方を工夫する必要性を痛感した。
【社会福祉の古典を現代に読む】
今日午後、山口県から吉島豊録先生も参加されての「かごしま福祉オフ会」を行います。
私がホストをつとめ、勤務する大学院のセミナー室を借りている。
この先生のブログ「アローチャートでケアマネジメントを」では、最近の先生の研修日程が示されています。
6月 9日 下関市菊川町 社会福祉原論勉強会
6月12日 鹿児島 Twitterオフ会
6月16日 北九州市若松区 アローチャート研修会(基礎編1)
6月16日 下関市 アローチャート事例検討会
6月18日 宇部市 アローチャート研修会(基礎編2)
6月19日 鳥取県米子市 講演
6月23日 北九州市若松区 アローチャート研修会(基礎編2)
6月27日 山口市 介護支援専門員 事前研修会
6月28日 下関市 株式会社セービング職員研修会
7月10日 朝倉市 アローチャート事例検討会(調整中)
7月14日 下関市菊川町 社会福祉原論勉強会
7月16日 大阪府堺市 アローチャート研修会
7月17日 岡山市 アローチャート研修会
7月21日 下関市 アローチャート事例研究会
8月11日 下関市菊川町 社会福祉原論勉強会
8月17日 久留米市 講演会
8月18日 下関市 アローチャート事例検討会
8月20日 宇部市 アローチャート研修会(基礎編3)
8月29日 神奈川県川崎市 アローチャート研修会
8月30日 名古屋 行脚
9月 5日 島根県松江市 アローチャートフォローアップ研修会
9月 6日 島根県浜田市 アローチャートフォローアップ研修会
9月 8日 下関市菊川町 社会福祉原論勉強会
9月11日 山口市 山口県ホームヘルパー協議会研修会
9月15日 下関市 アローチャート事例検討会
9月17日 宇部市 アローチャート研修会(基礎編4)
すさまじい日程です。
この中で、「社会福祉原論勉強会」というのがありますね。
ここでは、岡村重夫『社会福祉原論』(1983年)をテキストにしている。
吉島先生の講義は徹頭徹尾、現場感覚に満ちたものだが(第3736号)、私の頭ではなんどかトライして難しくて読み進めなかったこの『社会福祉原論』と先生の講義のイメージとが結びつかなかった。
2010.06.10
この記事を念頭に、木曜日、本屋さんで本書を見つけて早速購入した。(写真)
【無資格の介護保険施設の管理者】
昨夜の6時間目(18:00~19:30)は、大学院修士課程で「高齢者福祉学」を講義した。講義といっても、聴講者は2名なので、演習形式ですすめています。
昨日、話し合いの中で、議論したのは、
医療機関の管理者は、医師と法律で定められている。
これと同等の重みをもってきた「介護保険施設の管理者」については定めが無い。鹿児島県でよくある事例は、医療法人の理事長であり医療機関の管理者が医師、関連する社会福祉法人の運営する介護保険施設の管理者はその医師の配偶者がなっている。この方は、医師ではないし、社会福祉士や介護福祉士や介護支援専門員でもない。
このような不自然さは何故起きたのか?将来はどうすればよいのか?
こういった議論をしました。
私の頭の中には、漠然とではあるが、介護支援専門員の将来の発展形態こそが、介護保険施設の管理者として法定されるべきでは・・というイメージができてきた。
【縦割りの家族像から総合的な視点で】
昨夜、twitterを読み、ブログで詳しく読んだのは、
想い・思い・おもい ver2 第479回 2010.06.12
の考え方です。
【介護福祉の現場からの視点】
昨日午前の「社会福祉概論」の後半では、「笑わせてなんぼの介護福祉士」の記事を読んでチームごとにコメントをしてもらった。それに対して、ブログ管理者のJUNKOさんから今朝未明に記事の形で再コメントが寄せられています。
笑わせてなんぼの介護福祉士 2010.06.12
【今日午後のオフ会】
今日午後14時に予定しているオフ会には、鹿児島で社会福祉の現場で働く方々が参加される。私や、院生たちは、この議論を聞かせてもらうべく参加します。
ふだん、なかなか自由な本音を聞く機会が無いのですが、私自身は、今日ここで書いたようなことを念頭に参加したいと考えています。


























昨晩は眠れなかったようですが、お目覚めはいかがでしょう。
「アローチャート」というものを初めてしりました。
吉島先生のブログを見に行くと「思考過程を『見える化』するとありました。
ご著書では「ケアマネジメント」に利用するということですが、介護職員の思考過程を「見える化」するのに使えないかしら?と思っています。
そのご著書にそんなことは書かれていないでしょうか?
職員について、あの人は認知症の利用者のケアが上手いとか、下手だとか感じさせるのは、その職員の意思決定の差だと思っています。
職員の思考過程をきちんと「見える化」できたら、職員のレベルアップの一助になると思うのですが・・・
アローチャート、興味深いです!
コメント有難うございます。
吉島先生に聞いてみますが
私が読んだ限りでは
十分介護職員の場合にも
応用できると思います。
朝から
伊賀とか
神奈川とかの
twittererからご支援のメッセージが
山口から鹿児島へ
移動中の吉島先生に
届いています。
(吉島先生にかわりで申し訳ありませんが)
アローチャートは、職種関係無しに、
応用のできる方法です。
現に、介護職・福祉職の方々への研修も
行われています。
げんきさんも、是非、アローチャートの仲間に
加わってください。
地理的には、吉島先生と一番近いですね。
笑福会会長作成の会員マップが、
役立ちました
有難うございました。
これからは
ブログの方も
どんどん「横から」「誰でも」
というtwitter方式になりますね。
私は
受講者の感想文に
看護職からの賛同のご意見が多かったので
類推で
答えてみたのです。
というより
ニーズの考え方など
政策系、理論系、調査系の分野でも
応用可能な感じがしてきましたね。
看護職は、
既に30年ほど前から、
「病体関連図」といった、
身体内部の変化を、図式化するという手法が
取られています。
なので、アローチャートには
取り組みやすいと思います。
(私も、そうです)
実は、先日、認知症介護実践研修の申し込みで、現場の課題で「職員の意思決定の差を明確にする必要性」を書きました。
実際、それを研究する場合、どんな手法があるか行き詰っていたところでした。
アローチャート、勉強したくなってきました♪
まずは吉島先生の研修ですね! 7月17日、行けるかなぁ
最近の歯医者さんは職人と言うよりは、どちらかといえば店員さんという感じですが、
職人カタギと学者っぽさを思わせるような印象を受けました。
面白いことに、今日はレントゲンだけ取って帰ってきました。
すごくしっかり説明してくれて、なんか本当に患者のことを考えてくれているように感じました。
好き嫌いが分かれそうな感じですが、僕は好きです。
来週の月曜日行ってきたいと思います。
ご紹介いただきありがとうございました。
岡村重夫『社会福祉原論』全社協は、大学時代、社会福祉概論のテキストでした。つまり、「社会福祉とは何か」を岡村理論から学んだということになります。一応、講義はサボらずに出ていたかいもあり「社会保障でも、医療でもない社会福祉の固有の視点」についてそこそこ理解はできたと自賛していました。
ちなみに、私が教わった社会福祉概論の先生は、岡村理論を『社会福祉学 総論』と『社会福祉学 各論』(柴田書店)で学んでいたようでそちらの方には社会福祉の固有性を図解してあり、『原論』より理解し安いように感じました。
社会福祉の理論は、戦後間もない頃に本質論争がありましたが、「社会福祉とは何か」ということに対する最大公約数のようなものは未だに確立していません。しかしながら、現代の様々な社会福祉問題に対してどのように接近し解決するかという指針は理論的な研究無しにはありえないとも思っています。
最近は、学会発表でも理論研究はめっきり少なくなり、社会学的な統計調査が科学的な価値が高いと思われているのかそちらが増えているような気がします。複雑多様化する社会福祉問題に挑むためにも今一度原理論を再検討するときではないかと考えています。
ちなみに、私は岡村社会福祉理論一本槍ではなく、bonn1979は周知のことと思いますが、ブログで保育所保育問題を語るときは孝橋理論(『社会事業の基本問題』ミネルヴァ書房)を援用しています。理論は社会福祉問題を解析するツールであり、問題解決の指針を与えるものです。こと保育所保育問題では孝橋理論で解析すると明確な解決指針が出て来るのでこの部分に関しては岡村理論より孝橋理論を採用しています。
「ソーシャルワーク実践の岡村理論、政策の孝橋理論」といえば、異論のある人もいると思いますが、一応このようにまとめることができるかと思います。
遅くなりましたが、社会福祉概論で私のブログを取り上げて下さり、どうも有難うございました。
学生さん達のコメントにいつも励まされます。
高知に行って「にわか龍馬ファン」になっている私ですが、「なにかを変える」ためには大きなエネルギーが不可欠で、そこには「痛み」を伴い、「決断」が必要だと思いました。
新しい発想、広く深い知識、若い力、学生の皆さんの最大の武器だと思います。
皆さんが活躍する時代はすぐにやってきます。
机上の勉強と共に「痛み」を現実として受け止め直視し、変えていける強さを若い皆さんに身につけて頂きたいなと思います。
今日はオフ会でしたね。
ツイッターの呟きではとても楽しかったご様子。実りの多い1日だったのでしょうね。
アローチャート、私も学んでみたいです。
病体関連図のこと
ありがとうございました。
話は飛びますが
昨日、吉島先生がノートを取られるのを
みました。
独特の約束事が
あるみたいで
整然と図入りで記載されるご様子
に感心しました。