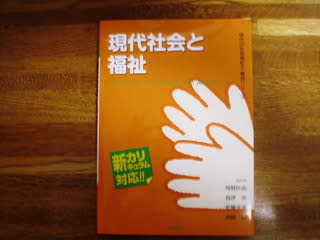
写真は、久美という京都の出版社からでているものです。
現代社会と福祉
【出版社からの案内】
編著者/川村匡由・島津淳・佐橋克彦・西崎緑
体裁 B5版 314頁
本体 本体2200円
送料 370円
コード 978-4-86189-104-5
平成21年度より施行される新教育カリキュラムに対応した「現代の社会福祉士養成シリーズ」の1冊です。
内容を論じるよりも、理解に結び付く「わかりやすさ」や本文の横に側注欄を設けるなどの「使いやすさ」を重視し、見開き完結型としています。
1年間の授業回数に合わせた30回で全体を構成しており、各回冒頭に「学びへの誘い」としてその回の学習のねらいをつけています。
【既存のものとの違い・・古瀬の感想】
先に紹介した(第2742号 2009.04.16)教科書との違い。
・先の教科書は14章建てだったが、今回は、8章で30回分となっている。
*出題基準の構成(大項目では8項目)と同じ。1年分の講義回数と同じ。
・説明は、こちらの方が平易である。
・執筆陣は、こちらの方が実務家あるいは第一線の教員という感じ。
・文献などに工夫(ウェブサイトもあげている)
【目次】
重要と考えられる箇所を詳しくしながら紹介します。
第1章 現代社会における福祉制度と福祉政策
第1回~第5回 佐橋克彦(北星学園大学)
第2章 福祉の原理をめぐる理論と哲学
第6回・第7回 小林恵一(江戸川大学総合福祉専門学校)
第3章 福祉制度の発達過程
第8回 前近代 松倉真理子(福岡教育大学)
第9回~第11回 西崎 緑(福岡教育大学)
第4章 福祉政策におけるニーズと資源
第12回 伊藤真一郎(北海道医療大学)
第13回 若狭重克(藤女子大学)
第5章 福祉政策の課題
第14回・第15回 清重哲男(日本放送協会学園)
第16回・第17回 川村匡由(武蔵野大学)
第6章 福祉政策の構成要素
第18回・第19回 佐橋克彦(北星学園大学)福祉政策の論点
第20回 政府の役割 松尾 亘(日本放送協会学園)
第21回 市場の役割 第22回 国民の役割 川村匡由
第23回 政策決定過程 菊池健志(神奈川県立保健福祉大学)
第24回 福祉供給部門 竹川俊夫(鳥取大学)
第25回 福祉供給過程 清水正美(城西国際大学)
第26回 福祉利用過程 伊藤新一郎
第7章 関連政策
第27回 教育政策 吉田忠司(札幌社会福祉専門学校)
第28回 住宅政策 金 美辰(田園調布学園大学)
第29回 労働政策 原田聖子(江戸川大学総合福祉専門学校)
第8章 相談援助活動
第30回 島津 淳(桜美林大学)・原田聖子
【重要な回数→第14回、第18回、第19回】
この3回分については、キーワードで示しておきます(節の内容に対応)
第14回
1 貧困
2 失業
3 社会的排除
4 孤独から孤立へ
5 リスク
6 社会連帯と社会的包摂
第18回
1 効率性と公平性
2 必要と資源
3 選別主義と普遍主義
4 自立と依存
第19回
1 パターナリズムと自己選択
2 参加とエンパワメント
3 ジェンダー
4 福祉政策の視座
【残された課題:古瀬】
○ 章の間の重複、関連付けにはまだ改善の余地
○ これは、カリキュラム上の課題ですが、「社会保障論」を別立てとしているので、日常生活的な意味での「福祉」の重要な部分(医療・介護・年金)との関係付けが弱い。わかりやすくいえば、「縦割り的」である。このことは、日本の「社会福祉」「社会保障」そして「福祉」をわかりにくくしている。
*上記目次は、明日の勉強会(第3135号)で話し合う参考にもなります。
*後期「社会福祉概論Ⅱ」では、ここに示された事項のうち、他の科目で触れないもの、前期で触れなかったものを扱います。
現代社会と福祉
【出版社からの案内】
編著者/川村匡由・島津淳・佐橋克彦・西崎緑
体裁 B5版 314頁
本体 本体2200円
送料 370円
コード 978-4-86189-104-5
平成21年度より施行される新教育カリキュラムに対応した「現代の社会福祉士養成シリーズ」の1冊です。
内容を論じるよりも、理解に結び付く「わかりやすさ」や本文の横に側注欄を設けるなどの「使いやすさ」を重視し、見開き完結型としています。
1年間の授業回数に合わせた30回で全体を構成しており、各回冒頭に「学びへの誘い」としてその回の学習のねらいをつけています。
【既存のものとの違い・・古瀬の感想】
先に紹介した(第2742号 2009.04.16)教科書との違い。
・先の教科書は14章建てだったが、今回は、8章で30回分となっている。
*出題基準の構成(大項目では8項目)と同じ。1年分の講義回数と同じ。
・説明は、こちらの方が平易である。
・執筆陣は、こちらの方が実務家あるいは第一線の教員という感じ。
・文献などに工夫(ウェブサイトもあげている)
【目次】
重要と考えられる箇所を詳しくしながら紹介します。
第1章 現代社会における福祉制度と福祉政策
第1回~第5回 佐橋克彦(北星学園大学)
第2章 福祉の原理をめぐる理論と哲学
第6回・第7回 小林恵一(江戸川大学総合福祉専門学校)
第3章 福祉制度の発達過程
第8回 前近代 松倉真理子(福岡教育大学)
第9回~第11回 西崎 緑(福岡教育大学)
第4章 福祉政策におけるニーズと資源
第12回 伊藤真一郎(北海道医療大学)
第13回 若狭重克(藤女子大学)
第5章 福祉政策の課題
第14回・第15回 清重哲男(日本放送協会学園)
第16回・第17回 川村匡由(武蔵野大学)
第6章 福祉政策の構成要素
第18回・第19回 佐橋克彦(北星学園大学)福祉政策の論点
第20回 政府の役割 松尾 亘(日本放送協会学園)
第21回 市場の役割 第22回 国民の役割 川村匡由
第23回 政策決定過程 菊池健志(神奈川県立保健福祉大学)
第24回 福祉供給部門 竹川俊夫(鳥取大学)
第25回 福祉供給過程 清水正美(城西国際大学)
第26回 福祉利用過程 伊藤新一郎
第7章 関連政策
第27回 教育政策 吉田忠司(札幌社会福祉専門学校)
第28回 住宅政策 金 美辰(田園調布学園大学)
第29回 労働政策 原田聖子(江戸川大学総合福祉専門学校)
第8章 相談援助活動
第30回 島津 淳(桜美林大学)・原田聖子
【重要な回数→第14回、第18回、第19回】
この3回分については、キーワードで示しておきます(節の内容に対応)
第14回
1 貧困
2 失業
3 社会的排除
4 孤独から孤立へ
5 リスク
6 社会連帯と社会的包摂
第18回
1 効率性と公平性
2 必要と資源
3 選別主義と普遍主義
4 自立と依存
第19回
1 パターナリズムと自己選択
2 参加とエンパワメント
3 ジェンダー
4 福祉政策の視座
【残された課題:古瀬】
○ 章の間の重複、関連付けにはまだ改善の余地
○ これは、カリキュラム上の課題ですが、「社会保障論」を別立てとしているので、日常生活的な意味での「福祉」の重要な部分(医療・介護・年金)との関係付けが弱い。わかりやすくいえば、「縦割り的」である。このことは、日本の「社会福祉」「社会保障」そして「福祉」をわかりにくくしている。
*上記目次は、明日の勉強会(第3135号)で話し合う参考にもなります。
*後期「社会福祉概論Ⅱ」では、ここに示された事項のうち、他の科目で触れないもの、前期で触れなかったものを扱います。

























