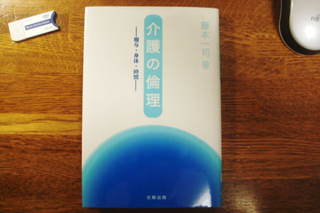
【きっかけ】
昨日5/10 第2839号で、書いたばかりです。
「岩清水日記」で、5/09に紹介されていました。5/10では、写真も。
本書は(岩清水氏のように借りようとして・・)次の図書館の蔵書検索では、蔵書なしでした。
勤務する大学、鹿児島県立図書館、鹿児島市立図書館、鹿児島大学図書館
ですが、鹿児島中央駅の紀伊国屋書店の在庫リストではありました!<それで買いに行きました>
*ちなみに、北海道医療大学(もと勤務)、日本社会事業大学(もと勤務)、東京大学(母校)の図書館でも、この本、藤本氏の本は1冊も蔵書されていません。
→北星大学図書館(札幌)には、蔵書されています。
【難しいことをやさしく説く】
この本の値打ちは、昨日の私の記事で紹介した釧路社会福祉士会の研修記録を読んだ時に予感はしました。
これまでもたくさんの「介護の価値」「介護の哲学」の類の本を読みましたが、本書は、以下の点で群を抜いています。昨夜遅くまでかかって読了しました。
○ 著者自身の体験と思索を基礎にしている(認知症のお母様を7年間介護)
○ 著者の専門は、カント哲学だという。「やさしいことを難しく書いている」のではないか?と、最初は思ったのです。
○ ところが、順を追って、「介護の倫理」を説いていき、今日の記事のタイトルにしたとおり、介護者がお年寄りに応接する仕方はまさに他人に対して人間として応接する場合の基本でもある p.164 とされます。
おそらく、著者は工業高等専門学校で講義されているとのことで、その経験から、このように「難しいことをやさしく」話すことができたのだ、と思いました。
【教育にも応用できる】
他者と接するということでは、私のように教室で学生と接する場合にも、本書で説かれていることは、応用できます。
「学生がわかってくれない」と私が感じたことは、ほんとうは逆で、藤本氏の介護に関する説明の応用では、それは、「私の説明や態度がよくなかったから」学生がそのように反応した・・と考えられます。
「地球は動いている」のガリレオではありませんが、一度、藤本氏の考えが納得できると、人生の途中ですが、多くの失敗のほんとの原因が(他人ではなく私自身だったと!)わかってきます。
→それで、このブログのサブタイトルに、本書から引用したのです。
【目次】
出版社のサイトには、まだ本書がアップされていません。
紀伊国屋の蔵書検索では、各章のタイトルがでています。
次のサイトでは、各節までの詳しい目次がアップされていました。
BLOG_inainabaの2009年2月25日付け記事。
【福祉哲学】
「社会福祉学とは何か?」と、このブログでも追ってきましたが、この本に示されたような人生への対応の仕方を学ぶことだと、昨夜、ガテンがいきました。
個別の介護の対応はもちろん、現在の社会の病弊をも打ち破るきっかけが示されています。
○ 脳による「科学的思考」ばかりを優先してきたことの誤り
○ 認知症への対応の(医学などのような)「科学的対応」が失敗してきた原因
○ 人々の「つながり」にたつ学問としての「社会福祉学」の存在証明
昨日5/10 第2839号で、書いたばかりです。
「岩清水日記」で、5/09に紹介されていました。5/10では、写真も。
本書は(岩清水氏のように借りようとして・・)次の図書館の蔵書検索では、蔵書なしでした。
勤務する大学、鹿児島県立図書館、鹿児島市立図書館、鹿児島大学図書館
ですが、鹿児島中央駅の紀伊国屋書店の在庫リストではありました!<それで買いに行きました>
*ちなみに、北海道医療大学(もと勤務)、日本社会事業大学(もと勤務)、東京大学(母校)の図書館でも、この本、藤本氏の本は1冊も蔵書されていません。
→北星大学図書館(札幌)には、蔵書されています。
【難しいことをやさしく説く】
この本の値打ちは、昨日の私の記事で紹介した釧路社会福祉士会の研修記録を読んだ時に予感はしました。
これまでもたくさんの「介護の価値」「介護の哲学」の類の本を読みましたが、本書は、以下の点で群を抜いています。昨夜遅くまでかかって読了しました。
○ 著者自身の体験と思索を基礎にしている(認知症のお母様を7年間介護)
○ 著者の専門は、カント哲学だという。「やさしいことを難しく書いている」のではないか?と、最初は思ったのです。
○ ところが、順を追って、「介護の倫理」を説いていき、今日の記事のタイトルにしたとおり、介護者がお年寄りに応接する仕方はまさに他人に対して人間として応接する場合の基本でもある p.164 とされます。
おそらく、著者は工業高等専門学校で講義されているとのことで、その経験から、このように「難しいことをやさしく」話すことができたのだ、と思いました。
【教育にも応用できる】
他者と接するということでは、私のように教室で学生と接する場合にも、本書で説かれていることは、応用できます。
「学生がわかってくれない」と私が感じたことは、ほんとうは逆で、藤本氏の介護に関する説明の応用では、それは、「私の説明や態度がよくなかったから」学生がそのように反応した・・と考えられます。
「地球は動いている」のガリレオではありませんが、一度、藤本氏の考えが納得できると、人生の途中ですが、多くの失敗のほんとの原因が(他人ではなく私自身だったと!)わかってきます。
→それで、このブログのサブタイトルに、本書から引用したのです。
【目次】
出版社のサイトには、まだ本書がアップされていません。
紀伊国屋の蔵書検索では、各章のタイトルがでています。
次のサイトでは、各節までの詳しい目次がアップされていました。
BLOG_inainabaの2009年2月25日付け記事。
【福祉哲学】
「社会福祉学とは何か?」と、このブログでも追ってきましたが、この本に示されたような人生への対応の仕方を学ぶことだと、昨夜、ガテンがいきました。
個別の介護の対応はもちろん、現在の社会の病弊をも打ち破るきっかけが示されています。
○ 脳による「科学的思考」ばかりを優先してきたことの誤り
○ 認知症への対応の(医学などのような)「科学的対応」が失敗してきた原因
○ 人々の「つながり」にたつ学問としての「社会福祉学」の存在証明


























私は道半ばです。
私は偶然、見つけた本ですが、とても手に入りにくい本だったのですね(すごい検索ですね)。
なにか、ブログを利用している醍醐味のような気がします。
この本の内容については、「見えていない本質」を
教えていただいたように思います。
私は、介護や社会福祉の専門性を考える時に、
「介護の倫理」のように心を深く理解していることが、
必要ではないかと思うものです。
カリキュラムにはないものかもしれませんが。
このような内容が、教育の場で話し合われたら
意味深いと思いました。