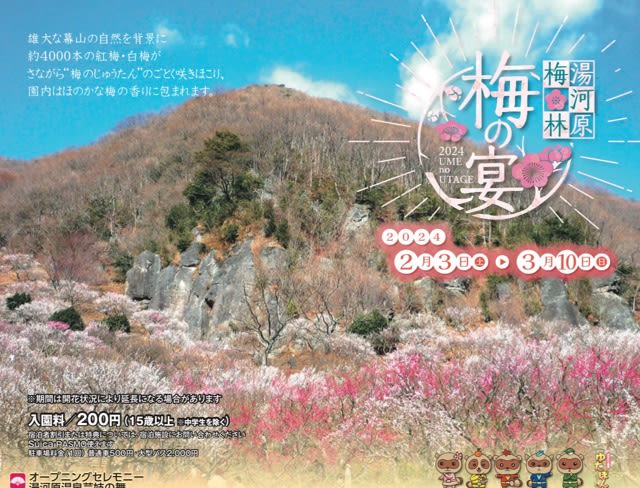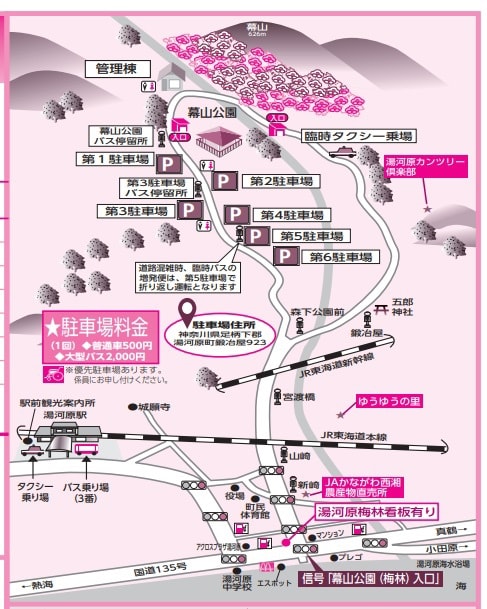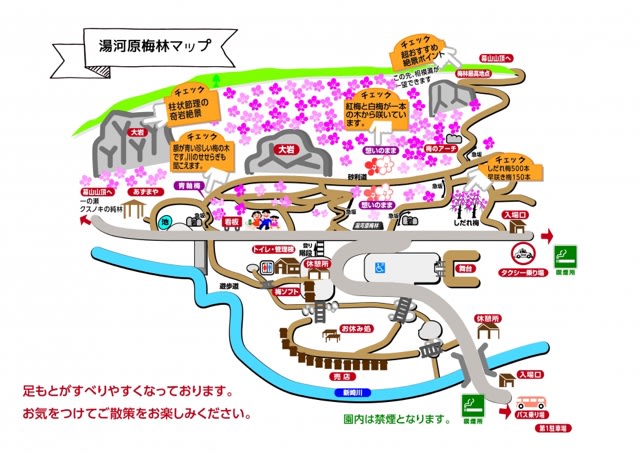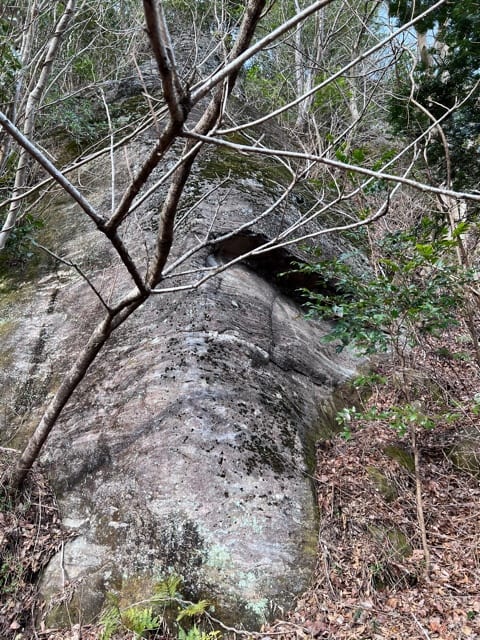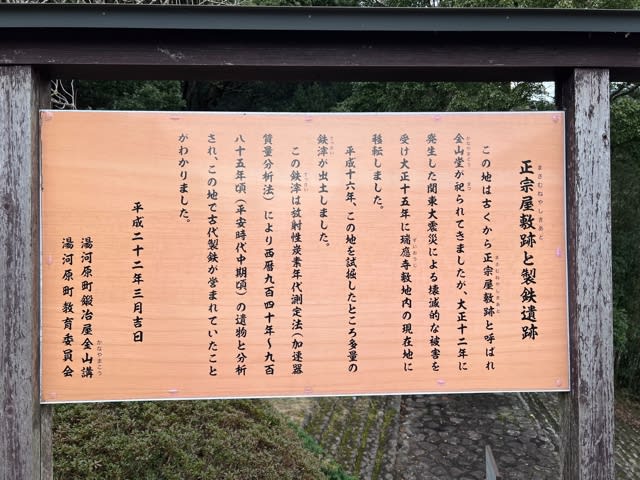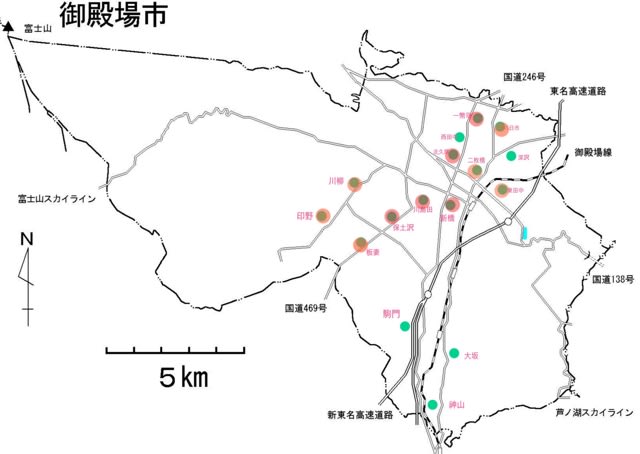梅まつりも最終週を迎えている小田原市。



小田原城址公園ではサル舎の解体工事が行われています。


昨年6月のサル舎の様子

昭和25年10月の小田原市報より


梅林駐車場散歩道の梅もほぼ終わってました。



小田原城址公園ではサル舎の解体工事が行われています。
お猿さんたちは昨年12月に茨城県の東茨城ユートピアに引越し。
この解体工事をもって小田原動物園70年の歴史は幕を閉じることとなります。

猿山も撤去されてただの平地になってしまいました。

昨年6月のサル舎の様子
(カナロコ by 神奈川新聞より)

昭和25年10月の小田原市報より
小田原こども文化博覧会
このこども文化博覧会のために象の梅子が来城。
他にもタヌキ、キツネ、猿、ワニ、孔雀、水鳥などの動物が飼育されたそうです。
小田原動物園の始まりです。
イラストのゆるい感じがたまらないです。特にまんなかの梅子がキュート。
それにしても
ワニって…なにかの間違いでは 笑
私は今はなき城内高校出身で、
授業中にキキーッとかケーッケーッなどとけたたましい動物の声が聞こえるのはしょっちゅう、
というかそれが日常の学校生活でした。
今はお猿さえいなくなって
聞こえる鳴き声といえば小鳥たちくらい。
国指定史跡にふさわしい姿に変貌していくのは嬉しい反面、やはり昔のことを思うとさみしいですね。


梅林駐車場散歩道の梅もほぼ終わってました。