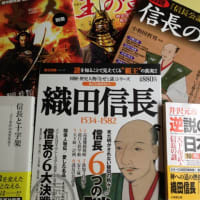「新しい公共」という概念が最近よくいわれています。公共は随分前からあるので「新しい」公共のことです。とうほうTVは「新しい公共」を創ることがひとつのお役目でした。
ICTを活用して地域活性化をするには?という総務大臣懇談会が昨年あってメンバーとして何度も総務省に通いました。そこでも「新しい公共」ということは言われました。わたしはすでにそれ(新しい公共を創ること)をやっていましたので様々な発言のかたちで表現しましたがなかなかわかりにくいようです。何故なら「それはまだ無い」と皆さんが思い込んでいるからです。「もうある」のに。しかしあるとはいっても芽生えでありまだまだこれからです。
今日も「新しい公共」に深みが増しました。とうほうTVは村民スタッフの皆さんで支えられています。今は完全ボランティアです。村民スタッフは総勢2500人の村民がとうほうTVに出て、TVを活用するためにサポートしてくれる人です。サポートするからには当然とうほうTVのことをよく知らないとできません。1年半前に開局して以来、とうほうTVには実に多くの村民に出てもらっています。その中で比較的早くから積極的に関わってもらっている方々に村民スタッフをお願いしています。
当初はわたしと役場の2名を含む6人で集まり企画会議をしてコミュニケーションをとりながらすすめてきました。そのうちに役場にもう一人、民間から70代、80代のお二人が、20代の農家の後継者が、・・と加わり週に1回企画会議として村の出来事や自分たちの経験、身近な出来事、仕事上の企画などなど話してきました。そして収録のスタジオでは実に様々な世代、色々な業界、分野の人達が交流し、とうほうTVがごく普通に公の場になり、そこで話し合われたことが企画になり、事業になり、番組になってきています。
そういう具合に村の日常が自然と番組化する流れが出来てきているのです。今後もっと多くの村民のみなさんが関わってくれるようになるとこれはもうしっかりとした「新しい公共」です。今朝も窯元の成美さんがひょこっと別の用件で寄ってくれたのですが30分程企画会議に参加してくれました。すると今までとは全然違う話しや話題が聞けてまた新たな発見がいっぱいありました。一人増えるだけでこんなにも企画会議が豊かになるのです。そしてここで話合われたことが番組化され、それを村民が見て共有し、その課題が次につながる・・・。新しい公共はこうして村民の知恵を集め、なごやかに議論し、情報共有して、課題を解決する動きになっていきます。
この流れがまさにテレビという生活道具の最も強いところなのです。とうほうTVというテレビを使い切るのは「村民スタッフ団」という新しい公共を創るみなさんです。