
(夕暮れ方の電信柱)
夕暮れ時、日暮れ時って昨日知ったんだけど
日没後の太陽が地平線下、七度二十一分四十秒になった時を言うらしい。
そして十八度になると薄明かりも消えるんだって
このときを天文薄明って呼ぶんだって。
どうやって測ったんだろう
地平線下ぎりぎりに立って分度器ではか~れる訳もなし
黄昏時って誰かが自分を呼ぶ声がするような
そんな時間だから
みんなおうちへ帰ろうね

こんな~日はこんな~日は
バグダッドカフェの「コーリング・ユー」
Jevetta Steele とBob Telson の歌声を聴き比べて

やっぱり朝はJevetta で 夕暮れ時はBobのを絶対聴いてみてよね~よね。
バグダッドカフェって映画は確かにみんなに愛される映画だって思うが
映像もいいけど、るるはジャックパランスが結構印象に残ってて
いい味だしてる親父だなって

夕暮れ時にカウチにビールと魚肉ソーセージまるかじりで見たいよね
誰かが呼んでいる
いかなきゃ
いかなきゃ
いかなきゃ
って思わせる
この歌は本当に罪だよ

きっと冥王星が泣いて呼んでいる
声なんじゃないの

何で仲間はずれになっちまったのかと
アメリカじゃ2006年のワードオブイヤーに
プルート(冥王星)させるを「降格させる」って意味で
みんなが使ってるって言うからさ
本当にかわいそうよ冥王星さん
きっと呼んでるよ
黄昏時に呼んでると思うよ
「何故
 何故なの
何故なの
 って」
って」そして2007年にはもうそんなことがあったっけ
って感じで忘れられてゆくんだよ
七度一分四十秒にたそがれるよ~
冬のそらに地平線すれすれにちょっと出て
すぐに沈んでしまう星があって
横着星って呼ぶらしいカノープスって星なんだそう
中国では南極老人星って言うって
この星が地平すれすれに見えるときは
天下泰平の吉兆だというから
この星を見ると長生きするという伝説がある
80光年の距離にある、探してみよう
カノープスはシリウスに次いで
二番目に明るい星だっていうから見つけやすい?
るるは冬生まれで山羊座なんだけども
山羊座のシンボルマークは
山羊だと思っていたら
よーくみたら尻尾がなくて
魚の尾っぽなんだよ~
なんか古代バビロニアじゃ雨季とかで
ユーフラテス川も氾濫じゃ~
って季節で、もともと山羊座のシンボルは
森と羊と羊飼いの神パーンだそう
でも
きっと川が氾濫しても溺れないようにって
下半身は魚になっておるにちがいないべ
あなたの星座のシンボルはどうよ?
そんなこんなでもう暗闇の時間よ
誰も呼んでない?
泳いでゆくわよ
あなたのもとへ














 温泉にでも浸かっていたのか?
温泉にでも浸かっていたのか? いい感じだと思うから
いい感じだと思うから
 の軌道敷き跡の公園
の軌道敷き跡の公園
 悩んだが
悩んだが



 に言うと
に言うと 」
」
 」
」



 。
。






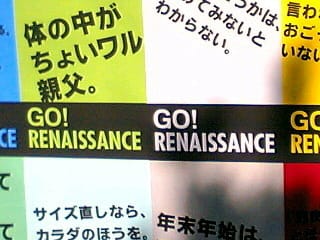






 。
。
 。
。