(1990/バリー・レヴィンソン監督・脚本・共同製作/アーミン・ミューラー=スタール、ジョーン・プロウライト、エイダン・クイン、レオ・ヒュークス、エリザベス・パーキンス、イライジャ・ウッド、ケヴィン・ポラック/127分)
 脚本も書いたレヴィンソン監督はボルチモアの出身らしいので、多少なりとも自伝的な要素もあるのでしょう。
脚本も書いたレヴィンソン監督はボルチモアの出身らしいので、多少なりとも自伝的な要素もあるのでしょう。
時代はテレビが一般家庭に普及していった頃ですから1950年代。撮影当時9歳だったイライジャ・ウッド扮するマイケル坊やがレヴィンソン監督の分身ではないでしょうか。
ヨーロッパからアメリカに移民としてやってきたロシア系ユダヤ人一家のファミリー・ヒストリーであります。
『1914年、私はアメリカに渡った。そこは見たことのないような美しい街だった』
映画はそんなモノローグで始まりますが、語っているのはマイケル君のお祖父ちゃんサム・クリチンスキー(スタール)。フィラデルフィアで船を降り列車でボルチモアに向う。そこでサムを待っていたのは4人の兄弟たち。既に壁紙職人としてボルチモアで生活基盤を築いていた彼らに仕事を教わりながらサムもアメリカ人になっていったのでした。
毎年感謝祭には兄弟達が家族を連れて集まるのが習わしで、その時にサムが小さな孫たちに聞かせてあげる一家の昔話が序盤に語られるのです。
そこはボルチモアのアバロンという地区。2世帯が一つ屋根の下で暮らす幸せな時代のお話です。【原題:AVALON】
楽器演奏が得意だったサム兄弟は、仕事が休みの日には街のダンスホールで揃ってバイオリンを演奏した。サムが後に妻となるエヴァ(プロウライト)と知り合ったのもそのダンスホールだった。やがてサムは自身でもナイトクラブを経営するようになり、息子ジュールズ(クイン)にも楽器を教えてやろうとしたがジュールズは興味を示さなかった。ならばとサムは息子には職人ではなくセールスマンになることを勧めた。
『セールスマンに商品は関係ない。自分を売り込むのさ』
ある日、ジュールズは従兄弟のイジー(ポラック)と一緒にそれぞれの彼女を連れてサムの店にやってきたが、それはジュールズと恋人アン(パーキンス)が結婚した日だった。イジーとジュールズは結婚証明書の姓名の欄に奥さんの名前を書いていた。クリチンスキーよりも聞こえが良い名前にしたというのだ。サムは怒ったが、やがて怒りは子供たちの結婚の喜びに消えていった。
ある年の暮れ、ジュールズはマイケルを連れて車でセールスに出かけたが、暗くなったころ通りで強盗にナイフで刺された。仕事終わりのセールスマンが現金を持っている事を知っていたのだ。車の中で父を待つマイケルの目の前の出来事だった。
病院に搬送されたジュールズは一命をとりとめたが、それを機に訪問販売ではなく店を持つことにした。イジーと共同でディスカウント・デパートを開くことにしたのだ。余計なサービスは省いて調理鍋や洗濯機、電化製品を並べたお店。ディスカウントという言葉さえ珍しい時代だったが、彼らのイニシャルを使った店「K&K」は戦後の好景気の波に乗って瞬く間に繁盛するようになるのだが・・・。
何か物語を転がしていく事件が最初に語られるようなドラマではなく、冒頭から昔話が緩やかに始まって、サムの兄弟げんかや嫁と姑の確執なども挟まれて、まるでアメリカ版「渡鬼」のような血縁関係の面倒くささも感じたのですが、徐々にこれはレヴィンソン監督のノスタルジーなんだと思いました。
貧しい時には家族肩寄せ合って暮していたのに、(社会だけでなく個人も)豊かになっていった時代には、逆に家族の絆が脆くなっていった。そんな空気を感じる人もいるでしょうが、僕にはそれらも含めて監督の家族の歴史を懐かしむ想いが作らせた映画のような気がします。
家族皆でテレビの前に集まった時代。
お祖父ちゃんとお祖母ちゃんと孫が一緒に生活していた時代。
国は違っていても、観終わった後につい遠い目になってしまう人も多いのでは。
中盤から後半にかけては伏線を敷きながらのエピソードがいくつか出て来ますが、火事に関するものが構成的にはクライマックスになっていますネ。
ラストシーンは、大きくなったマイケルが幼い息子を連れて老人ホームのサムに会いに来るエピソード。泣きはしませんでしたが、小津安二郎を思い出しました。改めて家族の話だったんだなぁと。
お勧め度は★四つ半。何年後かにまた観たくなる作品でしょう。
1990年のアカデミー賞で脚本賞、撮影賞(アレン・ダヴィオー)、作曲賞(ランディ・ニューマン)、衣装デザイン賞(Gloria Gresham)にノミネート。
ゴールデン・グローブでも作品賞(ドラマ)、脚本賞、音楽賞(ニューマン)にノミネートされたそうです。
※ ネタバレ備忘録はコチラ。
 脚本も書いたレヴィンソン監督はボルチモアの出身らしいので、多少なりとも自伝的な要素もあるのでしょう。
脚本も書いたレヴィンソン監督はボルチモアの出身らしいので、多少なりとも自伝的な要素もあるのでしょう。時代はテレビが一般家庭に普及していった頃ですから1950年代。撮影当時9歳だったイライジャ・ウッド扮するマイケル坊やがレヴィンソン監督の分身ではないでしょうか。
ヨーロッパからアメリカに移民としてやってきたロシア系ユダヤ人一家のファミリー・ヒストリーであります。
『1914年、私はアメリカに渡った。そこは見たことのないような美しい街だった』
映画はそんなモノローグで始まりますが、語っているのはマイケル君のお祖父ちゃんサム・クリチンスキー(スタール)。フィラデルフィアで船を降り列車でボルチモアに向う。そこでサムを待っていたのは4人の兄弟たち。既に壁紙職人としてボルチモアで生活基盤を築いていた彼らに仕事を教わりながらサムもアメリカ人になっていったのでした。
毎年感謝祭には兄弟達が家族を連れて集まるのが習わしで、その時にサムが小さな孫たちに聞かせてあげる一家の昔話が序盤に語られるのです。
そこはボルチモアのアバロンという地区。2世帯が一つ屋根の下で暮らす幸せな時代のお話です。【原題:AVALON】
楽器演奏が得意だったサム兄弟は、仕事が休みの日には街のダンスホールで揃ってバイオリンを演奏した。サムが後に妻となるエヴァ(プロウライト)と知り合ったのもそのダンスホールだった。やがてサムは自身でもナイトクラブを経営するようになり、息子ジュールズ(クイン)にも楽器を教えてやろうとしたがジュールズは興味を示さなかった。ならばとサムは息子には職人ではなくセールスマンになることを勧めた。
『セールスマンに商品は関係ない。自分を売り込むのさ』
ある日、ジュールズは従兄弟のイジー(ポラック)と一緒にそれぞれの彼女を連れてサムの店にやってきたが、それはジュールズと恋人アン(パーキンス)が結婚した日だった。イジーとジュールズは結婚証明書の姓名の欄に奥さんの名前を書いていた。クリチンスキーよりも聞こえが良い名前にしたというのだ。サムは怒ったが、やがて怒りは子供たちの結婚の喜びに消えていった。
ある年の暮れ、ジュールズはマイケルを連れて車でセールスに出かけたが、暗くなったころ通りで強盗にナイフで刺された。仕事終わりのセールスマンが現金を持っている事を知っていたのだ。車の中で父を待つマイケルの目の前の出来事だった。
病院に搬送されたジュールズは一命をとりとめたが、それを機に訪問販売ではなく店を持つことにした。イジーと共同でディスカウント・デパートを開くことにしたのだ。余計なサービスは省いて調理鍋や洗濯機、電化製品を並べたお店。ディスカウントという言葉さえ珍しい時代だったが、彼らのイニシャルを使った店「K&K」は戦後の好景気の波に乗って瞬く間に繁盛するようになるのだが・・・。
*
何か物語を転がしていく事件が最初に語られるようなドラマではなく、冒頭から昔話が緩やかに始まって、サムの兄弟げんかや嫁と姑の確執なども挟まれて、まるでアメリカ版「渡鬼」のような血縁関係の面倒くささも感じたのですが、徐々にこれはレヴィンソン監督のノスタルジーなんだと思いました。
貧しい時には家族肩寄せ合って暮していたのに、(社会だけでなく個人も)豊かになっていった時代には、逆に家族の絆が脆くなっていった。そんな空気を感じる人もいるでしょうが、僕にはそれらも含めて監督の家族の歴史を懐かしむ想いが作らせた映画のような気がします。
家族皆でテレビの前に集まった時代。
お祖父ちゃんとお祖母ちゃんと孫が一緒に生活していた時代。
国は違っていても、観終わった後につい遠い目になってしまう人も多いのでは。
中盤から後半にかけては伏線を敷きながらのエピソードがいくつか出て来ますが、火事に関するものが構成的にはクライマックスになっていますネ。
ラストシーンは、大きくなったマイケルが幼い息子を連れて老人ホームのサムに会いに来るエピソード。泣きはしませんでしたが、小津安二郎を思い出しました。改めて家族の話だったんだなぁと。
お勧め度は★四つ半。何年後かにまた観たくなる作品でしょう。
1990年のアカデミー賞で脚本賞、撮影賞(アレン・ダヴィオー)、作曲賞(ランディ・ニューマン)、衣装デザイン賞(Gloria Gresham)にノミネート。
ゴールデン・グローブでも作品賞(ドラマ)、脚本賞、音楽賞(ニューマン)にノミネートされたそうです。
※ ネタバレ備忘録はコチラ。
・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし!】 


















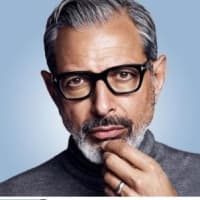



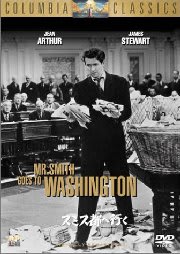



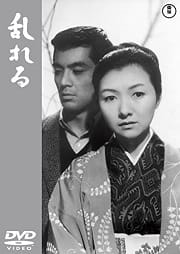







>イライジャ・ウッド扮するマイケル坊やがレヴィンソン監督の分身ではないでしょうか。
レヴィンスンは1942年生まれですので、年代的にもそう言って良いと思います。
登場人物が1930年を25年前と言っているので、一応1955年と計算しましたが、兄弟がTVを売ろうとしたのはもう少し前でしょうね。大体この一族、主人公以外は時代・時間に関して結構いい加減(笑)。
>家族皆でテレビの前に集まった時代。
この辺りは我が邦の「ALWAYS 三丁目の夕日」を思い出させますね。数年の違いがありますが、どちらもTV普及時代。「三丁目の夕日」でヒロインが地方から東京へ出て来るのは一種の移民でしょうか。
>小津安二郎を思い出しました。
内容は違いますが、正に「父ありき」といったところ。
今YouTubeでこの映画のフル・サントラを聞きながら書いています。経済発展が家族の絆を弱めたかもしれませんが(ばくり・・・笑)、良い時代になりましたね。
ここは「爺ありき」でしょうか(笑)
>経済発展が家族の絆を弱めた・・
コロナ禍の中、スマホで再生した絆もあったでしょう。百年前のスペイン風邪の頃はそれこそ大変だったでしょうけど。
因みに、オカピーさんの記事はこちらです。
https://okapi.at.webry.info/202010/article_11.html