(1973/ジェームズ・ブリッジス監督・脚本/ティモシー・ボトムズ、リンゼイ・ワグナー、ジョン・ハウスマン、ジェームズ・ノートン、グレアム・ベッケル、エドワード・ハーマン、クレイグ・リチャード・ネルソン、ロバート・リディアード/112 分)
<ネタバレあり>
 去年の2月にNHK-BSで放送されて録画していたもの。実に35年ぶりの再会です。【原題:THE PAPER CHASE】
去年の2月にNHK-BSで放送されて録画していたもの。実に35年ぶりの再会です。【原題:THE PAPER CHASE】
以前、「アレで思い出した、“リンゼイ・ワグナー”」という記事に、この映画のタイトルは出していましたが、そのリンゼイ・ワグナーの2作目の映画でした。
ハーバード・ロー・スクールの学生達の勤勉ぶりを描いた映画で、とにかく勉強、勉強の日々。主人公はミネソタ出身の男子学生、ジェームズ・ハート(ボトムズ)。彼の経験するロー・スクールでのストイックな学園生活、厳しい授業、そして思いがけない恋。それらを通して成長していくジェームズが描かれます。
この映画でアカデミー助演男優賞を獲ったジョン・ハウスマン扮する契約法担当のキングスフィールド教授の授業が厳しく、ジェームズも初日の授業で予習を忘れて叱責され、終わってからトイレで吐いてしまう。それ程、緊張感のある授業風景が度々出てくる映画です。
ハーバード・ロー・スクールは法科の専門大学院で、入ってくるのは大学を優秀な成績で卒業した学生が多い。監督のジェームズ・ブリッジスは、学生達の生い立ちとか家庭環境についてはなるべく触れず、とにかく学園生活の中の勉学風景を中心に描いています。

ジェームズはフォード(ベッケル)という学生に誘われ彼の勉強会に入ります。個別に勉強するよりも、単位別に担当者を決めて学年末の試験に備えたレポートをまとめ、コピーし合った方が効率がいいだろうということです。その時その時の授業に関しても、予習、復習で意見交換もできる、そういう勉強会を作るわけです。ところが、日々の授業の中で教授の問いかけに答えられず、脱落していく学生も出てくる。勉強会でも、お互いに助け合えるという甘えを持っている学生もいれば、勉強会仲間もライバルの一人だと考えている者もいる。主に描かれる学生は、この勉強会に参加している6人で、彼らの変遷がストーリーの一端を担っています。
ケビンという学生は既婚者で、ジェームズやフォードは学生寮に入っています。フォードは最初から積極的に手を挙げて意見を言うタイプで、ジェームズは当てられたら答えるが、なるべく目立たないようにしているタイプ。ケビンはテキストの事例等を記憶することは得意だが、帰納的な結論を出す事が出来ず段々と自信を無くしていく。ケビンに接するジェームズの態度に彼のあたたかい人間性がほの見えるのですが、ケビンの苦悩がこの学校の厳しさを如実に表しています。彼の妻とのエピソードも痛々しい。
当初は6人だった勉強会も、最後は3人だけになる。自滅する者、仲違いして脱会する者。
学年末の試験前、寮にいては他の学生からの質問責めにあって自分たちの勉強が出来ないと、ジェームズとフォードはホテルに逃げて最後の追い込みに励みます。優秀な成績で卒業できた者には、ニューヨークの弁護士事務所の高給取りの道が待っているのでしょうが、落第すれば元も子もない。入学するのさえ難しい大学院で、必死で頑張る学生達の姿には、今も考えさせられる部分が多いのではないでしょうか。
そんなジェームズにも出逢いはあります。夜、お腹がすいたのでピザ屋に行った帰り、『誰かにつけられてるの』と助けを求めてきた女性です。名前はスーザン(ワグナー)。
その夜は彼女の家まで送っただけですが、美しい彼女が忘れられず、数日後に『近くに来たから』と家を訪ねます。2度目の出逢いでベッドインという展開なのに、情熱的な描写がないのも当時の風潮を想像させますね。むしろ、今よりあっけらかんとしているかも。
実は彼女はキングスフィールド教授の娘で、既婚者だが夫とは別居中という身の上。彼女との関係もジェームズの学園生活に影響を与えていきます。スーザンの夫も教授の教え子だが、どうやら落ちこぼれ。学生時代から落ちこぼれなのか、卒業後に実社会で落ちこぼれたのかは分かりません。作劇上から推測すれば、卒業後に実社会に対応できなかったと考えるのが妥当でしょう。何故なら、スーザンはジェームズの素朴な人間性に惹かれており、教授に振り回されてデートをキャンセルした彼に辛く当たるからです。詳しくいえば、教授に論文の執筆の手伝いを頼まれて、デートの先約があるのを知りながら引き受けてしまうジェームズに教授に取り入ろうとする下心(ジェームズ本人には意識がなかったとも言えるが)が見えたからです。

ある映画サイトの解説では、<そして、全ての競争に勝った青年もまた、勉学だけの青春に虚しさを覚えるのだった……。>と結論づけていましたが、私はラストシーン(成績表の入った封筒を、封も切らずに紙飛行機にして海に飛ばしてしまうジェームズ)をそんな風には考えませんでした。
映画は1年生の終了までが描かれていて、優秀な成績だった主人公には、この後も2年間の学校生活が待っているわけで、彼が虚しさを覚えて退学するようには見えません。教授は学生の名前を覚えない冷たい人間ですが、そんな事に怯まずに、我が道を行く、そんな自信と決意を持てるようになったとの印象を持ちました。
室内や夜のシーンが多い画面は全体に落ち着いたトーンで、人物の内面の緊張感を出す為かミドルショットが多くて、「インテリア (1978)」を思い出しました。
カメラはゴードン・ウィリス。アラン・J・パクラやウディ・アレンとの仕事が多い人で、後で「インテリア」も彼の仕事だと分かって驚きました。「コールガール (1971)」、「大統領の陰謀 (1976)」、「アニー・ホール (1977)」、「マンハッタン (1979)」、「カイロの紫のバラ (1985)」、「推定無罪 (1990)」も彼の作品です。
1973年のアカデミー賞では助演男優賞以外にも、脚色賞、音響賞にノミネートされたそうです。又、ジョン・ハウスマンはゴールデン・グローブでも助演男優賞に輝いたそうです。
何を考えているのか分からない、人間らしい感情を表に出さない大学教授の、学生達を威圧するような存在感はお見事でした。尚、この教授の奥さん(つまり、スーザンの母)は、心の病に罹っているという設定で、登場シーンは有りませんでした。あの教授が旦那さんなら、さもありなん。
<ネタバレあり>
 去年の2月にNHK-BSで放送されて録画していたもの。実に35年ぶりの再会です。【原題:THE PAPER CHASE】
去年の2月にNHK-BSで放送されて録画していたもの。実に35年ぶりの再会です。【原題:THE PAPER CHASE】以前、「アレで思い出した、“リンゼイ・ワグナー”」という記事に、この映画のタイトルは出していましたが、そのリンゼイ・ワグナーの2作目の映画でした。
ハーバード・ロー・スクールの学生達の勤勉ぶりを描いた映画で、とにかく勉強、勉強の日々。主人公はミネソタ出身の男子学生、ジェームズ・ハート(ボトムズ)。彼の経験するロー・スクールでのストイックな学園生活、厳しい授業、そして思いがけない恋。それらを通して成長していくジェームズが描かれます。
この映画でアカデミー助演男優賞を獲ったジョン・ハウスマン扮する契約法担当のキングスフィールド教授の授業が厳しく、ジェームズも初日の授業で予習を忘れて叱責され、終わってからトイレで吐いてしまう。それ程、緊張感のある授業風景が度々出てくる映画です。
ハーバード・ロー・スクールは法科の専門大学院で、入ってくるのは大学を優秀な成績で卒業した学生が多い。監督のジェームズ・ブリッジスは、学生達の生い立ちとか家庭環境についてはなるべく触れず、とにかく学園生活の中の勉学風景を中心に描いています。

ジェームズはフォード(ベッケル)という学生に誘われ彼の勉強会に入ります。個別に勉強するよりも、単位別に担当者を決めて学年末の試験に備えたレポートをまとめ、コピーし合った方が効率がいいだろうということです。その時その時の授業に関しても、予習、復習で意見交換もできる、そういう勉強会を作るわけです。ところが、日々の授業の中で教授の問いかけに答えられず、脱落していく学生も出てくる。勉強会でも、お互いに助け合えるという甘えを持っている学生もいれば、勉強会仲間もライバルの一人だと考えている者もいる。主に描かれる学生は、この勉強会に参加している6人で、彼らの変遷がストーリーの一端を担っています。
ケビンという学生は既婚者で、ジェームズやフォードは学生寮に入っています。フォードは最初から積極的に手を挙げて意見を言うタイプで、ジェームズは当てられたら答えるが、なるべく目立たないようにしているタイプ。ケビンはテキストの事例等を記憶することは得意だが、帰納的な結論を出す事が出来ず段々と自信を無くしていく。ケビンに接するジェームズの態度に彼のあたたかい人間性がほの見えるのですが、ケビンの苦悩がこの学校の厳しさを如実に表しています。彼の妻とのエピソードも痛々しい。
当初は6人だった勉強会も、最後は3人だけになる。自滅する者、仲違いして脱会する者。
学年末の試験前、寮にいては他の学生からの質問責めにあって自分たちの勉強が出来ないと、ジェームズとフォードはホテルに逃げて最後の追い込みに励みます。優秀な成績で卒業できた者には、ニューヨークの弁護士事務所の高給取りの道が待っているのでしょうが、落第すれば元も子もない。入学するのさえ難しい大学院で、必死で頑張る学生達の姿には、今も考えさせられる部分が多いのではないでしょうか。
そんなジェームズにも出逢いはあります。夜、お腹がすいたのでピザ屋に行った帰り、『誰かにつけられてるの』と助けを求めてきた女性です。名前はスーザン(ワグナー)。
その夜は彼女の家まで送っただけですが、美しい彼女が忘れられず、数日後に『近くに来たから』と家を訪ねます。2度目の出逢いでベッドインという展開なのに、情熱的な描写がないのも当時の風潮を想像させますね。むしろ、今よりあっけらかんとしているかも。
実は彼女はキングスフィールド教授の娘で、既婚者だが夫とは別居中という身の上。彼女との関係もジェームズの学園生活に影響を与えていきます。スーザンの夫も教授の教え子だが、どうやら落ちこぼれ。学生時代から落ちこぼれなのか、卒業後に実社会で落ちこぼれたのかは分かりません。作劇上から推測すれば、卒業後に実社会に対応できなかったと考えるのが妥当でしょう。何故なら、スーザンはジェームズの素朴な人間性に惹かれており、教授に振り回されてデートをキャンセルした彼に辛く当たるからです。詳しくいえば、教授に論文の執筆の手伝いを頼まれて、デートの先約があるのを知りながら引き受けてしまうジェームズに教授に取り入ろうとする下心(ジェームズ本人には意識がなかったとも言えるが)が見えたからです。

ある映画サイトの解説では、<そして、全ての競争に勝った青年もまた、勉学だけの青春に虚しさを覚えるのだった……。>と結論づけていましたが、私はラストシーン(成績表の入った封筒を、封も切らずに紙飛行機にして海に飛ばしてしまうジェームズ)をそんな風には考えませんでした。
映画は1年生の終了までが描かれていて、優秀な成績だった主人公には、この後も2年間の学校生活が待っているわけで、彼が虚しさを覚えて退学するようには見えません。教授は学生の名前を覚えない冷たい人間ですが、そんな事に怯まずに、我が道を行く、そんな自信と決意を持てるようになったとの印象を持ちました。
*
室内や夜のシーンが多い画面は全体に落ち着いたトーンで、人物の内面の緊張感を出す為かミドルショットが多くて、「インテリア (1978)」を思い出しました。
カメラはゴードン・ウィリス。アラン・J・パクラやウディ・アレンとの仕事が多い人で、後で「インテリア」も彼の仕事だと分かって驚きました。「コールガール (1971)」、「大統領の陰謀 (1976)」、「アニー・ホール (1977)」、「マンハッタン (1979)」、「カイロの紫のバラ (1985)」、「推定無罪 (1990)」も彼の作品です。
1973年のアカデミー賞では助演男優賞以外にも、脚色賞、音響賞にノミネートされたそうです。又、ジョン・ハウスマンはゴールデン・グローブでも助演男優賞に輝いたそうです。
何を考えているのか分からない、人間らしい感情を表に出さない大学教授の、学生達を威圧するような存在感はお見事でした。尚、この教授の奥さん(つまり、スーザンの母)は、心の病に罹っているという設定で、登場シーンは有りませんでした。あの教授が旦那さんなら、さもありなん。
・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】 


















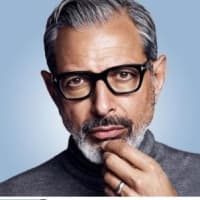




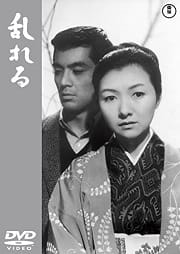

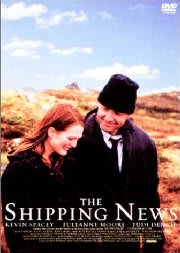
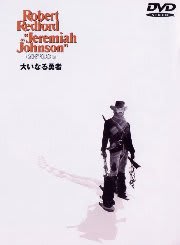







私はこの映画がとても好きですね。近いうちにもう一度観てしまいそう。
>2度目の出逢いでベッドインという展開
えっ、と私もあの速攻の展開にはちょっと驚きましたが、今となってはフリーセックスという時代性が感じられますね。
最後のラストシーンを含めて映画サイトには間違った内容があります。解釈は人それぞれでしょうが、勉学だけの青春の虚しさではないと私も思います。
>この教授の奥さん(つまり、スーザンの母)は、心の病に罹っているという設定で、登場シーンは有りませんでした。あの教授が旦那さんなら、さもありなん
細かいところまでよく覚えてらっしゃいますね。教授の妻は登場しませんが、神経を患っているというスーザンの言葉は気になりました。
好きな映画の記事があったので、コメント無しにTBしてしまいました。
いくつか僕の記事には無い内容もあったので、あぁそんな話もあったなぁと、面白く読ませていただきました。
>ラストシーンを含めて映画サイトには間違った内容があります。
読んでいて首をひねる内容のブログがありますが、そんなのに限ってストーリーにはあまり触れてないんですよね。
ニューシネマの時代ならドロップアウトで終了しそうですが、この頃はもう前向きに捉えるべきでしょうね。
今でも若い人にお薦めしたい映画ですね。