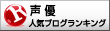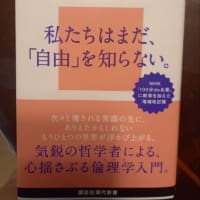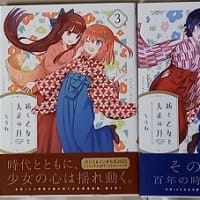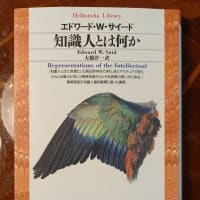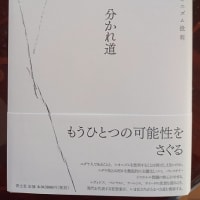難しい書き方がされたこの本のことを難しいまま書くと、読んでいただける方が限られてしまうでしょうし…
いくつかある論点を網羅すると、おそろしく長くなってしまうので、テーマを絞った上で、できるだけ簡潔かつ平易に、読み取ったことを書いてみます。
なので、噛み砕いた内容の中に私自身の誤読が混ざってしまう可能性があること…
論点の選び方に個人のクセや好みが反映されること…
また書かれた内容から派生した私自身の感想と意見がかなり多くなること…
(というか、内容紹介というよりはむしろそっちが主になります)
これらをあらかじめご承知の上で、読んでいただければと思います。
この後に続く各章を取り扱う場合も、同じことを頭に入れてお読みください。間違いが多ければそれは私の不勉強ゆえのことで、バトラー先生のせいではありません。
で、序章です。
ここで一番私の中に響いたのは「自己責任」を個人に強いる社会と、その社会にはびこる価値観、人生観…道徳律と関わるように思われる部分でした。
「自己責任」ということばが私たちの国で、流行語として流布し始めたのはそんなに古いことではなくて、たった20年前、2004年のことだったと言われています。
シリアで取材中だった日本人ジャーナリスト、安田純平さんが「IS」のテロリストたちに誘拐されて、日本政府が身代金を要求され…
「払う必要などない」と主張する人々が使い始めたのが、本格的にこの言葉が世に流布し始めたきっかけだったはずです。
その後世の中の様々なことに広く流用されるようになりました。
21世紀の初めごろ、いわゆる「新自由主義」=ネオリベの経済および政治思想が米国や欧州、そして日本で支配的な立場を獲得したのとほぼ同じころです。
日本ではそれ以前から「他人に迷惑をかけるな」という、庶民の間の教え、すなわち通俗道徳がとても広く共有されていた下地があったからでしょうか…
「自己責任」という言葉は、日本人に非常に好まれて、今にいたるまであらゆるところで顔を出しています。
たとえば貧困に陥った人に、生活保護を受けさせるべきではないと主張する人々が…
(そういう人々は生活保護のことをよく「ナマポ」などと呼んだりします。この言葉を使う人が私は嫌いです)
「その人がそうなるような道を自ら選び、そうなる生き方をして来たのだから、他の人たちの納めた『税金で』助けるのは違うのではないか」
といった主張をするときに「自己責任」という言葉が使われます。
ただこれは日本に限られたものではありません。たとえばバトラーのこの本では、米国の連邦議会議員、ロン・ポールが「ティーパーティー」の集会で言ったことが引用されています。
(ティーパーティーというのは、米国の保守ポピュリズム勢力で、2016年の大統領選挙でトランプ陣営の主な支持集団のひとつとなりました)
ロン・ポールいわく。
「重病を患っていて(私企業の商品である)健康保険に加入していない人々、あるいはその代金を支払わないことを『選んで』いる人々は死ぬしかない」
すなわち、公的健康保険が整備されていない米国で、私企業が販売する高額な医療保険に加入できるだけの収入を得られない人は、死ぬに値する住民であり、彼ら自身に死の責任がある、という主張です。
バトラーは米国の新自由主義者たちの考え方について…
<私たちは各人が自分自身についてのみ責任があり、誰か他者について責任を負うことはない>
という思想だと書いています。
要するに人は自分の面倒を自分で見ていればいいのであって、それ以外のことに責任はないし、興味を持たないのは当たり前だ、ということ。
各人への「経済的な自立への強制」とも言えるかもしれません。
そこには「自立することへの責任」への強い要求があります。
ぶっちゃけていえば「カネに困るようなやつは死ぬ以外に道はないし、死んでいいんだ」という、苛烈な考え方であり…
バトラーの言葉を借りれば<自分自身の市場価値を高めることが生の究極の目的>である世界観です。
こういう考えかたが支配的な社会で人はどうなるでしょうか。バトラーはこのように書いています。
<人は自立することへの「責任」の要求に従えば従うほど、ますます社会的に孤立し、ますます不安定(プレカリアス)だと感じることになる>
そして…
<人を支援する社会構造が「経済的」理由のために崩壊するにつれて、ますます自らの増大した不安と「道徳的失敗」の感覚において孤立を感じるようになる>
貧困へのセーフティーネットが不要なものとされ、なおかつお金が足りなくなることが「道徳的失敗」でさえある社会では、人は不安感から…
個人の「稼ぎ」と「蓄財」だけに専心せざるを得ず、他のことに心を向ける余裕を失います。
電車の中や駅のホームでとなりにいた人が泡を吹いて倒れても目もくれず、助ける行動などせずに仕事場に急ぐ人…
とにかく「貯金」に執着する人…
個人的なもの以外の、社会的な責任や権利-たとえば選挙の際の投票などに全く無関心な人…
どうですか?現代の日本人にそういう人、多くはないでしょうか?
他人に迷惑をかけるな、自己責任で何でもやれ、という社会は、とても不安で孤立した感覚を持った人々を増やします。
それが人々を集団的な、神経症的行動、異常行動、場合によっては残虐な行動へと駆り立てる結果に繋がりがちなこと…
とても脆く壊れやすく、危うい社会を作りがちなことは、容易に想像できるのではないでしょうか。
日本で、米国で、そして最近中国で目立つ「無敵の人」的な犯人による自殺的暴力犯罪や、政治的退廃は、そうした苛烈な自己責任を負わせて人々を締め上げ、窒息させる社会が生み出しているように思うのです。
そうした状況から脱するためには、どうすればいいか。
バトラーはこのように語ります。
<人が送るべき「生は」常に社会的な生であ>ると。
「他人に迷惑をかけるな」ではなく、お互いに「迷惑を掛け合い」すなわち頼り合い、助け合うことこそ、社会というものを作って生きる人間という動物の、本来あるべき姿なのではないでしょうか。
私たちは、親や他の大人たちから教えられてきた通俗道徳を乗り越えない限り、この難しい時代を生き残って行くことはできない気がします。
私たちを袋小路から救う道は、身体を持った一人一人の人間が、孤立するのではなく…
個人が閉じこもっている精神的な場所や物理的な場所から外に出て「集まって」行動すること…
連帯=団結にある、とバトラーは言っていると、私には読めました。
自己責任という、人を個人として孤立させ、最終的に絶望へと追いやる道徳規範を壊すこと。
社会的なインフラストラクチャーや、家族係累ではない人間同士のネットワークを強化すること…
それに「依存」することを、積極的に肯定する方向に、考え方をチェンジして行くことがいま求められているのだと思います。
いいじゃないですか、他人に迷惑をかけること。お互いに迷惑をかけあい、つまり助け合い、ともに生きることのほうが、人間らしいんじゃないでしょうかね。