
地の果てで、やっと君に帰る。
■監督 フェルナンド・メイレレス
■脚本 ジェフリー・ケイン
■原作 ジョン・ル・カレ(「ナイロビの蜂」)
■キャスト レイフ・ファインズ、レイチェル・ワイズ、ダニー・ヒューストン、ピート・ポスルスウェイト、ユベール・クンデ
□オフィシャルサイト 『ナイロビの蜂』
それは、しばしの別れのはずだった。英国外務省一等書記官のジャスティン(レイフ・ファインズ)は、ナイロビの空港からロキへ旅立つ妻テッサ(レイチェル・ワイズ)を見送った。 「行ってくるわ」「じゃ2日後に」それが妻と交わす最後の会話になるとも知らずに…。 ジャスティンに事件を報せたのは、高等弁務官事務所所長で、友人でもあるサンディ(ダニー・ヒューストン)だった。 テッサは車で出かけたトゥルカナ湖の南端で殺された。 彼女は黒人医師アーノルド(ユベール・クンデ)と共に、スラムの医療施設を改善する救援活動に励んでいた。 今回もその一環のはずだったが、同行したアーノルドは行方不明、警察はよくある殺人事件として事件を処理しようとする…。
おススメ度 ⇒★★★ (5★満点、☆は0.5)
cyazの満足度⇒★★★☆
ご存知本作でレイチェル・ワイズが第78回アカデミー賞の助演女優賞を獲得した作品です。 彼女はメジャーになる前から好きな女優さんです。 オスカーをもらってとてもうれしかったですし、またそれゆえに期待していた作品でもありました。
ではこの作品での彼女の演技はどうだったのか? 正直言って特筆すべき点は残念ながらありません(笑) 身重の体はこの作品のストーリーに合っていましたし、体当たりの演技かもしれませんが、謎を秘めたまま逝ってしまいました。
彼女を愛し、彼女のことを信じている、信じたい、信じさせて欲しい。 むしろ彼女の夫であるジャスティンの葛藤と苦悩の日々を描いたところがこの映画の主軸を為していて、それを演じるレイフ・ファインズの彼女に対するひたむきで且つ強い意志を描いている映画だと思った。
そもそもレイフ・ファインズはこの手の色の役が過去の作品にも多いように思う。 ある種男の悲哀と包容力の強さを持ち合わせて、それを相手によって場面場面で使い分ける器用な役者さんなんだと思う。 ただ彼についたこのカラーはこの先も変わらず他の役回りは無理なような気がする。
それにしても、実際に起こりそうな事件(実際に起こっているかもしれないが)をベースにアフリカのおかれた社会的背景や難民問題、この映画に描かれるイギリス政府と製薬会社との癒着等、社会的風刺を含め、少し前に観た『ホテル・ルワンダ』を思い浮かべながら観ていた。
ジャスティンは本当に自分の妻を最後まで信じ通せたのだろうか? それは最後の最後まで心の底では信じていたかったんだろうけど、彼女の正当性を立証したいがために、彼女の足跡を辿るジャスティンの行動は、最愛の妻が女性の武器を盾に、あるいは引き換えにひとつの真実にたいして突き進む姿を、確実な形に捉えていく毎に、彼の苦悩は大きくなる。 そして最後には本当に信頼していた人間までに裏切られていた事実を知り、傷つく。 それでも彼女への愛を信じ、また彼女の真の姿を見つけたとき、その彼女の愛の深さと重みと、そして何よりも勇気とを感じたのかもしれない。
もしも自分が同じような環境と立場に置かれたとしたら、あれほどまでに彼女のことを信じ、勇気を持って行動できたかどうかはわからない。
彼女の流産の原因と、流れても本当にジャスティンの子供だったかどうかは描かれていなかったが、テッサがお乳をあげていた赤ちゃんが黒人だったので最初やっぱり違ったのかと思ったが、隣の子だと知りなんとなくホッといた。 でもあの流産は、彼と彼女の子供だったのだろうか・・・。 少し引っ掛かりが残ってしまった。
テッサが言っていた今できること。 大切なことだと思う。
40キロを歩いて帰る赤ちゃんを抱いた母親と少年をただ見つめるだけしかない。 車に乗せることを望んだテッサの思いを聞き入れず傍らを通りぬけたジャスティン。
そして彼女の死を知り、その40キロの道程を彼女に花を手向ける為に歩いてきて、そしてまたすぐに引き返す少年(名前が思い出せませんが・・・)の姿に涙が溢れそうになった。
ピート・ポスルスウェイトの地味だけど存在感のある演技はいつも心に残る。 かつて『父の祈りを』を観たときの彼の演技には脱帽したものだ。
ジャスティンが自らの手で彼女のもとに旅立つ姿と、アフリカはケニアの大自然の雄々しさと厳しさが、静かな感動として心に残った作品だ。
レイチェルがオスカーに値するのだとしたら、是非レイフ・ファインズにも何かあげたい気持ちになった作品だ。
レイチェルはこの映画の後援にもなっている「WEF国連世界食料計画」に協力し積極的に飢餓撲滅を目指し活動しているそうだ。 映画の中で空から食料を落とすシーンがあったが、あれは実際のWEFの活動を撮影したものだという。 いつの矢面で取り上げられるのはアンジェリーナ・ジョリーだが、レイシェルもそういった面を含めこの映画に全力投球していたのかもしれない。




















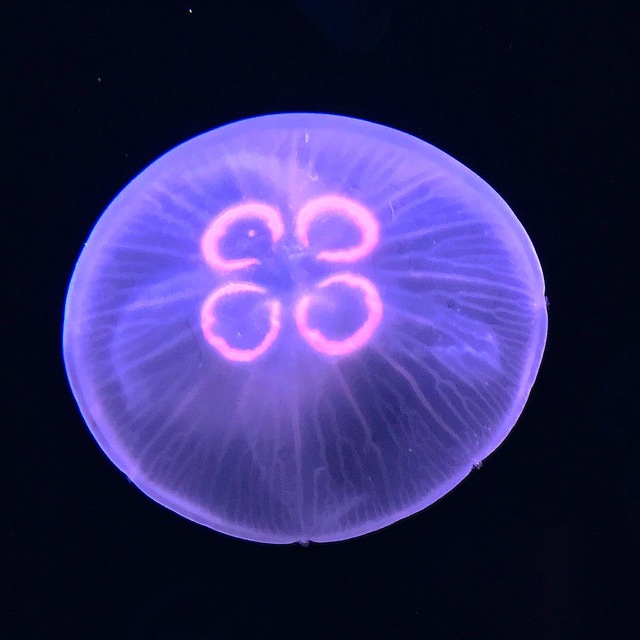





弊ブログへのトラックバック、ありがとうございました。
こちらからもコメント&トラックバックのお返しを失礼致します。
この作品は、社会的のみならずラヴ・サスペンス的な味わいも感じられる事柄を対比させて、様々な要素をバランス良く取り入れた優れた映画であったと思います。
そして、この映画を観てから原作の方が気になって、ジョン・ル・カレ氏の作品を初めて読ませて頂きましたが、映像作品とはまた違った読み応えのある小説でありました。
また遊びに来させて頂きます。
ではまた。
思い浮かべました。
テッサが歩いて帰る家族を助けようとしますけど、
でも彼らにとっては歩くのはあたりまえで、
そのへんってどうなんだろう?ってちょっと
考えさせられました。飛行機に一人乗せようとする
場面は感動的だったんですけど、でも操縦士の
セリフが真実な気もしましたし。。
こういう映画は感想が書きにくいなとも思います。
自分もレイフ・ファインズが良かったじゃないか
派です。
あ~それから ちゃっかりリンクさせて貰っていますo(*^▽^*)oエヘヘ! 事後報告で(*_ _)人ゴメンナサイ
私も 最初観たばっかりの時は、テッサに腹が立ち(押しかけ結婚でジャスティンの幸せを壊しておきながら 回想シーンのあのくったくのない笑顔は ないだろう~~みたいな^^)
そっちに気をとられていましたが 公式ページで、音楽を聴きながら レビューを書いてるうちに 映画を思い出し 悲しくなりました。
深い愛に・・・包まれていたのかな?
いえジャスティンが テッサを(皮肉な話ですが 死後)深く愛したのでしょうね・・・^^
確かにレイフ・ファインズもいい演技でしたよね
・セカイの貧困とそれに群がる悪のこと
そして
・一番近い存在について、実はそれほど理解が進んでいないこと
の2つです。遠いものと近いものどちらも判っているようで解らない存在かもしれません。この映画をみて、その様に感じました。TBありがとうございます。
あの流産はジャスティンとの子供ですよ~。
信じてあげてくださいな!
映画を見終わってからテッサはいつからジャスティンのことを愛していたのか、そして二人の愛の温度差や理解度の深さについて考えています。
映画を見ている間はサスペンス性に惹かれていましたが、観た後は彼らの愛の形を考えさせられました。
どうしてもフィクションとして見れなかったですね。
色んな意味でとても考えさせられる作品でした。
それにしても、レイチェルの妊婦姿は驚きましたね。違和感無かったですね^^;
TBさせて頂きます。
>この作品は、社会的のみならずラヴ・サスペンス的な味わいも感じられる事柄を対比させて、様々な要素をバランス良く取り入れた優れた映画であったと思います。
そうでしたね! ややハンディで捉える二人の表情が固定していない分、もったいなかったように感じました。
>ジョン・ル・カレ氏の作品を初めて読ませて頂きましたが、映像作品とはまた違った読み応えのある小説でありました。
僕も興味あるんですが良かったようですね!時間があれば読んでみたいと思います。
>自分も「ホテルルワンダ」をやっぱり思い浮かべました。
ですよね~^^
>テッサが歩いて帰る家族を助けようとしますけど、でも彼らにとっては歩くのはあたりまえで、そのへんってどうなんだろう?ってちょっと考えさせられました。飛行機に一人乗せようとする場面は感動的だったんですけど、でも操縦士のセリフが真実な気もしましたし。。
歩いて帰る少年はラスト近くの彼女の花をたむけるシーンの伏線と考えました。あそこは山が欲しいところですからねぇ^^
>こういう映画は感想が書きにくいなとも思います。自分もレイフ・ファインズが良かったじゃないか派です。
彼の演技は今までのキャリアで十分オスカーに値すると思います!
私もジャスティンの立場だったら彼のような行動は絶対できないです。
普通はそんなに信じきれないですからね。信じきったそんな所に二人の愛の強さがあったのかな。
cyazさんもレイチェル・ワイズよりもレイフ・ファインズ派でしたか!
私も彼女の演技はずば抜けてよかったと思えませんでした。オスカー獲ったからどんなもんかと勝手に期待してたからかもですが・・・
私はかなり前に、ブロガー対象のスニーク試写会で観たのですが、結構好きな作品です。
夫婦愛の物語をうたっていますが、私はアフリカのこどもたちの澄んだ悲しい瞳に心を惹かれました。