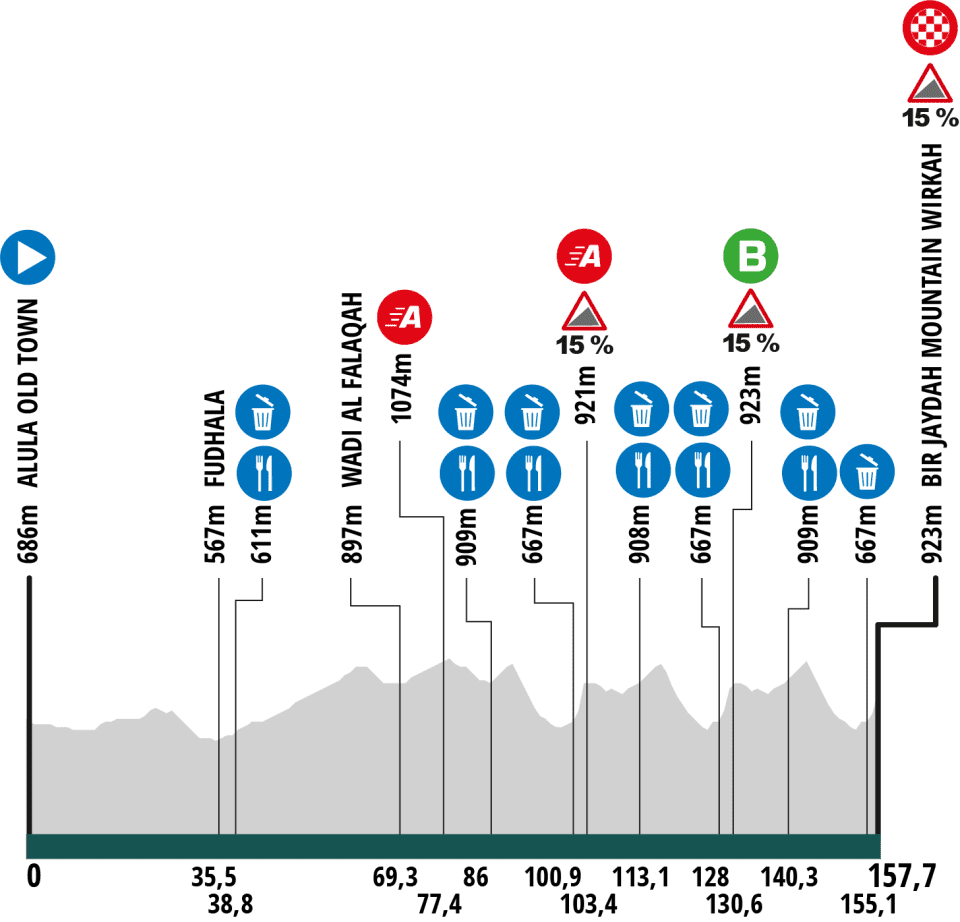昨年、ポガチャルと共にトリプルクラウンを達成したコルナゴのV4RsがV5Rsへと進化します。ここまで、ポガチャルがイベントでカモフラージュ柄のバイクに乗っていたり、ヴォルタ・カタルーニャで試験的に使用されていたという噂があったV5Rsですが、ついにそのベールを脱ぐことになりました。

未塗装のフレーム重量が685gという軽量でありながら、エアロ効果を落としていないというのがコルナゴの謳い文句のようです。ぱっと見では確かに少しスリムになった印象はありますが、エアロ効果が期待できるようには見えません。

V4Rsに比べ12.5%もの軽量化は評価に値するデータです。ポガチャルの山岳での強力な武器になることは間違いないでしょう。これはカーボンレイアップを刷新し、V4Rs と同等の剛性、堅牢性を維持しながら、カーボン使用量を減らし軽量化を達成したというのです。

コルナゴは「コルナゴ史上最軽量」を謳っていますが、初代のSupersix EVOはサイズ56の塗装済みで695gだったことやスペシャライズドのAETHOSのフレーム重量が585gだったことを考えると、驚くほどの数値ではありません。初代のSupersix EVOは軽すぎてUCI規定の6.8㎏を切ってしまうことになり、重りをシートポスト内に入れていたほどなのです。

ただ、Supersix EVOもディスクブレーキ化やエアロ化が進む中でフレーム重量が増えつつあるのも事実です。コルナゴのV5Rsは「登りで優位差を得て、下りでその優位性をさらに決定的なものにする」と謳っています。これはエアロ効果を高めたという意味ではなく、新たに開発されたフォークとヘッドセットが軽量化に貢献するだけでなく、最もテクニカルな下り坂で必要なコントロール性と瞬発的な反応性を高めているという意味のようです。

シートポストの形状やヘッドセット内部の構造が変わっているようですが、ぱっと見ではほとんど分かりません。全体的にはV4Rsがややスリムになっただけといった感じに見えてしまいます。V5RsはVRシリーズの進化系なので熟成度が高まっていることは間違いないでしょう。ただ、エアロ化が進んでいる時代にコルナゴが軽量バイクを敢えて出してくる意味が良く分からないのです。

コルナゴは昨年秋に最新エアロバイクのY1Rsを発表し注目を集めましたが、今シーズンでY1Rsの勝利はUAEツアーのポガチャルの2勝だけという結果に終わっているのです。ポガチャルのミラノ~サンレモ用に開発されたと思われるバイクが、登りでポガチャルの脚を削ったばかりか、チーム内から剛性が高すぎて乗り心地が悪いという悪評が漏れてきているのです。おそらくCANYONのAEROAD CFRも最初はそんな感じだったのだと思います。