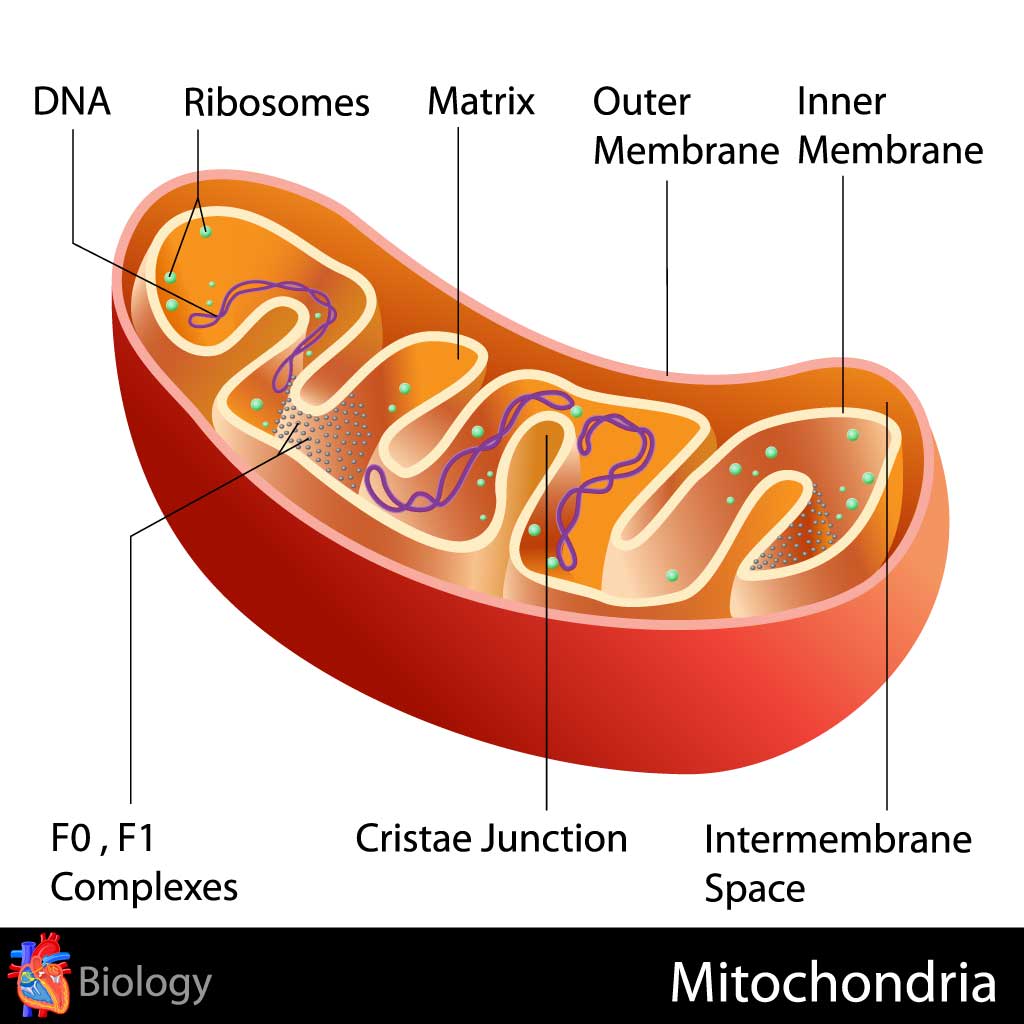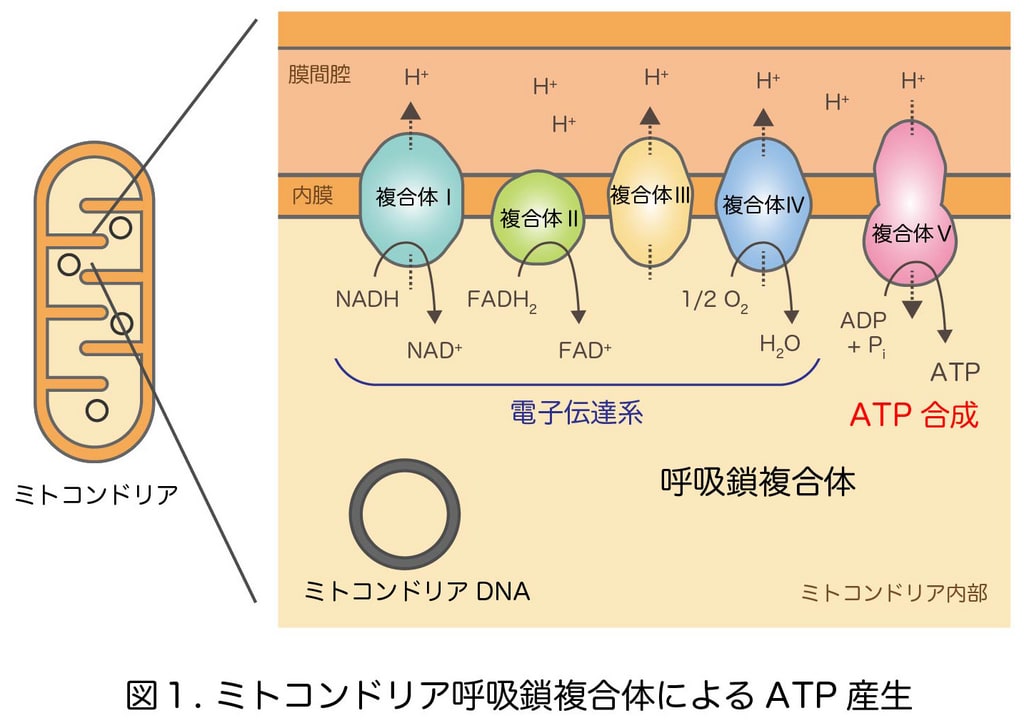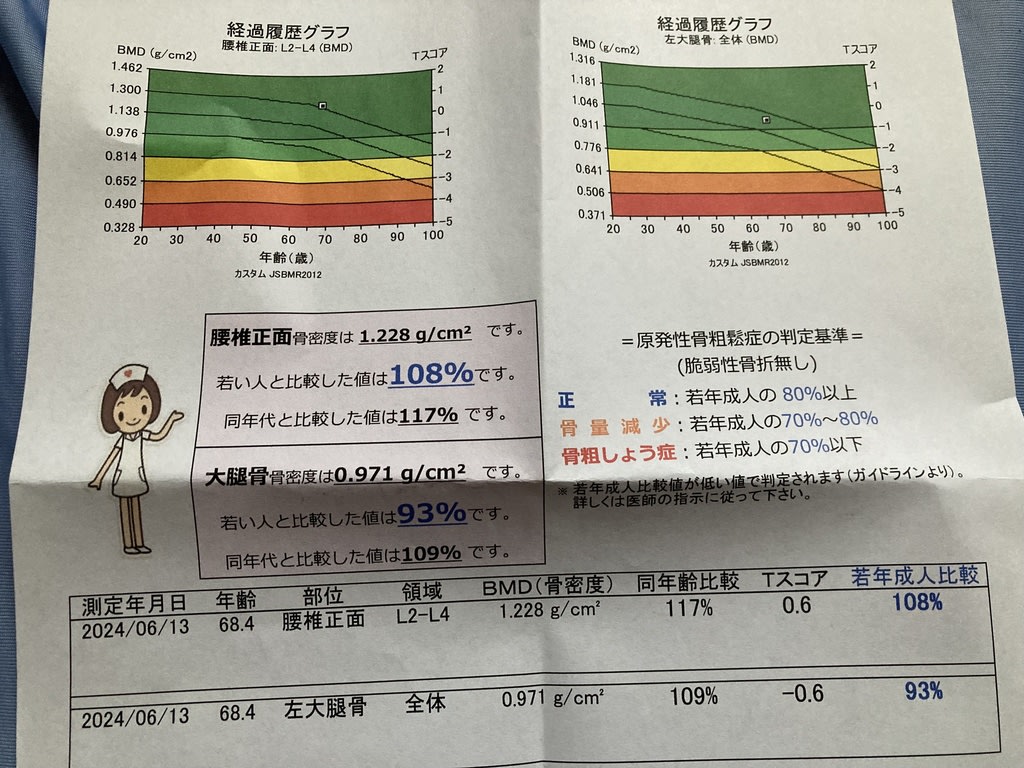冬場に足を骨折し、気が重い春を迎えることになりました。昨年秋にこの春を楽しみにエアロロードバイクの第4世代のSupersix EVOを購入していたからです。救急搬送から手術、退院してからも装具が外れる迄は自転車に乗る事もできず、気の滅入る時期が長く続きました。
その間はJ-Sportsでサイクルロードレースを観ながら、何とかモチベーションを保っていたのが実情でした。GWには何とかフラットペダルで近場の公園へお花見ライドが出来るまでになりましたが、ロードバイクで本格的に走ることが出来たのは6月に入ってからのことです。

春先のサイクルロードレースを観ていて、第4世代のSupersix EVOにエアロフレアハンドルを装着しました。これが想像以上に快適で、内向きのブラケットを握り込んだり、ブラケットの上部に掌を置いたりすることで、TTバイクのDHポジションに近いフォームになり、ギアが2枚ほど掛けられるようになったのです。

ディープリムホイールにエアロフレアハンドルの組み合わせでの走りでは、向かい風の中で心拍数が160bpmを越える走りが出来てしまい、ガス欠になるという経験も味わいました。足のリハビリは続いていた頃のことですから、驚きでした。久々の快適な走りでアドレナリンが出ていたのかもしれませんが、骨折のリハビリ中の走りではありませんでした。
そもそも第4世代のSupersix EVOは速く走ることを目的に購入したものではありません。同じスピードを低い出力で走るためだったのですが、スピードが出てしまうと、それが快感になり、アドレナリンが出てさらにギアを掛けてしまうのが人の性なのだと思い知らされたのです。
自動車でも高速で走ると同じ事が起きていたことを思い出しました。スピード違反が無くならないのは、この全能感のせいではないかと思っています。アドレナリンはスポーツなどではプラスに働くことが多いのですが、誤った全能感に陥ってしまうリスクもあるのだと、今は自戒しています。
それ以来、敢えてディープリムホイールは封印しています。骨折の治療は終わっていますが、骨折部位にボルトとプレートが入ったままで、来年の冬にはこのプレートを抜く手術が待ってるのです。本格的に走ることが出来るのは来年の夏頃になるのかもしれません。それまでは、敢えて抑える走りをするつもりでいます。

昨日はようやくそのペースがつかめたような気がしています。北海道は一機に季節が進み、寒さや雨の影響で、なかなか距離を走ることが出来ずにいましたが、昨日は風も弱く日差しもあったので、最高気温は21度でしたが、石狩灯台迄走って来ました。7月半ば以来のことになります。同じホイールで同じ幅のタイヤですから、バイクの装備は全く同じでも、今回の方が速度が速く出力が少ない走りとなっています。

確かにリアが17Tで走る時間が長くなっていたことは間違いありません。且つてはリア17Tでケイデンス75rpmは尤も効率的な走りでしたが、年々リア17Tで走り続けることが辛くなり、リア19Tを多用するようになっていたのですが、第4世代のSupersix EVOにエアロフレアハンドルを装着してからは、リア15Tでの走りも苦にならなくなっているのです。
ただ、流石にリア15Tだと、速度域は30km/hを越えているので、心拍数は150bpmを越えてしまい、私にとっては長く走れる心拍ゾーンでは無いのです。何とか140bpm代で維持させることを意識して走っていました。結果、少ない出力でスピードアップが可能になったようです。

少ない出力で速く走るためには、スピードのアップダウンを出来るだけ減らし、一定のペースを刻むことだと改めて認識することができました。ギアを掛けたいという気持ちを抑え、ペースを刻むのはなかなか難しいのですが、敢えてそうすることのメリットは脚の疲労が少ないことでしょう。また、走りにも余裕が出来、季節の風や風景を味わうことができたのもメリットのひとつでした。昨日の空と雲はまるで夏のものでした。ただ、日が陰ると一機に寒さを感じたので、季節は進んでいるんだなと思います。