遅い更新ですいません。
当面、ブログ更新は午後11時以降になると思います。
よろしくお含み置き下さい。
本日は、証券アナリスト協会主催講演会「企業再編の会計処理」に出席しました。
新日本監査法人の中島康晴先生による、120ページを越す膨大な資料を使っての
講義でしたが、豊富な事例紹介と滑らかな語り口であっという間の2時間。
不勉強な私もかなり収穫がありました。
今日のネタは、まずはその中から、私が興味深く思ったものをご紹介。
-------------------------------------------------------------------------
■イトーヨーカ堂グル-プの再編事例より
・ヨーカ堂グループはご存知のように昨年9月に持株会社化しております
(セブン&アイホールディングス)。
細かい説明は省きますが、興味深かったことは、
再編の前と後で、連結当期純利益のH18/2期の予想値が大幅に
上昇していたことです。
具体的に見てみましょう。
①H17年4月7日に公表したH18/2期 連結業績予想
(イトーヨーカ堂の連結短信の1ページ目の一番下をご覧下さい)
http://www.7andi.com/ir/pdf/fresult/05_iy_con.pdf
連結営業利益 2,330億円
連結経常利益 2,300億円
連結当期純利益 637億円
(この時点ではまだ持株会社構想の開示なし)
②H17年8月22日に公表した新しい業績予想
http://www.itoyokado.co.jp/company/investors/release/pdf/20050822j.pdf
連結営業利益 2,330億円
連結経常利益 2,300億円
連結当期純利益1,147億円
①と②を比較してお分かりのように、
何故か当期純利益だけ510億円も増えている。
グループ内再編で株式交換による100%子会社化で
ありながら、再編前後で利益が増えるっていうのはおかしい。
では、何故こうなったのか?
カンの鋭い人であれば、
「そりゃ、収益の柱であるセブン・イレブンの少数株主損益がなくなったから
ではないのか?」とお考えのはず。
答えは、その通り。
しかし、何故、少数株主損益がなくなったかといえば、
セブンの少数株主に対して株式交換によって、膨大なセブン&アイ株式を
発行しているからです。
ただ気をつけなくてはならないことは、
この企業統合がいわゆる「プーリング法」っていうのを用いているため、
簿価ベースでの統合。
よって、パーチェス法でおなじみの「のれん」が生じない。
のれんが生じないということは、のれん償却費(販売管理費)も生じない
っていうことです。
以上をまとめますと、セブン&アイは、
①株式交換によってセブンの少数株主を排除
→連結損益計算書上、利益の控除項目である「少数株主損益」が大幅に減少
②プーリング法での統合ゆえ、のれんは発生せず、当然のれん償却費も発生しない、
という、いいとこ取りの会計処理をしていた、ということです。
もちろん、当時の会計基準では許容されたものなのでどうこういうつもりは
無いのですが、新しい企業結合会計基準では原則パーチェス法が適用される
(プーリング法は極めて限定的な場面でしか適用できない)
「もう二度とできない処理」なのです。
セブンはその最後のチャンスを生かした、ってワケですね。
ただ釈然としないのは、
パーチェス法であれば本来計上されるはずの資産サイドの「のれん」が
ごっそり無いわけですから、相手方勘定では何かがそれと同額だけ減額されて
いる、ってことになります。
・・・・・・・・ということは、株式交換のために発行された新株の発行価額を抑えた
可能性があります。ということは、株式交換に応じたセブンなどの少数株主に、
のれん相当額の損失がチャージされていった、ということになるのでしょうか。
うーん、奥が深い。
------------------------------------------------------------------------
で、「のれん」といえば、例の阪神と阪急の統合。
新会計基準に従い、阪神株取得により膨大なのれんが発生する可能性は高いと思われます。
で、こののれんの中には、村上ファンドによる同社株の売却益も含まれている、
ってことになります。
つまり、阪急の貸借対照表に、村上ファンドの「置き土産」がズシっと乗ってくるワケですね。
つまるところ、企業統合を通じて、誰かがトクをし、誰かが損をしている、
ということなのでしょうか。
当面、ブログ更新は午後11時以降になると思います。
よろしくお含み置き下さい。
本日は、証券アナリスト協会主催講演会「企業再編の会計処理」に出席しました。
新日本監査法人の中島康晴先生による、120ページを越す膨大な資料を使っての
講義でしたが、豊富な事例紹介と滑らかな語り口であっという間の2時間。
不勉強な私もかなり収穫がありました。
今日のネタは、まずはその中から、私が興味深く思ったものをご紹介。
-------------------------------------------------------------------------
■イトーヨーカ堂グル-プの再編事例より
・ヨーカ堂グループはご存知のように昨年9月に持株会社化しております
(セブン&アイホールディングス)。
細かい説明は省きますが、興味深かったことは、
再編の前と後で、連結当期純利益のH18/2期の予想値が大幅に
上昇していたことです。
具体的に見てみましょう。
①H17年4月7日に公表したH18/2期 連結業績予想
(イトーヨーカ堂の連結短信の1ページ目の一番下をご覧下さい)
http://www.7andi.com/ir/pdf/fresult/05_iy_con.pdf
連結営業利益 2,330億円
連結経常利益 2,300億円
連結当期純利益 637億円
(この時点ではまだ持株会社構想の開示なし)
②H17年8月22日に公表した新しい業績予想
http://www.itoyokado.co.jp/company/investors/release/pdf/20050822j.pdf
連結営業利益 2,330億円
連結経常利益 2,300億円
連結当期純利益1,147億円
①と②を比較してお分かりのように、
何故か当期純利益だけ510億円も増えている。
グループ内再編で株式交換による100%子会社化で
ありながら、再編前後で利益が増えるっていうのはおかしい。
では、何故こうなったのか?
カンの鋭い人であれば、
「そりゃ、収益の柱であるセブン・イレブンの少数株主損益がなくなったから
ではないのか?」とお考えのはず。
答えは、その通り。
しかし、何故、少数株主損益がなくなったかといえば、
セブンの少数株主に対して株式交換によって、膨大なセブン&アイ株式を
発行しているからです。
ただ気をつけなくてはならないことは、
この企業統合がいわゆる「プーリング法」っていうのを用いているため、
簿価ベースでの統合。
よって、パーチェス法でおなじみの「のれん」が生じない。
のれんが生じないということは、のれん償却費(販売管理費)も生じない
っていうことです。
以上をまとめますと、セブン&アイは、
①株式交換によってセブンの少数株主を排除
→連結損益計算書上、利益の控除項目である「少数株主損益」が大幅に減少
②プーリング法での統合ゆえ、のれんは発生せず、当然のれん償却費も発生しない、
という、いいとこ取りの会計処理をしていた、ということです。
もちろん、当時の会計基準では許容されたものなのでどうこういうつもりは
無いのですが、新しい企業結合会計基準では原則パーチェス法が適用される
(プーリング法は極めて限定的な場面でしか適用できない)
「もう二度とできない処理」なのです。
セブンはその最後のチャンスを生かした、ってワケですね。
ただ釈然としないのは、
パーチェス法であれば本来計上されるはずの資産サイドの「のれん」が
ごっそり無いわけですから、相手方勘定では何かがそれと同額だけ減額されて
いる、ってことになります。
・・・・・・・・ということは、株式交換のために発行された新株の発行価額を抑えた
可能性があります。ということは、株式交換に応じたセブンなどの少数株主に、
のれん相当額の損失がチャージされていった、ということになるのでしょうか。
うーん、奥が深い。
------------------------------------------------------------------------
で、「のれん」といえば、例の阪神と阪急の統合。
新会計基準に従い、阪神株取得により膨大なのれんが発生する可能性は高いと思われます。
で、こののれんの中には、村上ファンドによる同社株の売却益も含まれている、
ってことになります。
つまり、阪急の貸借対照表に、村上ファンドの「置き土産」がズシっと乗ってくるワケですね。
つまるところ、企業統合を通じて、誰かがトクをし、誰かが損をしている、
ということなのでしょうか。













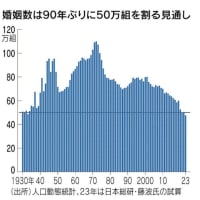
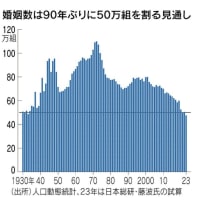
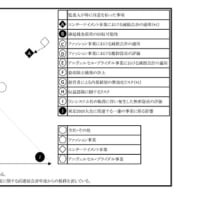
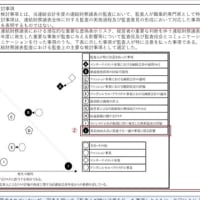
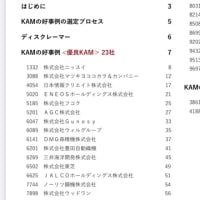

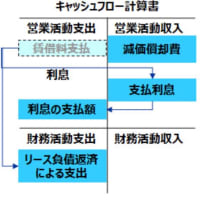







②のところ「パーチェス法での統合ゆえ、のれんは発生せず」となっています。プーリング法ですよね。
あとは解釈の問題なんでしょうけど、パーチェス法が強制適用というと(確かに新会計基準では今回の条件ではパーチェス法しか適用不可ですが)プーリング法が全く適用されないという印象を受けますが・・・。一応一定要件に該当すれば適用可能かと思うので。
僭越ながら以上コメントさせていただきました。
すこし気になったのでコメント失礼します。
>セブン&アイは、
>
>①株式交換によってセブンの少数株主を排除
> →連結損益計算書上、利益の控除項目である「少数株主損益」が大幅に減少
>
>②パーチェス法での統合ゆえ、のれんは発生せず、当然のれん償却費も発生しない、
>
>という、いいとこ取りの会計処理をしていた、ということです。
とありますが
少々語弊があるような・・・
一見、少数株主持分の利益まで奪ったように聞こえてしまいます。
正確には、いままで他人だったセブンイレブンの少数株主は株式交換によってグループ支配株主の一部になったわけです。
ですから、大きくなった利益を旧支配株主が独占しているのではなく、旧支配株主と新支配株主の両者で持っているのですから、ああゆうP/Lになっても致しかたがないことです。
不勉強なんで間違ってるかもしれませんが・・・
のれんを計上した場合、相手勘定は確か資本剰余金ですよね。それを将来の期間に渡って償却していく訳ですが、それは利益剰余金の減少になるのでしょうが、結局、株主資本はチャラになるのではないでしょうか?
もちろん、その期間中は持分プーリング方式と株主資本に差が生じますが、それは会計処理の違いとして分かります。
ですが、のれんを計上しなかったことについて、それはすべて少数株主に負担させてしまったというような表現には正直「?」です。
少数株主が本当に不当な損失を押し付けられたかどうかは、結局のところ株式交換の交換比率が不当だったかどうかに尽きるのではないでしょうか?
私見ですが、適正な株式交換比率が算定されているのであれば、そこでセブンイレブンの「のれん=超過収益力」は織り込まれているので、結果として割り当て株式を、のれんを評価しない場合よりも多くもらうことで、きちんとした価値分の株式は交付されていると思われます。
もちろん、株式交換比率は様々な要素が考慮されますので、のれん分だけを抽出して語ることはできませんが・・・
いずれにしても、中身の企業集団が変わっていないのに、連結財務諸表の数値が変わるのは利用者にとって混乱を招く話というのは激しく同意します。
ある意味、株式交換というのはよーく考えないと理解困難な状況に陥りやすいと思われます。
こういう比較可能性の阻害は非常に重要な話と思われますが、現行の開示制度ではなんの手当てもなされていません。
営業外損益の内訳科目が10%を超えたから別掲しました・・・的な表示方法の変更を載せるよりも、遥かに重要な問題だと思いますが。w
ちなみに昨夜の予想利益が監査対象かどうかについての書き込みも私です(名無しで失礼しました)。
これからもブログ頑張ってください。
まずはワールドカップさま
ご指摘有難うございました。
仰るとおりです。
時間が無く焦って更新してしまい
十分なチェックができていませんでした。
直ちに修正させて頂きました。
そして348GTBさま
ご指摘有難うございます。
「大きくなった利益を旧支配株主が独占しているのではなく、旧支配株主と新支配株主の両者で持っている」
とのご指摘に関しては、私も同感です。
統合後はいいのです。
(また間違っている可能性がありますが)
私の意見は
「統合時に割を食ったのではないか。」
もっと言えば、少数株主への
割当株数が少なかったのではないか?
ということなんですね。
いずれにせよ時間が無い中で
言葉足らず・検証不足の面は否めず
反省しております。
取り急ぎご回答まで。