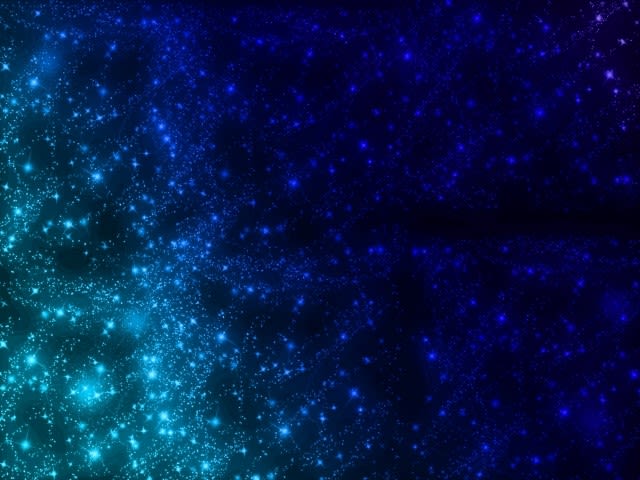気がつくと青い道を歩いていて、道の向こうにぼんやりと青い灯りが見えていた。
潮の香り。
ここは海の近く?
たしかわたしはさっきまで車を運転していて、海へ向かう道路を走っていた、はず。
そう、海のそばの駐車場に車を止めたのだ。
それで潮の香りのする道を、今歩いているのだ。
こういうこと、わたしにはよくあることで。
「こういうこと」というのは、頭が少しぼんやりして、記憶がかすれたり、さっきのことが昔のことに思えたり、逆に昔のことがさっきのことみたいに思えたり、そういうの、よくあることで。
ほんとはこんな、ひどくぼんやりな頭で車の運転とかしてはいけないのかもしれないが、車の運転をしているときは、ただ流れに沿って動く機械みたいにハンドル回してアクセル踏んでいればいいし、だからあんまり考えなくていいから。それは今のわたしにとってラクなことだから。
後ろを振り返ってみると、わたしがここまで乗ってきた車が見えた。
青い道の上の砂浜の駐車場。
駐車場に数本街灯が光っている。
灯りの色は青。
だから道も駐車場も青く照らされているのだ。
あそこの駐車場に停めたんだ。
あの青い街灯が目印。
覚えておかなくてはかえれないから、頭に入れておこう。
よく道に迷う。
知っている道だって、よく行く町だって迷う。
歩いているときはもちろん、車、運転してるときも、道がわからなくなることがしばしばある。
うんと回り道して目的の場所にうまくたどり着くこともあるけれど、たいてい、どの道を走っても、どの角を曲がっても、どの交差点を横切っても、ここがどこなのか、わからないことのほうが多い。
方向音痴? 人からはそう言われる。
そうかな。自分では違うと思う。
ただ道を覚える気がないだけなのだ。
道を覚えないのは仕事上いろいろと不都合で、それで前の会社は解雇になった。
車でスーパーマーケットを回って営業する仕事だったから。
遅刻ばかりして会社の上司や相手先に謝ってばかりだった。
向かなかったのだ。
向かなかった?
あれもこれも―結婚したことも子供を育てることも仕事も「あの男」と付き合ったことも―そう、向かなかったんだよ、うん、向かなかった。向かなかった、という切り方。
それは自分への哀れみでありなぐさめであり体のいい言い訳であり。
「あの男」のことを思いながら道を歩いた。
あの男の顔……うまく思い出せない。
ほんの一時、共に過ごした男。
付き合ったのは、いつからいつまでだったっけ……
きのう別れたばかりなのか、三年前のことなのか、わたしの頭の中は、時空の順序がいつだって不規則にジグザグしているのだ。
わたしの子供って、いったい何才になったのかな。
あの子はいつだって別れたときのままの、三才で止まってる。
あの子とわたしの、これからすごすであろう密のような時空を奪ったのは、わたし自身だ。
あの子の父親とわたしはよく言い争いをした。
彼はわたしに軽蔑の言葉を残し、子を連れて家を出ていった。
お前はちゃんとした子育ても日常生活もできない、親として妻として失格者だ、と言い残し。
わたしはきっと家の中でも道に迷っていたのだ。
いったいどっちへ歩いていいのかわからないのに、道を進むハンドルを握りたがる。
あの男に、わたしは失格者らしいの、と伝えると、
僕も失格者だよ、だって職も女も趣味も長く続いたためしがないし、と「同士である」ことを教えてくれた。
左利きだったあの男、中学と高校時代、ハンドボールの選手だったそうだ。
飛び上がってゴールする瞬間だよ、すごいだろ、僕の頂点の頃だ、と言って、写真を何枚か見せてくれた。
わたし、その写真ほとんど覚えてない。
あの男が写真でどんな飛び上がり方をしてたのか、そのときの表情とか、着ていたユニフォームだとか、なんにも、なんにも思い出せない。
残念だし申し訳ないけれど。
彼は会うたびにわたしの手首を、自分の左手でぎゅっと握って、ふわっと離してくれた。
まるでボールを握り、そのボールをシュートするみたいに、ぎゅっとふわっと。
その男の左手のことは、いつでもそこにあるみたいに簡単に思い出すことができる。
あ、
道の向こうにまた青い灯り。
駐車場の灯りとは違う。もっと深い青。
あれは……お店の灯りなのだろうか。
喫茶店?
人通りの少ないこんなところに?
建物の形が変わっている。
船の形をしている。
壁のペンキはあちこちはがれていて、藻のような青い蔦がからみついていた。
まるで海に沈み、朽ち始めた船みたいだ。
店の看板がうっすらと青い灯りに照らされていた。
「Amalia」―アマリア、と読むのだろうか。
店の中から、ギターの音が聴こえてきた。
聴いたことのない曲。
なのに懐かしい。
店の扉の前に立ったまま、しばらく耳を澄ませた。
心地良い音が、入ってくる。
心の奥に眠っている深い海に、すうっと潜り、すべて包み込んでくれるような、そんな旋律。
しばらく聴いていると、中から扉が開いた。
「どうぞ、遠慮はいりません、お入りください」
この店のマスターなのだろう。
どこか異国の血が混じった風貌の中年の男の人。
わたしが外でぼんやり立っているのに気づき、扉を開けてくれたのだ。
招かれるまま、中に入った。
数人の客がいた。
小さな円形の木製の台(ステージ)の上で、男の人がギターを弾いていた。
空いている席に座ると、マスターが
「当店には珈琲しかございませんがよろしいでしょうか」
と言うと、わたしの返事を待たず、演奏のじゃまにならないように気遣ってか、静かにカウンターの向こうに消えた。
「これは『難破船』という曲ですよ」
隣に座っていた銀髪の女の人が、わたしに小声で耳打ちしてくれた。
男の人が今演奏している曲の題名を教えてくれたのだ。
ギターを弾いている男の人の腕が目に入る。
弦を押さえる左の手。
そして指。
記憶が滝のようにいちどきに流れ、わたしは思わず顔をおおった。
あの男に似ていたのだ。
長い指の形がとても。
腕の動かし方がとても。
わたしたちは何度か抱き合い、そして別れた。
もう連絡はしないと言ったのはわたしからだ。
だってわたしはあの男を殺してしまうかもしれないから。
あの男の左手も左手以外もすべて、わたしはわたしのものにしたくて、よく飲んでいる風邪薬だかビタミン剤だかの錠剤のように、わたしの中に、のみ込んでしまうかもしれないから。
それはつまり、あの男を殺すことでしょう。
失格者の愛し方は、愛しいものの時や空間や命さえも奪ってしまうのだと、三才のあの子と別れた時に、そう思った。
あの男も失格者なのだとしたら、わたしたちは殺し合うってことになるでしょう。だから。
最後にあの男に会ったのは、海の見える海岸通りの喫茶店。
あのとき流れていた曲、何だったろう。
この曲を聴いていると、不思議だ。あのときこの曲が流れていたような気がしてくる。
三才のあの子と別れたとき、どこかから聞えてきた曲も、もしかしてこの曲だったのかもしれない。
わたしの記憶は塗り替えられすり替えられているのか、そしてわたしはまたどこにいるのかわからなくなる。
珈琲が運ばれてきた。
あ、そうだった。薬の時間だ。薬を飲まなければ。
風邪薬。風邪気味で熱っぽいから。
一錠、二錠、水と熱い珈琲で、からだの中心に流す。
もしかしてあの男にもギターを弾いてよと頼めば弾いてくれただろうか。
あの男の奏でる旋律は、わたしのかすれた記憶の一部になっただろうか。
わたしはあの男と別れてから、どうしていたのだろう。
どうやって暮らしていたのだろう。
そもそもわたしの暮らしなぞ、現実味のないいい加減なものなのかもしれない。
押し寄せる波のような旋律の上で思う。
それはあの男の記憶の中の左手と同じだ。
三才のあの子の持つどこにもない柔らかなからだも、まるであの男の左手といっしょだ。
いつでも、どこにいても、わたしを逃さない。
曖昧なわたしのからだに流れ落ちる記憶に溶けていく。
「珈琲のおかわりはいかがですか」
マスターの声にうなずく。
二杯目を飲んだら帰ろう。
でもわたしはたぶん、店を出るとまた帰り道がわからなくなっているのだろう。
どこに車を置いたのだっけ。
どこの道を歩いてきたのだっけ。
道は青く、駐車場の街灯も青かったのだということだけしか覚えていない。
薬は飲んだのだっけ、それともまた別の薬を飲む時間がきたのだっけ。
ギタリストの指はたおやかに踊り、わたしのからだの記憶をなぞっていく。
『難破船』fin.