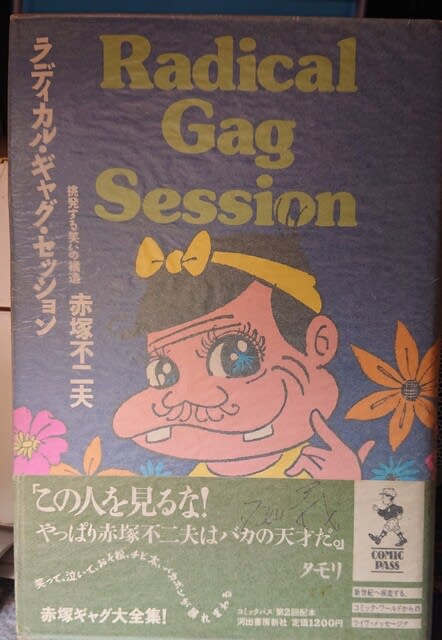
『バカボン』に纏わるトピックで、最も特筆に値するのは、今尚伝説として語り継がれている実験的エピソードの数々だ。
『バカボン』の週刊連載での合計期間は、途中休載分を差し引いても、八年以上の長きに渡り、ギャグ漫画の限界が、週刊ペースで概ね二年強だとしても、そのエピソード数は通常の約四倍にも相当する。
その為、読者を飽きさせないよう、数々のギャグのシンカーを投げ続け、連載ペースをキープせざるを得ない、切実な事情が背景にあり、常識を破るフォーマットが幾つも生み出されるに至ったのだろう。
*
霧に閉ざされた夜の摩天楼を背景に、トレンチコートに身を包み、コルトを構えた劇画調のバカボンのパパが颯爽と登場する見事な一枚絵の扉ページと、本編中繰り返される稚拙な劇画タッチとのコントラストが、多大なインパクトを与える「天才バカボンの劇画なのだ」(72年9号)は、佐藤まさあき(代表作/『堕靡泥の星』、『若い貴族たち』)の劣化コピーといった趣のハードボイルド・パロディーだが、陰影を加え、微妙な立体感を湛えたキャラクターデザインや、映画的手法を駆使したローアングルや局部アップ等の表現技法を、作画崩壊ギリギリのタッチで再現することで、漫画とも劇画とも付かない、珍妙奇天烈なダークファンタジーをここに視覚化した。
ストーリーは、暴力団の縄張り抗争に巻き込まれたバカボンのパパが、目ん玉つながりと共闘し、街の平和のため、双方のヒットマン相手に大捕物を繰り広げるという勧善懲悪ものでありながらも、途中、通常の二頭身から四頭身、再び二頭身へと、パパが変幻自在に姿を変える、メタモルフォーゼを全面に押し立てた展開や、日本古来の遊び歌である「ずいずいずっころばし」を最後まで歌わなければ、弾が発射されないクラリネット型の改造拳銃など、アホらしさ全開のガジェットを用いたギャグを効果的に取り込んでおり、転んでもただでは起きない赤塚独特の洒脱な逸脱をここでも視認することが出来る。
その後、コマからコマへの連続の中で、グロテスクな形象を意匠とする、登場人物達の喜怒哀楽の表情を大ゴマで描出した一枚絵のような劇画的カットが、赤塚ギャグの独壇場として見せゴマの如く頻出するが、このような新たな表現様式もまた、この劇画版『バカボン』の執筆が一つの契機となって生まれたものであることは言うまでもない。
*
新たな少女漫画の類型提示を隠れ蓑に、自身のオネエ趣味を笑いのディテールへと転化した「天才おバカボン」(72年13号)は、かつて少女漫画の王道パターンであったバレエ物をコミカルにパロディー化したホモセクシャル・ナンセンス。
この作品は、薔薇の花をたっぷり描き入れることで、その心象を更に具象化せしめたキメ細やかな背景に、センチメンタルなモノローグの使用、そして、長い睫毛にキャッチライトが無数に当てられたパパやバカボンの瞳といった、少女漫画特有の装飾性を心憎いまでにフォローした怪作だ。
物語の要点として、春山うらら先生ことオカマのカオルちゃんが主宰するバレー教室で、パパとバカボンが女学生宜しく、トップバレリーナを目指し、日夜奮闘を重ねるといった一つの対決軸が展開されるものの、そこは流石の『バカボン』ワールドで、パパが「黒田節」のメロディに合わせて、トウシューズを尖らせるなど、その脱力的なギャグに関しても枚挙に暇がない。
(赤塚も、駆け出し時代に、一人の薄幸の少女が悲痛に満ちた現実を乗り越え、バレリーナとして成長を遂げてゆく『ブローチとバレエ靴』(「少女ブック 新年増刊号」58年1月10日発行)なる読み切りを執筆したことがあった。)
「天才おバカボン」では、少女漫画の完全コピーを意識してか、ファンシーテイスト溢れるバカボンのパパも登場し、読む人の度肝を抜く。
鼻毛を抜いて作った付け睫毛や、「マーガレット」を飾ると、「なかよし」の「フレンド」がいっぱい出来てしまうという「りぼん」型の鉢巻きが印象的なグーなおバカボンのパパのファッションは、1960年代より、少女雑誌のお洒落ページのイラストや、サンリオ、サンスター等で、多数のキャラクターメイクを受け持ち、後にエッセイストとしても活躍する田村セツコの手によって描かれたものである。
彼女は、新人時代より、赤塚と公私ともに親しい間柄にあり、そうした交流の深さがこのような異色のコラボレートを生んだのだろう。
田村セツコとのコラボは極めてレアなケースだが、絵の面白さを追求したエクスペリメンタルなギャグをこの時多数生むことになったのも、第四章にて詳しく記述したフジオ・プロ劇画部のバックアップがあったからこそだと言えよう。
「天才バカボンの劇画なのだ」以降、前述したように、心持ち悪さを意図した、登場人物らの顔面クローズアップが半ページ大の大ゴマで多用されるようになるが、これを開発し、最初に執筆したのが、木村知生である。
その木村がアシスタントを努めていたフジオ・プロ劇画部のリーダー・芳谷圭児にも、等身大の美男美女を劇中登場させたい際、作画協力を要請するなど、この時、赤塚が求めるイメージは、常にスタッフの誰かによって、具体化出来る環境にあったという。
*
これらの他にも、『巨人の星』、『天才バカボン』とのトライアングルで、「少年マガジン」の第一次全盛期を牽引した『あしたのジョー』が、今尚語り草として名高い、衝撃の最終回を迎えたその翌週に、「あたしのジョー」(73年22号)なるタイトルで、バカボンが矢吹丈に、パパが丹下段平に扮し、草ボクシングに奮戦するというパロディー漫画を、友人である高森(梶原一騎)、ちば両氏への労いと賛辞を込め、執筆したこともあった。
但し、作中、ちばタッチに合わせた、等身大のジョーや段平が登場するわけではなく、バカボン扮するジョーが、ウナギイヌやノラウマとボクシング対決をしたり、ロードワークのつもりが、脱線して野原をサイクリングしたりと、微笑誘発型の尾籠の笑いを、定例通りのドタバタに絡めた稚気満々のオリジナルエピソードとして描かれており、やはり同じパロディーでも、対象作品のキャラクターの模写や、世界観の引用に比重を置いた長谷邦夫作品との笑いにおける温度差は歴然としている。










