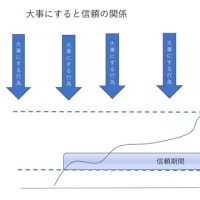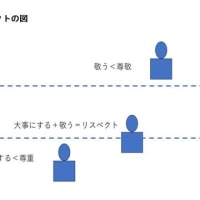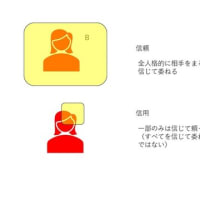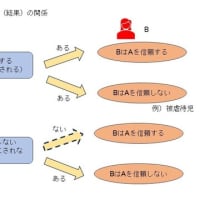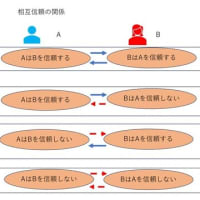4月に来日するアダム・カヘン氏の著書「手ごわい問題は対話で解決する」を読んでいるのですが、ここでもいろいろと教育で使えそうなことが早速出ていました。
今の教育で問題だと思うのは、唯一の正解ある問題への偏重です。もちろん、考える基礎トレーニングとして答えがはっきりしているものは扱いやすい。しかし、現実の社会では答えが唯一でない問題がほとんど。よって、学校教育が終わってそこに放り込まれた人々は対応できないというものです。また、討論番組などを見ていてわかるとおり、自分の主張はこうであると決めたらそれを絶対に曲げない。自分が常に真の答えをつかんでいるなどということはありえないのに・・・
そこで、アパルトヘイトを解決に導いたファシリテーターとして有名なアダム・カヘン氏のアプローチとはいったい何だったのか。そこに興味があるわけです。
アパルトヘイト問題の解決には、シェル石油で培ったシナリオプラニングという手法が使われるのですが、実際に南アフリカのモン・フルーという場所で行われたワークショップにおいて、カヘン氏は次のようなアプローチをとります。
****ここから引用 p32
ワークショップはまず、バックグラウンドが異なる人同士で小グループ(ミックス・グループ)をつくり、今後10年間に南アフリカで起こり得るシナリオをブレーンストーミングすることから始まりました。私はシェルの慣習に沿って、普段彼らが未来について語るときのように、「未来に起こって欲しいと思っていること」を語るのではなく、望むかどうかにかかわらず、単純に「何が起こり得るか」について話すようにお願いしました。
・・・・聞き手は「そんなことは起こり得ない」とか「そんなことは起こってもらいたくない」といった反論をすることは許されず、「どうしてそれが起こる必要があるのですか」とか「その次は何が起こりそうですか」という質問だけが許されました。
*****ここまで引用
注目すべき1番目は、普通のディベートの方式では、同じ考えを持つ同士でグループを組ませ、集団対集団の構造にリードしてしまいがちです。しかし、ここではあえてミックスグループを作らせている。
そして2番目は、小グループ内で対立構造を生まない、うまい問いかけをしているということです。「何が起こり得るのか?」という問いは、物事の構造やそこに働いている有形無形の力のかかり方などを想像しないと考えられないわけです。
こうしたグルーピングや問いを1つとってみても、問題解決に向けての戦略(ストラテジー)として非常に参考になるものがあると感じました。
今の教育で問題だと思うのは、唯一の正解ある問題への偏重です。もちろん、考える基礎トレーニングとして答えがはっきりしているものは扱いやすい。しかし、現実の社会では答えが唯一でない問題がほとんど。よって、学校教育が終わってそこに放り込まれた人々は対応できないというものです。また、討論番組などを見ていてわかるとおり、自分の主張はこうであると決めたらそれを絶対に曲げない。自分が常に真の答えをつかんでいるなどということはありえないのに・・・
そこで、アパルトヘイトを解決に導いたファシリテーターとして有名なアダム・カヘン氏のアプローチとはいったい何だったのか。そこに興味があるわけです。
アパルトヘイト問題の解決には、シェル石油で培ったシナリオプラニングという手法が使われるのですが、実際に南アフリカのモン・フルーという場所で行われたワークショップにおいて、カヘン氏は次のようなアプローチをとります。
****ここから引用 p32
ワークショップはまず、バックグラウンドが異なる人同士で小グループ(ミックス・グループ)をつくり、今後10年間に南アフリカで起こり得るシナリオをブレーンストーミングすることから始まりました。私はシェルの慣習に沿って、普段彼らが未来について語るときのように、「未来に起こって欲しいと思っていること」を語るのではなく、望むかどうかにかかわらず、単純に「何が起こり得るか」について話すようにお願いしました。
・・・・聞き手は「そんなことは起こり得ない」とか「そんなことは起こってもらいたくない」といった反論をすることは許されず、「どうしてそれが起こる必要があるのですか」とか「その次は何が起こりそうですか」という質問だけが許されました。
*****ここまで引用
注目すべき1番目は、普通のディベートの方式では、同じ考えを持つ同士でグループを組ませ、集団対集団の構造にリードしてしまいがちです。しかし、ここではあえてミックスグループを作らせている。
そして2番目は、小グループ内で対立構造を生まない、うまい問いかけをしているということです。「何が起こり得るのか?」という問いは、物事の構造やそこに働いている有形無形の力のかかり方などを想像しないと考えられないわけです。
こうしたグルーピングや問いを1つとってみても、問題解決に向けての戦略(ストラテジー)として非常に参考になるものがあると感じました。