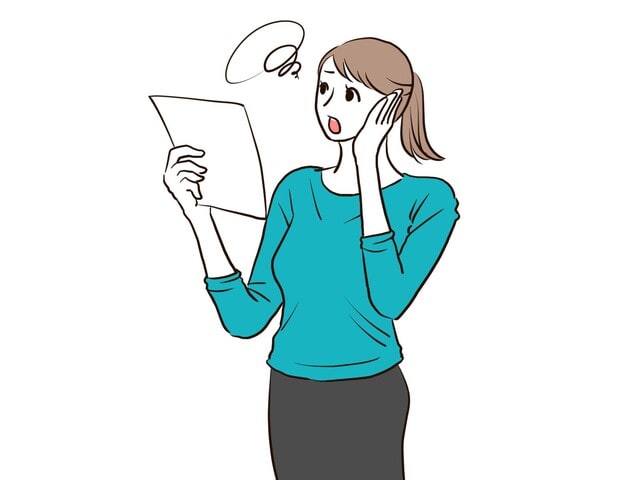
2016年から電力の小売自由化で、電力会社が自由に選べるようになりました。
これまでは東京電力など、大手電力会社が電力市場を独占していたのですね。
私たちは住んでいる地域の大手電力会社と契約を行っていたわけです。
格安電気会社は、基本料金がゼロだったり、ポイントが貯まったり、とても魅力的
当然、新しい電力会社は、大手の既存の電力会社より安い料金や、
お得なメリットがなければ誰も契約をしてくれませんね。
たとえば、お勤めの人なら、昼間の電気料金を高くして、
その代わりに夜間の電気料金を安くするなどの料金プランがあります。
ところが、大きな誤算が生じました
①在宅勤務による昼間の電気代の消費が増えた
②電力不足で電気代が高騰した
2020年末から2021年1月にかけて続いている大寒波の影響で
発電所が発電できる量の限界近くまで達してしまったそう。
モノの値段は、売り手が多いのか、買い手が多きのかで決まります。
買う人が多ければ、値段が上がり、
売る人が多ければ、値段は下がります。
需要と供給の関係ですね。
そのため、売り手の発電所から電気の買い手である各電力会社に卸す電気の価格が高騰してしまったのです。
その結果、私たちの電気代も高くなることに
もっとも、各電力会社のプランには、大きく分けて2つのプランがあります。
①市場連動型の電気料金プラン
②それ以外の電気料金プラン
①のプランを選んでいる人は、世の中の電気代の卸価格によって、
支払う電気代が上がったり下がったりします。
これまで、市場連動型プランは、電気の卸価格によって価格が増減するため、
電気代がお得になりやすいと説明されてきました。
ところが、電気代が前月に比べて2倍、3倍になってしまった人も珍しくありません
寒波が続けば、さらに高騰する可能性も。

日本卸電力取引所(JEPX)の電力取引価格推移(出典はテラエナジーのWebサイト)
電気市場高騰による電気料金への影響について
そこで政府は、電力の卸売価格高騰で「新電力」事業者を支援へ することにしました。
これは卸売りの価格を安定させて、私たちへの影響を抑えるのがねらいです。
私の感想ですが、これは住宅ローンの変動金利と固定金利と同じ意味ですね
変動金利は目先の返済額が安いけど、金利が上がったら返済額も上がる。
電気卸価格が上がったら、電気代が上がる
どちらがよいか悩ましいのですが、私は固定金利派です。
リスクが嫌なのですね
反対に、投資はリスクがないと儲けることもできません。
投資、資産運用の大リスクは好きですが
電気代や住宅ローンでリスクは取りたくないなと思っています。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます