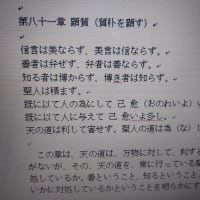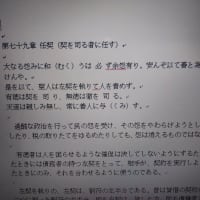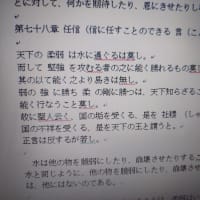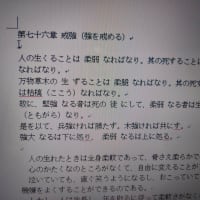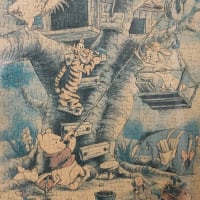第四十二章 道化(道徳による徳化)
道は一を 生 じ、一は二を 生 じ、二は三を 生 じ、三は万物を 生 ず。
万物は陰を負いて陽を抱き、沖気は以て和を為す。
人の悪(にく)む 所 は唯孤寡、不轂(ふこく)なり。而るを王公は以て 称 と為す。
故に物は、或いは之を損じて而して益す。或いは之を益して而して損ず。
人の教うる 所 、我も亦人に教う。強 梁 (きょうりょう)の者は其の死を得
ずと。
吾将た以て教えを為す 父 (はじめ)とす。
道から陰と陽を生じ、陰と陽との他に、中性のもの、すなわち、冲気を生じたことを指す。とあるは、万物には、陰性と陽性の部分が備わっているが、その他に、中性の部分が備わっているので、全体の調和がとられていることをいうのである。
孤寡は、孤児と、老いて夫のないやもめのことであり、不轂(ふこく)は、不善のこと、徳のないことであって、どちらも人の嫌がるものである。しかるに、王公が自分の称呼としているのは、これは、高い地位にある王公と、民衆の地位が余り違いすぎるので、その調和をはかる考えから生じたことである。
益をしようとして、欲張ったことをしたり、その地位を利用して民衆を威圧するようなことをすると、一応は益をすることがあっても、信用を失ったり、民心が離反するようなことになって、結果においては損をすることになるのである。
孔子は、門人の子路が、剛強な態度を見せることがたびたびあるので、子路は、終りを全うすることはできないのではないか、と言っていたのであるが、子路は、後に、衛国の乱に死んだのである。
譲、ということをしないで、あくまでも力ずくで押し通そうとすると、必ずこれをさえぎり、或は倒そうとする強敵が現れて闘争しなければならぬこととなるものであるから、生命を全うすることは難しいこととなるのである。