3.安倍氏起つ
さて,摂関家とは別系で,不遇を託っていた藤原登任が齢60余にして陸奥守となり,着任するところから今回は始まる。
当時の奥州,それも奥六郡と呼ばれた現在の岩手県中部から北部にかけては,奥州一の大河日高見(北上)川沿いに,俘囚の長である安倍氏が忠頼-忠良-頼良と三代続く間に勢力を扶植していた。
特に頼良の代になると,柵と呼ばれる城柵を領内に何カ所も築いて,一族をそれぞれ配していた。
例えば,嫡男の貞任は厨川柵(盛岡市北部)を領していたので,厨川次郎(長子は夭折したのだろう)と呼ばれたし,次弟の宗任は鳥海柵(盛岡市西部)で生まれたか育ったようで鳥海三郎(居たのは胆沢城),さらにその弟の正任は黒沢尻柵(北上市西部)を領して黒沢尻五郎とそれぞれ呼ばれた。
胆沢城は,前項でも述べたとおり,陸奥鎮守府が置かれた地である。
つまり中央政府の出先機関であるはずなのだが,ここに安倍頼良が自分の子を配したということは,既に鎮守府の役割を果たしていないことがうかがえよう。
世はまさに道長-頼通と続く摂関家の全盛期であり,それに連なる貴族たちは遙任として,中央にて地方から上がってくる利益を搾取した。
地方行政が疎かになるのは当然で,族長たる安倍氏が奥六郡の実権を握ったのも何の不思議ではないといえる。
実力で奥六郡を従えた安倍氏にとって,中央政府(或いは多賀城の官人たち)何する者ぞ,といった気概は当然あっただろうし,奥州にとって中央政府こそ侵略者にして簒奪者に他ならなかった訳である。
安倍氏が朝貢を拒否したのは至極当然,と蝦夷の子孫たる私は思う・・・。
さて,そんなところへやってきたのが登任である。
中央官界では頭打ち故,陸奥守になったのを幸いと,地方の民から搾取して「外貨稼ぎ」を目論んで,老躯を押して奥州までやってきたのだろう。
当然,安倍頼良が賦貢遙役を拒否することなど許せるはずもない。
度々の訓告を当然無視したであろう頼良に対し,陸奥守の権勢をかさに登任は兵を起こす。
多分,兵馬の経験はなかったからだろうが,出羽に援軍を要請し,秋田城介重成とともに数千の兵で安倍氏討滅を計った。
時に永承6年(1051)3月。
世に言う「前九年の役」の始まりである。
九年とはいうものの,足かけ12年にわたる奥州兵乱は,この陸奥守藤原登任+秋田城介重成と安倍頼良一族の激突が端緒となった。
これを鬼切部の戦いという。
鬼切部の場所は,現在の宮城県玉造郡鳴子町鬼首-去年から大崎市鳴子町-というのが定説だが,随分と安倍氏の本拠地たる奥六郡より離れているように思われる。
安倍氏の前哨基地が衣川柵(岩手県奥州市衣川区)と考えると,相当な行軍距離となる。
そうなると,磐井郡鬼切沢(一関市西部)がその地では??という説も頷ける気がするが,こちらは磐井川の渓流に沢が合流する場所で,軍勢がぶつかるには狭隘な気もする。
また,現在の鬼首には「軍沢」なる地名も残り,こちらもあなかち誤りとは言えまい・・・。
いずれにしても,官軍と安倍軍は奥州鬼切部で激突した。
奥州の山間部の3月であるから,積雪を蹴散らしての合戦だったろう。
結果は,安倍氏の圧勝。
慌てたのは,登任は勿論中央政界であろう。
安倍氏反乱!!
100年前の承平・天慶の乱を思った者がどれほど居たか分からないが,官軍が散々に負けたのだから衝撃は大きかったと思われる。
慌てて追討軍の大将の人選にかかったが,公家に適任など居るはずもない。
そこで白羽の矢が立ったのが,源頼義である。
源氏の長ならば,武門として間違いなし,という評価があっただろう。
遂に頼義は,念願の奥州経営の契機を得た。
前九年の役は源氏vs安倍氏となり,いよいよ歴史が動き出す・・・。
現在の鬼首
(続く・・・)










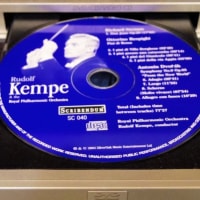
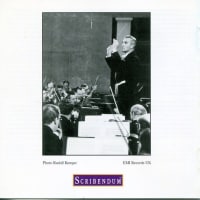
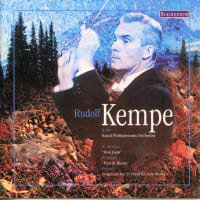







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます