いよいよエントリする。
古代史,しかも地域のものとなると,今まで全くの関心外で,何の知識もない。
果たして,どのような内容と分量になるか想像もつかないが,無謀を承知でエントリを敢行する。
ちらりとで結構なので,読んでいただけると幸甚である・・・。
1.序章
東北地方を「みちのく」と呼ぶ。
何とも旅情を感じさせる響を持った言葉であるが,道の奥が変化しただけである。
道-即ち陸の奥。
陸奥国の語源は,そんなところにあったと言える。
で,畿内や九州から見れば,それこそ陸の奥であり,荒ぶる東夷(あづまえびす)の住む東国のさらに北は未開の地であり,それこそ毛むくじゃらな食人族のような野蛮人が棲息していると思われたであろうことは,想像に難くない。
誤解を覚悟で言うが,西国に対して東国や東北は後から開けた後進の地,と思われがちである。
ただ,それは飽くまでも中央政府による支配が遅かったというだけの話であり,だから文化的に後進地域,と断ずるのは短絡的にすぎると思う。
例えば,東北に縄文遺跡は数多く存在するが,残された遺構からも優れた意匠の跡がうかがえる。
そして,何よりも本州最北端部に位置する後期縄文時代の三内丸山遺跡の発掘により,縄文-狩猟・採集,弥生-農耕という単純な図式が成り立たなくなったくらいである。
中央政府が,東北を支配した最初の例は,多分大和朝廷時代の国造(くにのみやつこ)ではないだろうか。
以前,会津国造が高度な文明を有していたのではないか,という雑文を書いたことがあったが(こちら参照),古代の東北は,会津と越の国(越後)から支配が浸透していったと思われる。
道奥国-陸奥国の成立は,多分律令制初期と思われるが,全部で三十五郡もある大国で,陸奥守に任命された国司は,上の位階の貴族が多かったとされる。
東北経営の最初の入り口は,高校の日本史の教科書にもある大化の改新直後に設けられた越後の淳足(ぬたり:沼垂),磐舟両柵である。
そして,阿倍比羅夫の水軍による北航が続く。
時に斉明天皇4(658)年。
比羅夫は渡島(北海道南端)まで行ったという記録があるが,おそらく白村江の海戦を想定した軍事演習だったとの見方もある。
秋田(土崎?)に能代,そして十三湊はこの時期から開けたと思われる。
奈良に遷都された8世紀になると,律令政府による東北政策はさらに活性化する。
越後の沼垂・磐舟両柵を足がかりとしたため,まず出羽が開けた。
和銅2(709)年には出羽柵,3年後には置賜柵と最上郡が設置された。
それに比べると太平洋岸(宮城・福島)は少し遅く,養老~神亀年間(720年代)に石城(岩城=磐城)郡,石背(いわしろ-岩代)国,刈田郡,そして多賀城が設置された。
多賀城に政庁が置かれた時代は長く,陸奥の中心だったわけだが,その前は同国郡山(現在の仙台市南東部)に政庁があった。
秋田城が設置されたのもこの時期と思われる。
陸奥守とともに秋田城介(あきたじょうのすけ)も権威有る職階となり,8世紀後半には,岩手県中部にまで中央政府の支配は及ぶことになった。
この時期,朝鮮半島に拠る渤海の使者が出羽国に度々来航している。
9世紀で著名なのは,何と言っても坂上田村麻呂であろう。
桓武帝の命によって蝦夷を征伐し,初の征夷大将軍となったことは,小学生の頃教わった記憶がある(今は教科書から削除されているようだ)。
阿倍比羅夫の時代から150年後のことである。
この間に征討将軍として,多くの者が陸奥の土を踏んだ。
例えば,藤原不比等の子で,後に天然痘で相次いで没した宇合(うまかい)と麻呂の兄弟も,8世紀前半に征討将軍となっているし,歌人として有名な大伴家持も同様である。
田村麻呂は胆沢城を築き,そこに鎮守府を置いた。
それまで15年にわたって征討軍を悩ませた阿弖流爲(あてるい)は田村麻呂の薦めによって投降したが,中央貴族たちの反対によって阿弖流爲は畿内で斬られる。
それによって,奥州の民を帰順させようとした田村麻呂の政策は実らず,さらに奥の雫石川畔に紫波城を築くことになる。
以来,奥州の民は中央政府に対して一層不信感を募らせる結果となる。
そして,元慶年間や承平年間には出羽で反乱が起きる。
中央の官吏たちは彼等を俘囚と呼んで蔑んだ。
蝦夷という語も,野蛮人という意味である。
蘇我入鹿の父の名は蝦夷(えみし)となっているが,律令政府が後に付けたであろうことは容易に想像される。
因みに九州では,隼人や熊襲と呼ばれるのも同義であろう・・・。
古代の東北の歴史は,中央政府との軋轢の歴史とも言える。
平和な生活を送っていた彼等にとって,中央から派遣される役人は簒奪者でしかなかった。
だから征夷大将軍などという語も,我々にとっては差別以外の何者でも無いのである。
蝦夷が反乱を起こしたので,政府は征討将軍を送って鎮圧したと言えば,格好良いかもしれないが,先日のチベット蜂起同様,歴史とはそんな一面的なものではないのである・・・。 紫波城跡
紫波城跡
(続く・・・)










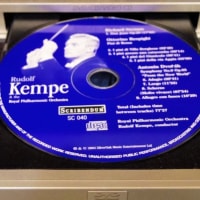
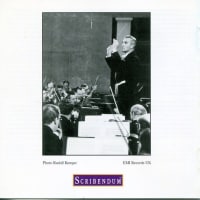
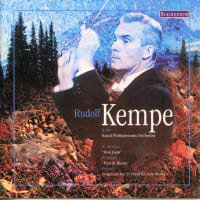







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます