「足利尊氏=逆賊」は明治政府の陰謀だった…最新研究でわかった室町幕府初代将軍のこれまでとは真逆の評価
ー醍醐天皇との対立、日本中を揺るがした兄弟げんかの真相
:::::
香原 斗志(かはら・とし)
歴史評論家、音楽評論家
神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。
歴史評論家、音楽評論家
神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。
日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。
著書に『お城の値打ち』(新潮新書)、 『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。
:::::
:::::
室町幕府を開いた足利尊氏とはどんな人物だったのか。
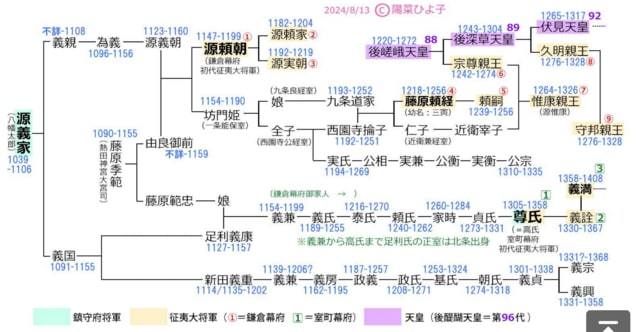
(注1)樺崎八幡宮 :鑁阿寺の開基足利義兼が身内の菩提のために創建した樺崎寺跡(国史跡)のなかにあります。3代目義氏がお堂を建て、八幡を勧請して義兼を合祀したことが八幡宮のはじまりと言われています。 電話番号
0284-41-3504
0284-41-3504
(注2)・・・『下野神社沿革誌』によれば『樺崎八幡宮』は西暦838年に
長一族の租・長六郎平爲により建立された『赤土神社』に、西暦1056年、源義家が八幡神を勧請・合祀し八幡宮とし、更に西暦1199年に生入定された義家の曾孫、足利義兼の御霊をも合祀したとされます。
『樺崎八幡宮』の宮司は歴代長一族の者がその任に当たったと記録されています。・・・
:::::
歴史評論家の香原斗志さんは「戦前の日本では天皇に弓を引いた逆賊として扱われていた。
しかし、近年の研究を見るとその評価は間違っていたことがわかった」という――。
■日本史上において最も毀誉褒貶が激しい人物
史上最悪の逆賊なのか、はたまた稀代の英雄なのか。日本史上における著名な政治家または武将で、足利尊氏ほど毀誉褒貶が激しく、時代によって評価が異なった人物は、ほかにいないだろう。
このうち戦前の評価は「逆賊」に一本化されていた。
その流れをつくったのは、天皇を中心とする秩序を重んじ、後醍醐天皇が開いた南朝を正統と唱える水戸学だった。
よく知られているように、幕末の政治運動の支柱となった尊王攘夷論は、水戸学の中核をなす考え方だった。
尊王攘夷論が目に見えるかたちで足利尊氏に向けられたのは、
尊王攘夷論が目に見えるかたちで足利尊氏に向けられたのは、
俗にいう「足利三代木像梟首きょうしゅ事件」だった。
これは文久3年(1863)2月22日深夜、京都の等持院霊光殿に安置されていた足利尊氏、義詮、義満、すなわち室町幕府の初代から3代までの将軍の木像の首、および位牌が持ち出された事件である。
3つの首は三条河原に「正当な皇統たる南朝に対する逆賊」という罪状とともに晒された。
少し早いが結論を先にいっておくと、水戸学に代表される、足利尊氏を「逆賊」とする評価には、歴史的な裏づけがまったくない。
尊氏は「逆賊」などと呼ばれかねない失敬がないように、むしろ配慮し続けた人物だった。
また、弟の直義との名高い兄弟げんか、すなわち観応の擾乱かんおうのじょうらんについても、配慮ができる人物だからこそ弟に大きな権限を持たせ、激しいけんかになったといえる。
■薩長藩閥によって「逆賊」に
尊氏に対する過去の評価の話に戻る。
南北朝時代について、
明治時代の国定教科書『尋常小学日本歴史』には「南北両朝の対立」と表記されていた。
並立する2つ朝廷に対し、どちらが正統だといった評価はされていなかった。
現代の価値観からみれば、ごく当たり前の表記なのだが、
これに噛みついたのが明治44年(1911)1月19日付の読売新聞だった。
「南北朝対立問題(国定教科書の失態)」という見出しがつけられたその記事は、件の教科書を厳しく糾弾する内容だった。
すなわち、建武の中興に際して後醍醐天皇を支えた楠木正成や新田義貞ら「忠臣」と、それに反旗を翻した足利尊氏と直義兄弟ら「逆賊」が、同列にあつかわれていること。
両朝の分立をあたかも国家の分立のように記されていること。
それらが厳しく糾弾された。
この記事は、学界やジャーナリズムを巻き込んだ論争の契機になり、記事に賛同した学者らは、藤沢元造代議士に衆議院で質問させた。
そして2月16日に質問が行われると、一挙に政治問題化したため、2月28日には桂太郎首相が明治天皇の裁定を仰いでいる。
こうして南朝を正統化することが正式に決まり、教科書も南朝正統論にもとづいて書き直されることになったのである。
だが、南朝正統論の論拠は単純でバカバカしい。
明治維新の理念に「天皇親政」があり、後醍醐天皇が元弘3年(1333、翌年に建武と改元)から行った建武の新政も、「天皇親政」を志して実現したものだった。
足利尊氏はそれに弓を引いたから「逆賊」と呼ばれたにすぎない。
そもそも明治政府にとって「天皇親政」など建前で、政治を動かしていたのは薩長藩閥であった。
その建前を傷つけないために、尊氏は逆賊あつかいされたのである。
■後醍醐天皇に対する本当の思い
建武の新政下で参議などの要職に就き、後醍醐天皇から厚遇されていた足利尊氏が、後醍醐天皇側と争うきっかけになったのは、建武2年(1335)に北条氏の残党が一時的に鎌倉を占拠した中先代の乱だった。
当時、鎌倉にいた弟の直義には乱を鎮められず、やむなく尊氏は8月、4万の軍を率いて出兵し、乱を鎮圧した。
そのころ鎌倉では武家政権樹立の機運が高まっており、尊氏はそこに飛び込んでいったわけだ。
そして、京都に戻らず鎌倉に留まっているあいだに、直義が新田義貞と対立。11月に直義が義貞を討伐する目的で軍勢催促状を発給すると、後醍醐天皇は尊氏に謀反の意思があると判断。
尊氏追討の綸旨(天皇の命令)を発し、尊氏の官職を解いた。
そこにいたって尊氏は軍事行動を開始している。
だが、森茂暁氏は『足利尊氏』(角川選書)で、
「凶徒」をはじめ激しい言葉で尊氏を糾弾した後醍醐天皇に対し、尊氏はそうした言葉を一切使っていないことなどを強調。
尊氏が後醍醐に対していだいていたのは「畏敬と追慕の念であったことは間違いない」と記し、さまざまな例を挙げる。
■約束を破ったのは後醍醐天皇の方
たとえば、後醍醐天皇の没後100日に納められた『後醍醐院百ヶ日御願文』では、「尊氏は願文中で自身を『弟子』と記しており、後醍醐から被った恩に報いたいと念じている」という。
また、足利側から書かれた歴史書『梅松論』にも、中先代の乱の平定後、後醍醐天皇の勅使から帰京を求められながら、帰らないと答えたことについて、本意ではなく「深く歎なげきおぼしめされて」いたという。
さらには「いつの世いつの時なりとも君(後醍醐天皇)の御芳志ごほうしをわすれ奉るべきにあらざれば」と述べたという。
いずれにせよ、尊氏は朝敵あつかいされるのが嫌だったからこそ、建武3年(1336)5月25日、湊川の戦いで新田義貞と楠木正成を破ると光厳(こうごん)上皇を奉じて入京し、8月15日、その弟を光明天皇として即位させたのである。
それにこの天皇、北朝の初代とされるが、じつはこの時点では南北両朝に分かれるはずではなかった。
たしかに光明天皇の即位の時点では、後醍醐天皇は退位していない。
だが、比叡山に避難していた後醍醐とは、光明天皇への一本化で話がついていた。
息子の成良(なりよし)親王を皇太子にする代わりに、後醍醐は譲位することで合意。
実際、11月2日に帰京して譲位するとともに三種の神器を光明天皇に渡し、11月4日には成良親王が立太子した。
ところが後醍醐は12月21日、約束を破って京都を脱出し、吉野(奈良県吉野町)に逃れてしまい、南北両朝が並立することになった。
こうした経緯から、南朝が正統だ、尊氏は逆賊だ、などと軽々しくいえないことがわかると思う。
■13年も続いた兄弟の二頭政治
ところで足利尊氏といえば、後醍醐天皇に弓を向けたのに加え、兄弟でひどく争った人物という印象もある。
兄弟とは前出の直義だが、この件はどうなのか。
後醍醐天皇がいったん譲位した5日後の建武3年(1336)11月7日、室町幕府の基本方針を示した建武式目が定められた。
実質的にこれを制定したのは、行政や司法に通じていた直義だったと考えられている。
前出の森氏は建武式目について「足利尊氏が関東方面に支持者の多い直義の手を介して、幕府を京都に置くことの必要性を法知識に詳しい公武の専門家たちに諮問して、関東の有力武士の説得を多分に意識しつつ答申させたのが建武式目であった」(前掲書)と記す。
要するに、幕府の成立当初、兄弟のあいだに意見の相違はなかったようなのだ。
そして建武5年(1338)8月11日、尊氏が光明天皇から征夷大将軍に任命されると、同時に直義も従四位上左兵衛督ひょうえのかみになっている。
兄弟の同時昇進は過去に例がなく、こうして世にもまれな兄弟による「二頭政治」がはじまったのである。
森氏は尊氏が「軍事面(およびそれに伴う恩賞給付)の権限」、
直義が「政務面(実質的には所領裁判)の権限」を持つ二頭政治が、貞和5年(1349)9月まで続いたとみる。
森氏の説明と続けると、「二頭政治は尊氏・直義という両巨頭によって権限の棲み分けという方法をとって、互いに他方を侵すことなく調和的に運営された」ということになる。
■親子対立→兄弟げんか
古今東西、兄弟の一方が一方を従わせるのではなく、
力を合わせて調和的に、
平和裏に政治を運営した例などほとんどない。
しかも尊氏と直義の場合、その状態を13年も続けている。
これはその後のけんかよりもよほど、驚くべきことではないだろうか。
しかし、それが最後までは続かなかった。
尊氏のもとで軍事作戦を実行していた執事の高師直(こうのもろなお)と直義のあいだに亀裂が入り、次第に広がったのである。
一言でいえば革新的な師直は新興の武士、保守的な直義は保守派の武士に支えられ、両派の対立が次第に激化。
このため尊氏は高師直を執事から外すが、師直は直義の殺害を企てる。
結局、直義が担当していた政務を尊氏の嫡男の義詮に引き継ぎ、高師直は執事に復帰することなどを条件に和睦が成立した。
だが、尊氏の次男で直義の養子になり、九州で勢力を拡大していた足利直冬(ただふゆ)が立ちはだかった。
それを受けて尊氏と師直が、直冬追討のために出陣すると、
外されたうえに養子が討伐の対象になって納得がいかない直義が挙兵。
こうして兄弟が激しく争う観応の擾乱が勃発したのである。
観応2年(1351)、高師直らが殺されて直義の勝利に終わるが、
半年後にはまた騒乱が勃発。
結局、尊氏は対立する南朝の後村上天皇から直義討伐の綸旨を獲得。
ようやく直義の軍を破り、鎌倉に幽閉したのちに殺害した。
背景にはすでに述べたように、直義の養子である直冬の存在があった。
尊氏は嫡男たる義詮の地位が脅かされるのを嫌ったのだろう。
いずれにせよ、足利尊氏という人物は、後醍醐天皇に対しても、弟の直義に対しても、むしろ融和的な態度をとったことこそ強調されるべきなのではないだろうか。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます