双葉山 定次[3](ふたばやま さだじ、1912年2月9日 - 1968年12月16日)は、大分県宇佐郡天津村布津部(現:大分県宇佐市下庄)出身の元大相撲力士。第35代横綱。本名は龝吉 定次(あきよし さだじ)[1]
■定次少年の角界入り
1912年2月9日に大分県宇佐郡天津村布津部(現:大分県宇佐市下庄)で生まれる。5歳の時に吹き矢が自身の右目に直撃して負傷し、右目が半失明状態になった[4]。後年、双葉山は著書「相撲求道録」の中でこの事件について、友達と遊んでいる最中に目を傷めたことは覚えているものの、その原因が吹き矢だったことについてははっきりとした記憶が無いと語っているが、横綱審議委員長を務めた舟橋聖一は「誰が吹き矢を拭いたのかを唯一知っていたのは定次少年の父親で、定次少年が吹き矢を吹いた人物を恨んで自身のマイナスになることと、定次自身が傷つかないようにするため、決して名前を出さなかった」と分析している[5]。少年時代は成績優秀で普通に進学を目指していたが、父親が営む海運業が失敗して5000円(現在の2億5000万円相当)の借金を負い[6]、兄と妹と母親も早くに亡くしている事情から、次男でありながら一家の家計を支えるべく手伝いをしながらたくましく育つ[7]。浪曲研究家の芝清之が作成した「双葉山物語」では、この海運業の手伝いをしているときに錨の巻上げ作業で右手の小指に重傷を負ったとしている[4]ほか、定次が14歳の頃、乗船していた船が大波を受けて転覆して海に投げ出されたが、たまたま近くを通っていた船に助けられて九死に一生を得た。その後定次は別の業者に雇われることになった[8]。
1912年2月9日に大分県宇佐郡天津村布津部(現:大分県宇佐市下庄)で生まれる。5歳の時に吹き矢が自身の右目に直撃して負傷し、右目が半失明状態になった[4]。後年、双葉山は著書「相撲求道録」の中でこの事件について、友達と遊んでいる最中に目を傷めたことは覚えているものの、その原因が吹き矢だったことについてははっきりとした記憶が無いと語っているが、横綱審議委員長を務めた舟橋聖一は「誰が吹き矢を拭いたのかを唯一知っていたのは定次少年の父親で、定次少年が吹き矢を吹いた人物を恨んで自身のマイナスになることと、定次自身が傷つかないようにするため、決して名前を出さなかった」と分析している[5]。少年時代は成績優秀で普通に進学を目指していたが、父親が営む海運業が失敗して5000円(現在の2億5000万円相当)の借金を負い[6]、兄と妹と母親も早くに亡くしている事情から、次男でありながら一家の家計を支えるべく手伝いをしながらたくましく育つ[7]。浪曲研究家の芝清之が作成した「双葉山物語」では、この海運業の手伝いをしているときに錨の巻上げ作業で右手の小指に重傷を負ったとしている[4]ほか、定次が14歳の頃、乗船していた船が大波を受けて転覆して海に投げ出されたが、たまたま近くを通っていた船に助けられて九死に一生を得た。その後定次は別の業者に雇われることになった[8]。
定次は、相撲の方はそれほど気持ちを入れていたわけではなかったが、初めて出場した相撲大会で畳屋の男と取組むことになった。だが、定次は相撲を取ったことがなかったため相手に食いつかれてしまい動けなくなったところ、見物人から「押せ!押せ!」の声が聞こえたため、定次は相手を上から押さえつけて倒し、相手はしばらく起き上がれなかったという[8]。このことが地元の新聞に載り、この記事を見た大分県警察部長の双川喜一(のちに明治大学専務理事)の世話で立浪部屋に入門、1927年3月場所に初土俵を踏む。
四股名の双葉山は「栴檀は双葉より芳し」から命名し、入門時に世話になった双川の一字も含まれる[7][9]。双川は大分県に赴任する前、立浪の出身地の富山県で学務部長を務めていて立浪とは昵懇の間柄で、かねてから全国を転勤して回る双川に新弟子を見つけたら入門の世話をするように頼んでいた。そのことから、立浪が弟子勧誘の網を全国に張り巡らせていたことが窺える[7]。
■69連勝
1935年に蓄膿症の手術を受けたのを機に体重が増え、それまでの相撲ぶりが一変した[12]。取り口そのものは正攻法で変わらなかったが、それまでは力不足で土俵際まで押し込まれることが多かったのに対し、立合いから「後の先をとる」を地で行き相手より一瞬遅れて立つように見えながら先手を取り、右四つに組み止めた後に吊り出し、寄り、または左からの上手投げで相手を下すようになった[1][9]。なお、この年に「未練はございません」と言って引退を決意して仙台に行ったが、この時は後援者に諭されて戻った[14]。
・・・
■70連勝ならずの一番
1939年1月場所、この場所の双葉山は前年の満州・大連巡業でアメーバ赤痢に感染して体調を崩し、体重が激減してしまい、当初休場を考えていた。しかし、力士会長だった玉錦が前年に急死したのと、休場続きの武藏山は今場所も休場していたために横綱が男女ノ川しかいなくなるため、責任感の強い双葉山は強行出場を決意した。双葉山は調子が悪いながらも初日から3日目まで連勝を重ね、70連勝を賭けて1月場所4日目(1月15日)を迎える。
・・・
安藝ノ海は左に回り込んで双葉山の右に食い下がり、双葉山の右掬い投げに対して左外掛けを掛けた。両者の身体が大きく傾いたが一度堪えた後、双葉山が安藝ノ海の身体を担ぎあげるようにして外掛けを外し、再度右から掬い投げにいったので、安藝ノ海の身体は右側に傾きながら双葉山と共に倒れた[24][25]。双葉山の身体が先に土俵に付いていたため、双葉山の連勝は69で止まり、安藝ノ海は金星を挙げた。
・・・
この69連勝は2021年1月場所終了時点まで最多連勝記録であり、2021年1月場所終了時までにこの記録を超えた力士は現れていない。近年では2010年に白鵬翔が63連勝を挙げたが、あと一歩及ばなかった。双葉山が三役に上がった頃、一場所の取組日数は11日だったが、双葉山人気が凄まじく、1月場所でも徹夜で入場券を求めるファンが急増したため、日数が13日となり(1937年5月場所から)、さらに現在と同じ15日(1939年5月場所から)となった。












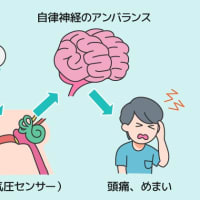


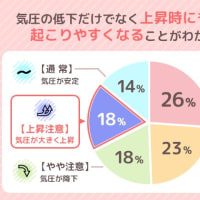
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます