ーQ1-
その後、多くの相互援助条約、集団安全保障条約、軍事同盟条約が各国間に締結されてきたが、そのほとんどは明示的に集団的自衛権を法的根拠として援用している。米州諸国は早速1947年に全米相互援助条約に署名し、「アメリカの一国に対するいかなる国の武力攻撃も、アメリカのすべての国に対する攻撃とみなすことに合意し」、「個別的又は集団的な固有の自衛権を行使してそのような攻撃に対抗するために援助することを約束」(第3条1項)した。そのほか、48年のブリュッセル条約、49年の北大西洋条約、
<
北大西洋条約(きたたいせいようじょうやく、North Atlantic Treaty)は、北大西洋地域における集団防衛・集団安全保障に関する軍事同盟構築のための条約。 条約締結地のワシントンD.C.にちなみワシントン条約と呼ばれることもあるが、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(締結地がやはりワシントンD.C.で同じ通称)との混同を避けるためか浸透はしていない。
条約の根幹は、いずれの加盟国に対する攻撃も全加盟国に対する攻撃とみなし集団的自衛権を発動することによって集団防衛体制を構築し、加盟国外からの攻撃を抑止することにある。
北大西洋条約機構(NATO)は、本条約に基づいて結成された軍事同盟である。

2014年5月6日にも、安倍が欧州歴訪の際にNATOのラスムセン事務総長と会談[39]。海賊対策のためのNATOの訓練に自衛隊が参加することや、国際平和協力活動に参加した経験を持つ日本政府の女性職員をNATO本部に派遣することなどで合意[39]。さらに日本とNATOとの間で具体的な協力項目を掲げた「国別パートナーシップ協力計画 (IPCP)」に署名した[39]。
またNATOはアフガニスタンにおける活動の中で、現地の日本大使館が行っている人道支援や復興活動に注目しており、軍閥の武装解除を進める武装解除・動員解除・社会復帰プログラムの指導者的立場にある日本との連携を模索している。
さらには、日本をNATOに加盟させようとする動きもある。これはNATOを北大西洋地域に限定せずに世界規模の機構に発展させたうえで、日本のほかオーストラリア、シンガポール、インド、イスラエルを加盟させるべきだという意見である。ルドルフ・ジュリアーニ元ニューヨーク市長、ブルッキングス研究所のアイボ・ダールダーシニアフェローなどが提唱している。
2018年5月、北大西洋理事会は、ブリュッセルの在ベルギー日本大使館にNATO日本政府代表部を開設することに同意[40]。
2018年7月1日、NATO日本政府代表部を開設した[41]。
2021年時点で、日本は「グローバル・パートナー国」と位置付けられている。
>
55年のワルシャワ条約など、いずれも集団的自衛権を基礎として規定している。日米安全保障条約も、両国が個別的または集団的自衛の固有の権利を有することを確認した(前文)うえで、共同防衛を規定(第5条)している。
ーA1-
弧状列島自由民主主義・普通選挙・議員内閣制与党は、次期国政選挙公約
「日本のNATO加盟の加速」表明か
公表時期不明、石本泰雄
<
石本 泰雄(いしもと やすお、1924年(大正13年)12月5日 - 2015年(平成27年)12月8日[1] 91歳没)は、日本の法学者。専門は国際法。学位は、法学博士(東京大学・論文博士・1962年)。大阪市立大学名誉教授。日本学士院会員。
東京大学法学部助手、大阪市立大学法文学部講師、大阪市立大学法学部教授、大阪市立大学法学部学部長、上智大学法学部教授、神奈川大学短期大学部特任教授などを歴任した。
>
国連憲章は、武力による威嚇または武力の行使を一般的に禁止しているが(第2条4項)、その例外として、「武力攻撃が発生した場合には」「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を行使することを認めている(第51条)。集団的自衛権については憲章はなんらの定義もしていないが、たとえ自国が直接には武力攻撃を受けていなくても、自国と深い関係にある他の国家が武力攻撃を受けた場合には、これに対して防衛する権利であるといってよい。
憲章に集団的自衛権についての規定が加えられたのは、1945年のサンフランシスコ会議においてであり、憲章の原案たる前年のダンバートン・オークス提案には含まれてはいなかった。
原案では、地域的取極や地域的機関による強制行動は、旧敵国に対するものを除いて、すべて安全保障理事会の許可を要するものとされていた。したがって安全保障理事会において少なくとも5常任理事国の一致がない場合には、地域的取極や地域的機関による強制行動は不可能という結果になる。これに反発したのは主として米州諸国であった。これらの諸国は、サンフランシスコ会議の直前にチャプルテペック規約に署名し、第二次世界大戦終了後に相互援助条約を締結することを約束していた。しかし、安全保障理事会の許可がなければ、このような相互援助条約に基づく行動がとれないというのでは、条約の機能がきわめて限られたものとなることは明らかである。
サンフランシスコ会議で、アメリカが強く集団的自衛権の規定の挿入を推進したのは、このような背景があったからである。その結果、地域的取極や地域的機関による行動には安全保障理事会の許可を要するという規定を維持しながら(第53条1項)、その例外として集団的自衛権に基づく行動は、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」は、単に安全保障理事会に報告すれば足り、許可を必要としないという現行憲章の構造が成立した。
その後、多くの相互援助条約、集団安全保障条約、軍事同盟条約が各国間に締結されてきたが、そのほとんどは明示的に集団的自衛権を法的根拠として援用している。米州諸国は早速1947年に全米相互援助条約に署名し、「アメリカの一国に対するいかなる国の武力攻撃も、アメリカのすべての国に対する攻撃とみなすことに合意し」、「個別的又は集団的な固有の自衛権を行使してそのような攻撃に対抗するために援助することを約束」(第3条1項)した。そのほか、48年のブリュッセル条約、49年の北大西洋条約、55年のワルシャワ条約など、いずれも集団的自衛権を基礎として規定している。日米安全保障条約も、両国が個別的または集団的自衛の固有の権利を有することを確認した(前文)うえで、共同防衛を規定(第5条)している。もっとも政府の解釈では、この条に基づく行動はアメリカ合衆国については集団的自衛権の行使に相当するが、わが国については個別的自衛権の行使に相当するという。共同防衛が「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対するものだからである。しかし、わが国がアメリカ合衆国に基地を提供し、軍事的に結合すること自体、集団的自衛権を基礎としなければ説明することができないと思われる。
集団的自衛権の行使は、かならずしもあらかじめ条約や協定によって約束されている場合にだけ許されるわけではない。条約上の根拠がなくてもこの権利を行使することが認められる。
しかし、国連憲章第51条の規定の成立経過や、その後の実行にみれば明らかなように、集団的自衛権はむしろ軍事同盟網の形成の法理的基礎として機能してきた。そのために、集団的自衛権のこのような機能は、本来、国連憲章が構想した集団的安全保障の機能を逆に減殺すると評されている。












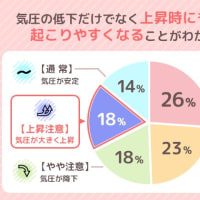
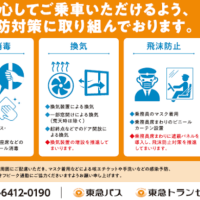


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます