<検査感度低い「陰性証明」お札(ふだ)数増加は、飛沫感染肺炎ウイルス無症状患者の増加、医療行政=予算要員整備体制=を崩壊させるか>
:::::
2020/09/06 5:00
「陰性証明」というお札(ふだ)バブルの弊害
森井 大一(もりい・だいいち)Daiichi Morii
大阪大学医学部附属病院感染制御部医師
大阪大学医学部附属病院感染制御部。2005年3月大阪大学医学部卒業、同年4月国立病院機構呉医療センター、2010年大阪大学医学部附属病院感染制御部、2011年米Emory大学Rollins School of Public Health、2013年7月厚生労働省大臣官房国際課課長補佐、2014年4月厚生労働省医政局指導課・地域医療計画課課長補佐、2015年4月公立昭和病院感染症科を経て今に至る。2020年8月から厚生労働省技術参与として新型コロナ対策にも関わる。※ただし、東洋経済オンラインへの寄稿は1人の医療者としての私見に基づくもので、筆者の関係組織の公式見解とは一致しない
筆者は9月4日の東洋経済オンラインのコラム『「誰でもPCR」は公費の大半を捨てることになる』で、PCR検査は「感染が疑われる人(=検査を最も必要とする人)が速やかに検査される」ために拡充すべきで、陰性を確認するための検査の拡大は、非効率で公費の無駄遣いであることを述べた。個人にとってそうした検査の結果にどのような意味があるのかも説明した。今回は、PCR検査で儲かる構造が作られてバブルとも呼べる状況が生まれていること、そのことが引き起こしている問題を指摘したい。
5月以降、症状がなくても、接触歴がなくても、医者がやりたいといえばPCR検査が公的保険でカバーされることになった。医療機関が診療の中でPCR検査をするには、大きく2つのパターンがある。
①1つは、検体採取だけを医療機関で行い、その検体を民間の検査会社等に運んで実際のPCR検査はそこで行ってもらうやり方(外注検査)である。
②もう1つは、検体採取から実際のPCR検査そのものまでを自分の施設で行うやり方(インハウス検査)である。診療報酬上は、前者の外注の場合は1万8000円、後者のインハウスの場合は1万3500円の診療報酬が検査ごとに医療機関に入る。
しかし、外注の場合は民間の検査会社が1万8000円に近い額を持っていくので、医療機関に残る収益はあまりない。輸送料がかさむ場合などは、結果的に医療機関の持ち出しとなることさえある。
一方でインハウス検査の場合、試薬等のランニングコストは人件費を除けば8000円程度であり、1回に検査する検体数を増やせば1件当たりのコストはさらに低く抑えることができる。もちろん初期投資として機器の導入は必要だが、公費による全額補助の仕組みができたので、医療機関が負う投資リスクはかなり低くなっている。
インハウスのPCR検査は「打ち出の小槌」になった
このインハウス検査の参入障壁は、実際に手を動かせる検査技師を確保できるかどうかに大きく依存しているが、一度インハウス検査の体制が整えられれば検査すればするだけ医療機関は儲かる構造になっている。通常の保険診療では患者はかかった医療費の3割を自己負担することになるが、こと新型コロナウイルスのPCR検査に限っては、患者の自己負担分も税金で賄われる。
ここで重要なポイントがある。PCR検査というサービスを中心に見てみると、外注に頼らざるをえない多くの医療機関は、このサービスの買い手であって売り手ではない。医療機関が検査会社にお金を払ってPCR検査というサービスを提供してもらうのだ。
しかし、インハウス検査が可能な医療機関は、このサービスの買い手と売り手の二役を同時に担うことになる。医療機関がそのサービスを求め、医療機関自身がそのサービスを提供する。そして、その費用は保険と税金で賄われる。これは、PCR検査という打ち出の小槌を手にしたのと同じである。
検査の適応は「医師が必要と判断」するかどうかの一点のみである(「疑義解釈資料の送付について(その12)」令和2年5月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)。症状も曝露歴も必要ない。このような仕組みを最大限活用して莫大な利益を上げている医療機関もある。だが、システムがそうなっているのだからもちろんまったく適法な経済活動である。
このようなインハウス検査が可能な医療機関は、当初は大学病院等の大病院が中心だった。したがって、大学病院の圧力団体がスクリーニングのPCR検査を保険収載すべきというキャンペーンを先頭に立って行った。まったくもって合目的な振る舞いというほかない。
しかし、PCR検査機器導入に関わる公費助成が進んだことと、上記に説明した収益構造から、比較的小規模の施設でも自前でPCR検査を行うところが増えてきている。検査バブルとでも言うべき状況だ。このようなモデルが持続可能なはずはなく、早晩どこかで国ははしごを外さざるをえないだろう。
「目詰まりの除去」でも無制限には増やせない
しかし、実際には検査機器と検査技師をそろえても思いどおりにインハウス検査が進められないという事態も起こっている。最も大きな原因と考えられるのは試薬の不足である。
新型コロナウイルスの感染は世界に拡大しており、8月末時点で、インド(人口13.6億人)で7万人超、アメリカ(人口3.3億人)で4万人超の新規陽性者が毎日出ている。日本では2月から8月末時点までの累積で陽性確認者数が7万人弱であるのと比較すると、これらの数字がいかに膨大であるかわかるだろう。つまり、これだけの数の患者を見つけ出すために、各国で膨大なPCR検査を行っているわけだ。
PCR検査の障害となっているものについて、安倍晋三首相は5月4日の記者会見(緊急事態宣言の延長を表明した会見)で「目詰まり」との表現を用いている。具体的には、上述した試薬不足や検査技師不足に加えて、検査機器整備の遅れ、検体採取に対する医療機関の非協力、検査判断を保健所に集約したこと、疑い患者の診療を行う帰国者・接触者外来を非公表としたことなど、さまざまな要因があった。
これらの目詰まりの一部はすでに解消され、1日当たりの検査実施件数は1月には数百であったが、4月には数千となり、8月末においては2万程度となっている。数として増えたのは事実だ。しかし、それはしょせん程度問題である。より重要なことは、1億2000万人の人口にとっては、どこまで行ってもPCR検査能力という社会的に重要な資源は有限であることのほうだ。
量的拡充は大いに結構だが、それをどれだけ主張したところで本質的な問題は解決しない。ナイーブな「巷の拡大論」に欠けているのは、「限りある資源の効率的な配分」という視点である。
このことがシニカルな形で現実的な問題になりつつある。それは、非医療におけるPCR検査需要の増大が、医療現場での本当に必要な検査の障害となるという事態である。
どのような形で障害となるかに入る前に、現状で非医療の検査がどれだけ行われているのかについて考えておきたい。上述した8月末時点での1日当たり約2万件という検査件数には、非医療の検査や保険適応外の検査は入っていない。保険適応であっても、スクリーニング検査については報告の段階で含めていない施設も多いと考えられ、筆者の考える「不必要で無駄な」検査はこの統計に含まれない傾向があると推測される。
つまり、発表されている実施件数の何倍もの数の不必要で無駄な検査がすでに毎日行われていると考えられるのだが、その実数のデータはどこを見てもみつからない。どうやら誰も把握していないようである。そのうえで、非医療の需要が医療現場に与える影響を考えたい。
高価な民間検査が医療需要を追い出してしまう
非医療の需要は診療報酬とは無関係なので、すべて自由市場において、質、価格、量が決定されることになる。まず質についてだが、そもそもの動機が陰性ほしさなので、検査の感度が悪ければ悪いほど顧客の満足度は上がる。
これは一種の市場の失敗ともいえる状況であり、市場を適正に機能させるためには、非医療の検査についての検査精度も本来は行政が管理する必要がある。2次補正予算の中に「外部精度管理調査」の項目があるが、問題はこの「外部精度管理調査」制度が自由診療や非医療の検査についても適用されるものであるのかが、はっきりとしていない点である。非医療検査に関して、もしこのまま規制が及ばない状態が続けば、市場はルーズなサービスをより選択するよう働く可能性が高い。
それと同時に、医療の検査には確実にこの外部精度管理が適応されるため、検査会社から見れば、医療需要に応えるよりも、非医療・自由診療の需要に応じたほうがビジネスとして楽ということにもなりうる。そのようなことが実際に起こってしまえば、医療側の検査需要はますます後回しになり、相対的に需要逼迫・供給不足の傾向がより加速されることになる。
次に価格であるが、現在の自由市場での相場は1件4万円ほどとなっていることが国会でも議論されている(8月19日、衆院厚生労働委 閉会中審査の動画)これは、医療における外注検査の1万8000円という額をはるかに超えるものだ。非医療需要の将来的な不安定性という点をいったん無視すれば、1万8000円よりも4万円出すところの検査を請け負ったほうが儲かることは幼稚園児でもわかる。
PCR検査の処理能力はどこまで行っても有限である。不必要なものまで需要を喚起してしまえば、公的医療保険制度で価格が固定されている医療側の需要は、人々の不安と信仰に煽られた非医療の需要に簡単に押し出されることになる。民間検査会社による検査なくして、量的拡充はありえないのだから、非医療の検査需要でこれが占有されることは、本当に必要な医療の検査にとっては好ましくない。
PCR検査の枯渇感がメディアによって強調され煽られる中で、陰性証明というお札(ふだ)への信仰が生まれた。そして、このお札がなければあらゆる社会経済活動を行ってはならないというような雰囲気がいつの間にか醸し出された。決定的だったのは、医療現場がそれに悪乗りしたことで、「専門家集団」の権威によるお墨付きを与えてしまったことだ。
「まやかし」でPCR検査を規範化する愚かさ
このことによって、社会経済活動をする以上はPCR検査しなければならないということが、一部で規範化してしまった。このような「変なルール」が一度できてしまうと、「PCR検査による陰性証明」ということの誤謬を理解していたとしても、宣伝文句として社会的にアピールすることに新たな価値が生まれるという倒錯した現象が起こる。そしてそのこと自体が「PCRなしでは何事も進められない」という教条をさらに補強していくことになる。
長期的に見れば、これは企業活動に新たな錘(おもり)が付け加わったということなのだが、いずれこの「まやかし」に多くの人が気づいた段階で、PCR信仰もあっという間に霧散するだろう。筆者は、情報が行き渡りさえすれば、PCRに関する多くの企業の決定も合理的着地点に落ち着くことを疑ってはいない。
今、雨後の筍のごとくあちこちで勃興しているPCRビジネスは、数年後にはほとんど残っていないだろう。しかし、そこまで待つ必要があるだろうか。指定感染症の指定期間は原則1年であり、1回に限り延長をすることができると定められている。指定されたのは今年の1月だから、この扱いをどうするかはそう遠くなく決定される。常識的に考えれば、二類か五類かの議論もそのあたりをメドに進んでいくだろう。
筆者自身は、冬の流行を把握し終わった来春に結論を出すべきだと考えているが、実際の決定はもっと早いかもしれない。もし五類相当となれば、それは季節性インフルエンザと同等の流行(1500万人の感染者と1万人の超過死亡)を容認するということを意味する。それは、血眼になって無症状者の全数把握を目指す努力そのものが無効化される瞬間である。半年後にはそのような文脈が付け加わる可能性があることを知れば、「巷の拡大論」のようなバカ騒ぎに付き合う必要はないと容易に理解できるはずだ。











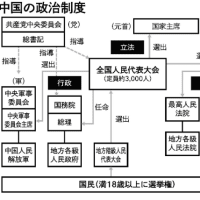






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます