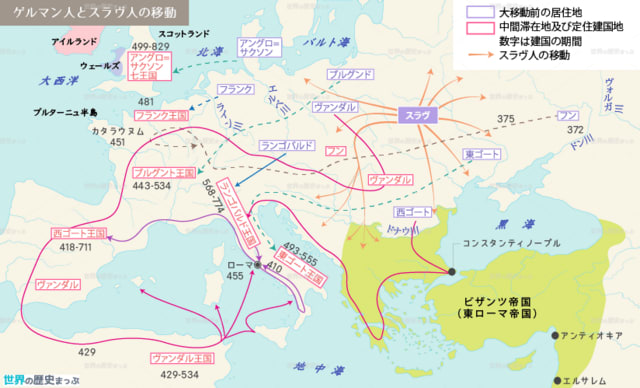

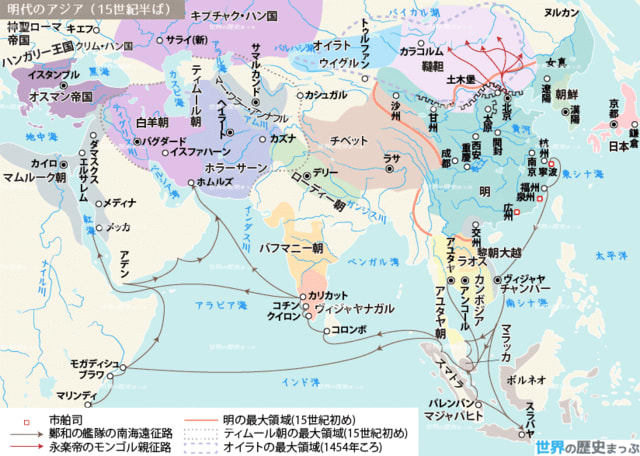
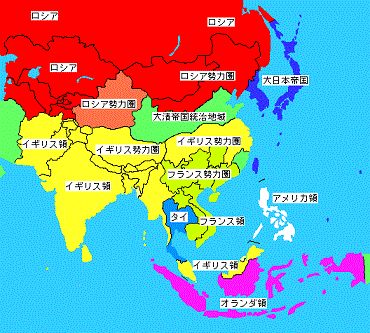
■モーハンダース・カラムチャンド・ガーンディー(グジャラーティー文字表記:મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી、デーヴァナーガリー文字表記: मोहनदास करमचन्द गांधी、ラテン文字表記:Mohandas Karamchand Gandhi、1869年10月2日 - 1948年1月30日、78歳没)は、インドのグジャラート出身の弁護士、宗教家、政治指導者である。
マハトマ・ガンディー(=マハートマー・ガーンディー)として知られるインド独立の父。「マハートマー(महात्मा)」とは「偉大なる魂」という意味で、インドの詩聖タゴールから贈られたとされるガンディーの尊称である(自治連盟の創設者・神智学協会会長のアニー・ベサントが最初に言い出したとの説もある)。また、インドでは親しみをこめて「バープー」(बापू:「父親」の意味)とも呼ばれている。
1937年から1948年にかけて、計5回ノーベル平和賞の候補になったが[1]、受賞には至っていない[2]。ガンディーの誕生日にちなみ、インドで毎年10月2日は「ガンディー記念日」(गांधी जयंती、ガーンディー・ジャヤンティー)という国民の休日となっており、2007年6月の国連総会では、この日を国際非暴力デーという国際デーとすることが決議された。
■南アフリカで弁護士をする傍らで公民権運動に参加し、帰国後はインドのイギリスからの独立運動を指揮した。民衆暴動やゲリラ戦の形をとるものではなく、「非暴力、不服従」を提唱した(よく誤解されるような「無抵抗主義」ではない)。
この思想(彼自身の造語で「サティヤーグラハ」、すなわち「真理の把握」と名付けられた)はインド独立の原動力となり、イギリス帝国をイギリス連邦へと転換させた。さらに政治思想として植民地解放運動や人権運動の領域において、平和主義的手法として世界中に大きな影響を与えた。特にガンディーに倣ったと表明している指導者にマーティン・ルーサー・キング・ジュニア、ダライ・ラマ14世等がいる。
性格的には自分に厳しく他人に対しては常に公平で寛大な態度で接したが、親族に対しては極端な禁欲を強いて反発を招くこともあったという。なお、インドの政治家一族として有名な「ネルー・ガーンディー・ファミリー」(インディラー・ガーンディーら)との血縁関係はない[3]。
■1888年にロンドンで、インドの宗教思想を取り入れた神秘思想結社・神智学協会の会員と出会い、さらに神智学の創始者ヘレナ・P・ブラヴァツキーや2代目会長のアニー・ベサントにも会い、インド哲学・ヒンドゥー教の精神と文化に興味を持つようになった[4]。ガンディーは、当時のヨーロッパでインド哲学(ヒンドゥー教)の要と考えられていたインドの宗教的叙事詩『バガヴァッド・ギーター』を、サンスクリット語でもグジャラート語でも読んだことがなかったが、神智学協会員との出会いがきっかけとなり、神智学協会版テキストで『バガヴァット・ギーター』を読み、英語を通じてインドの伝統を学ぶようになった[5]。
■卒業後、1893年にはイギリス領南アフリカ連邦(現在の南アフリカ共和国)で弁護士として開業した。しかし、白人優位の人種差別政策下で、イギリス紳士としてふるまったが列車の車掌にクーリー(人夫)扱いされるという人種差別を体験した[5]。ここから「インド人」意識に劇的に目覚めたといわれるが、Richard G. Foxによると、ガンディーはしばらくの間従来通りのイギリス化の方向性を保ち、その後インド意識に目覚めていったようである[5]。
■なおガンディーはこれ以前から日本の中国侵略に極めて批判的であり、1939年にハリジャン紙に掲載された日本の生活協同組合運動指導者である賀川豊彦との対談でも「あなたがた日本人はすばらしいこともなしとげたし、また日本人から、私たちは多くのことを学ばなければなりません。ところが、今日のように中国を併呑したり、そのほかぞっとするような恐ろしいことをやっていることを、どのように理解したらいいでしょうか」と批難している。[11]
■印パ戦争さなかの1948年1月30日、ガンディーはニューデリー滞在場所であるビルラー邸の中庭で射殺された。
■個人資産[編集]
糸車を廻すガンディー。但し本葉はライフ誌を飾った有名なCongress Party & Gandhiではない
ガンジーは金融資産も不動産も、全く持っていなかった。個人的な所有物は、以下のものだけだった。
- インド綿布の衣と草履。
- 眼鏡と入れ歯。
- 竹の杖。
- 糸車。糸車を廻すカンジーのイメージは著名だが、政治指導者の彼が自ら糸を紡ぐのは、インド綿花を輸入加工してインドに再輸出するイギリスの植民地経済政策に対する抵抗の意思表示であり、また彼の「働かない日に食べるパンは、盗んだパンである」という信条の実践であった[29]。
- いわゆる「見ざる言わざる聞かざる」の三猿の像。日本人から貰ったものという。
- 人と会う約束の時間に遅れないための、インガーソルの懐中時計。紐で首にかけていた。
- 携帯用便器。彼はインドの平均寿命の短さは、野糞があたりまえの国民の衛生観念の欠如のためであると信じており、ガンジーがいかに衛生を重んじているかを示す意味があった。
- 食事のための乳をとる雌ヤギが1匹。
- 習字用の鉛筆と、古い封筒を切り開いた練習用紙。鉛筆は、かならずちびて持てなくなるまで使った。物を無駄にすることは、それを作るための同胞の労働をないがしろにすることになるという思想からであった。
- 一冊の『バガヴァッド・ギーター』。
彼はこれらを側近に持たせ、ガンジーの行くところには必ず携帯便器を担ぎ、ヤギを曳いた弟子が従った。














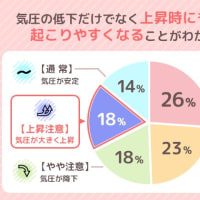

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます