:::::
斎藤 彰 (さいとう・あきら)
ジャーナリスト、元読売新聞アメリカ総局長
1966年早稲田大学卒業。
68年米カリフォルニア州立大学バークレー校大学院修士課程修了、70年読売新聞入社。
ワシントン常駐特派員を2度務めた後、アメリカ総局長、東京本社取締役調査研究本部長などを歴任。
著書に『中国VSアメリカ』、『アメリカはカムバックする!』(いずれもウェッジ)がある。
:::::
米国では最近、台湾有事ともからめ、中国が混迷化する「ウクライナ戦争」から何を学んだかについての論議が活発化しつつある。
〇西側の対応を学習材料とする中国
ロシア軍のウクライナ侵略から1年――。
戦争が長期化する中で、バイデン政権にとっての直近の最大関心事は、中国が対露軍事支援に踏み切るかどうかに集まっている。
しかしそれとは別に、中国は今次戦争そのものをどう見てきたかの論議も無視できない。
米側専門家の間では、
①侵攻開始20日前に中露首脳会談が行われたにもかかわらず、プーチン大統領から習近平国家主席に事前通報もなく、中国側を困惑させた、
②ロシア側は十分な準備なしに侵攻作戦に乗り出したため、苦戦を強いられてきた、
③世界の目がアジアにおける〝第二のウクライナ・シナリオ〟として、にわかに中国の台湾進攻問題に集まり始め、中国側は意表を突かれた、
④中国は世界世論と対露友好関係重視の間で今後難しい対応を迫られている――などの見方が目立つ。
では中国は、具体的に「ウクライナ戦争」からどんな教訓を学んできたのか。
伝統ある外交問題専門誌「Foreign Affairs」(電子版)は去る先月14日号で、エヴァン・ファイゲンバウム「カーネギー財団」副所長らによる「米国主導の秩序維持で多国間結束が続く限り、(中国のような)大国といえども、経済戦争から難を逃れられない」と結論付けた以下のような分析記事を掲げた:
「ロシアがクリミア半島を占領した2014~15年のウクライナ危機当時、西側諸国はロシア側にそのコストを負担させ、行動を再考させ、停戦交渉を有利に進めるために、何カ月もかけて慎重な対露制裁を画策してきた。
ところが、22年、プーチンがウクライナ領のさらなる拡大のみならず、国全体の占領に乗り出した途端、西側の対露制裁は直ちに大規模かつ全面的経済戦争へと化していった。
豪州、カナダ、日本、英国、米国に至る同盟諸国が、ロシアのすべての外貨準備金の凍結を発表し、ロシアを国際送金システム『SWIFT』から締め出した。このことから中国は、新たな教訓を学んだ」
「ウクライナ侵攻開始当時、ロシアは日産1100万バレルの石油産出国であり、国内総生産(GDP)世界第10位の経済大国であり、地政学的にも、中国同様に核保有の国連安全保障理事会常任理事国として、もろもろのグローバル組織に関与してきた。
中国の経済規模はロシアの10倍と巨大であり、グローバル経済特に、貿易,投資、キャッシュフローなど米国とのつながりの面でも、ロシアとは比べものにならないほど甚大であることは事実だ。
しかし、もしその中国指導部が、自国ほどの第一級経済国は巨大すぎて、(台湾などの国際危機の際に)制裁対象外となると考えたとしたら、昨年の出来事は心穏やかならざるものになったはずだ」
「中国は(ウクライナでの教訓から)、仮に台湾侵攻に踏み切った場合、多大な経済的リスクゆえに西側政界が対中制裁を踏みとどまるとは推定できなくなった。
なぜなら、米国および欧州同盟諸国は、アジアで第7位の経済規模を誇り、グローバル・サプライチェーンとの重要なリンク役を果たしている台湾と比較しても小規模な経済国でしかないウクライナに対してさえ、国家的かつグローバルなリスクを冒してまで支援に乗り出したからに他ならない。
すなわち、西側の主だった制裁は弱小国に限定され、(中国のような)主要国に対する制裁は軽微なものにとどまる保証はなくなったのだ」
「中国は(ウクライナでの教訓から)、仮に台湾侵攻に踏み切った場合、多大な経済的リスクゆえに西側政界が対中制裁を踏みとどまるとは推定できなくなった。
なぜなら、米国および欧州同盟諸国は、アジアで第7位の経済規模を誇り、グローバル・サプライチェーンとの重要なリンク役を果たしている台湾と比較しても小規模な経済国でしかないウクライナに対してさえ、国家的かつグローバルなリスクを冒してまで支援に乗り出したからに他ならない。
すなわち、西側の主だった制裁は弱小国に限定され、(中国のような)主要国に対する制裁は軽微なものにとどまる保証はなくなったのだ」
しかし、中国が上記のような教訓をウクライナで学んだとしても、それは、近い将来、台湾武力統一の延期や断念を意味するわけでは断じてない。
むしろ、その逆に、今回露呈したロシア軍の対ウクライナ作戦の欠陥ぶり、西側諸国の反応を十二分に研究、分析し、台湾進攻作戦をより精巧なものにするための恰好の学習材料とみていることは確実だ。
〇教訓となった〝ロシアの失敗〟
この点に関連して注目されるのは、イェンス・ストルテンベルグ北大西洋条約機構(NATO)事務総長の発言だ。
同事務総長は去る2月1日、来日した際、慶應義塾大学での講演で、台湾有事を念頭に「中国はロシアによるウクライナ侵略作戦を極めて注意深く観察、学習しており、その結果が(台湾侵攻のような)インド太平洋のパワー・バランスを揺るがす同国の将来の政策決定に影響を与えることになる」と警告。
さらに具体的に以下のように述べた:
「もし、ロシアのプーチン大統領が今回の戦争で勝利すれば、中露両国とも強引な武力行使によって目的を達成できるとのメッセージを発することになる。その結果、世界はより危険で、脆弱性をさらけ出す。
中国はNATOの敵国ではないが、より一段と権威主義国家の体をなしつつあり、一連の覇権的強圧的政策は欧州大西洋そしてインド太平洋地域に重大な安全保障上の結果をもたらしかねない。
また、中露両国は近年、軍事面での関係緊密化、日本近海における海空両面での合同軍事演習などを含む戦略的パートナーシップを強化しつつある点も懸念材料だ。
これに対処するには、地域ではなくグローバルな協力関係が不可欠であり、NATO諸国と日本などアジア諸国との関係強化が望まれる」
ではこれまで、戦争作戦面で中国側は具体的に何を学んだのか。
この点に関し、2月24日付の米「TIME」誌(電子版)は、ロシア軍が短期決戦で勝利できなかった「4大要因」として以下の点を挙げているが、これらは台湾武力統一の可能性も排除しない中国軍部にとっても、無視できない重要な教訓になっていると推察される:
① 兵站面での長期計画欠如=ロシア軍は当初、「作戦開始後数週間での目的達成」を確信していた。
従って、長期戦に備えた兵站支援の備えが不十分だった。
メイソン・クラーク「戦争問題研究所」上級研究員は「軍指導部のみならず、クレムリンも、戦争がこれだけ長期化し、しかも戦線も拡大することを予測できなかった」と述べている
② ウクライナ側レジスタンスの過小評価=マーク・キャンシアール「米戦略国際問題研究所」(CSIS)上級顧問によると、ロシア軍侵攻直前までのゼレンスキー・ウクライナ大統領の国内支持率は27%と低迷し、ウクライナ国民自体も政府不信を募らせていた。
このため、プーチン氏は電撃作戦によって、ゼレンスキー政権は短期崩壊を招き、容易に占領できると読んでいた。
侵攻当時、そのゼレンスキー氏がよもや『第2次大戦におけるチャーチル以来の偉大なリーダー』になると予言していたとしたら、笑い飛ばされていたはずだ。
いかなる戦争であれ、長期戦となった場合、国のリーダーシップが極めて重要なカギとなることを示した。
③ NATO結束の読み違え=14年ウクライナ危機の際、西側諸国の反応はバラバラかつ優柔不断だったため、クレムリンは同程度の反応しか予想していなかった。
ところが、今回の場合、欧州およびアジア同盟諸国は侵攻開始後、短期間のうちにつぎつぎに対露経済制裁に踏み切った。
さらにNATO諸国は制裁のみならず、軍事面でも果敢にウクライナ支援に乗り出した。中でも米国は、すでに249億ドルもの対ウクライナ軍事支援を行っており、米国防総省も今後、20億ドルの長期軍事支援を約束している。
④ 兵器・弾薬類の大量損失=ウクライナ軍は米国製最新鋭ロケットシステム「HIMARS」投入により、国内各地のロシア軍兵器・弾薬庫多数を破壊した。それ以降、ロシア軍は被害を最小限にとどめるため、前線から離れた作戦地域に弾薬類を移し替えたが、この結果、必要時に前線基地にタイムリーに兵站支援することが困難になった。
このため、ロシア軍は今後、長期戦に備えた作戦練り直しを迫られている。
〇吟味される台湾とウクライナの違い
ただ、ロシアにとってのウクライナと、中国にとっての台湾との間には、国勢、地政学上など、さまざまな違いがある。
このため、もし中国が近い将来、台湾侵攻に踏み切った場合、ウクライナの教訓がただちにそのまま生かされるわけでもないことは自明の理だ
たとえば、ウクライナは人口4200万人で国土面積約60万平方キロメートル(日本の1.6倍)と広大なうえ、東欧、NATO諸国とは地続きだ。陸海空軍合わせ最大兵員数24万人、予備役100万人であり、周辺諸国ではロシアに次ぐ兵力規模を維持している。
これに対し、かつて「中華民国」と呼ばれた台湾は今日、国際的に独立国ではなく国連でも「地域」扱いを受けている。
人口2300万人で面積は約3万平方キロメートルと、ウクライナの20分の1に過ぎず、周囲を海に囲まれ孤立状態にあり、しかも中国本土とは至近距離にある。
これらの点だけを見る限り、中国は、ウクライナで苦戦するロシアに比べ、台湾侵攻上、条件としては優位に立っているとみることもできる。
しかし、中国にとって、難題もある。
①台湾島民の大半が中国大陸への帰属を望んでいない、
②台湾はウクライナとは異なり地理的には孤立しているが、米国、日本、カナダ、豪州などの主要国と太い経済的結びつきがある、
③台湾は地形的に、平野の多いウクライナと異なり、山地、丘陵地、盆地、台地、平野からなり、山地、丘陵地が全島面積の3分の2を占めているため、中国軍にとって侵攻、占領は容易でない、
④台湾の経済力とくに半導体をはじめとする最先端テクノロジーが世界に果たす役割は増大しつつあり、有事となった場合、世界経済全体に深刻な影響が及ぶ恐れがある、
⑤このため、軍事最強国米国も以前にもまして、台湾安全保障に重大な関心を示している――などだ。
結論として、中国は今後も、ウクライナ戦争の展開を引き続き注意深く見守ると同時に、軍事も含めた台湾政策を長期かつ多角的視野で検討していくことを迫られている。
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29654?page=3












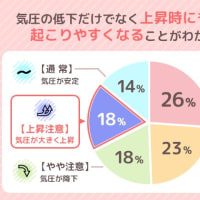

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます