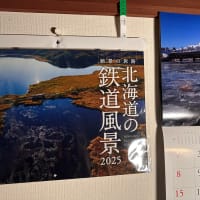レノア・テアの『記憶を消す子供たち』草思社2300円+税 を読んでいる。
レノア・テアは精神科医でトラウマと記憶に関する研究の第一人者だ。
この本は、2000年ころに一度読んでいて、職場の行きかえりや休日に車を河川敷に停めて読んでいたその時の風景と共に覚えているのだが、今回再度読んで「あぁ、そうだったんだ。」と初めて理解できることも多くあり、目を開かれる。
書名にもあるように、この本はいろいろな理由で記憶を消してしまった”かつての子ども達”が、どのように記憶を取り戻していくかを、ドキュメンタリー風に描いている。ある主婦は突然20年も前に自分の親友が自分の父親に殺されたことを、ふとしたきっかけで思い出し、父親を警察に訴え出る。裁判では当然その主婦の思い出した”父親が犯した殺人の記憶”の信憑性が問われることになり、トラウマと記憶の研究の権威として、レノア・テアが、なぜその主婦が記憶を失っていたか、なぜ思い出すことができたか、なぜその記憶が信頼に足るものなのかを、脳のメカニズムも合わせて説明する。
そのようなドキュメンタリー風な物語が7話収められているが、ヒトの弱さと強さ、両面を再認識させられる。
その中で、解離について次のような記述を見つけた。
--解離はふつう、くりかえし、つまり度重なるトラウマ体験により起る。一回限りの出来事では、通常、子供はそれほど深い自己催眠には陥らない。家庭内の虐待や暴力が、子供の解離のもっともありふれた原因である。それに慢性的な病気、家族のアルコール中毒。(中略)
想像力豊かな子供は、ときに何かのふりをするというかたちで解離する。彼らの解離の役に立つのは、リズムや踊り、魔術に呪文、それに太陽系の外の世界だ。
--『記憶を消す子供たち』レノア・テアより
以前同じカテゴリーに『乖離(かいり)ということ-NHK教育『子ども虐待』より』という記事を書き、その中で我が家に来た里子のミナナ(仮名)という子の解離の様子を記し、その子がボーッとしていると、「あ、また木星行ってる。」と私が言ったということを書いたが、なんとなくその場、その町、地球にさえ存在していないのではないかというあの存在の仕方は、やはり彼女が、レノア・テアが指摘するように”地球外”に身をおいて安全を保っていたということなのだと、改めて知った。
以前の記事で記したように、ミナナはたたかれても痛さを感じない術を身につけていた。そのことは、想像を絶するトラウマが連続する環境に彼女が置かれていたということを意味するのではないだろうか。
しかし、いろいろな”すごい”家庭をみている児童相談所に言わせると、「あの親は問題ないですよ。」ということで、彼女と妹は、また彼女に解離を与えた環境へと戻っていった。
私たちは、彼女の性化行動や彼女の告白なども報告した上で、家庭での性虐待の可能性も指摘したが、何度か若い心理士が面接を行ったのち、予定通り家に戻っていった。
私たちは、”児童相談所”が、車をあちらこちらと移動させる駐車場係のようだと思い、”児童相談所”とは、児童を守る場ではなく、大人の都合で児童を移動し、児童に大人の都合を悟らせる場なのだなあと思った。
話は逸れたが、ショッキングなほど、スポッとトラウマとなる出来事を忘れ、しかしそのトラウマに引きずられながら生きている人間の姿を、この本は教えてくれる。
ぜひ読んでください。
 | 記憶を消す子供たち |
|---|---|
| レノア テア | |
| 草思社 |