町田徹氏の『東電国有化の罠』(ちくま新書/2012年6月)を読んでの「その1」を書いてから、もう1ヶ月半になる。その間は「エネルギー基本計画」の選択肢をめぐるパブリックコメント募集と原子力規制委員会の人事問題が、津波のように襲って来ていた。どちらも終わったわけでなく現在進行中だが、とりあえず8月12日に「パブコメ期間」は終了した。寄せられた国民意見を踏まえて、閣僚で構成する「エネルギー環境会議」が政策を決定するが、市民にとってもまだ第二ラウンドがはじまったところだ。原子力規制人事委員会の人事問題はもっと切迫していて、このお盆明け20日の週にも国会承認案件として本会議にかけられ、承認されてしまうかもしれない。
そんな状況だが、この東電国有化問題はいったんまとめておきたいということで続編をお示しする。
原子力損害賠償支援機構が「原発事故被害者の救済」ではなく、「加害者である東京電力を救済し存続させるための仕組み」であることは過去にも書いた。町田氏の著作は「こんな仕組みを考えたのは一体誰か」という、私自身の問いにある程度答える内容だった。
前回「その1」では、この仕組みを考えた「東電を守ろうとしたものたち」を町田氏の分析によって解明した。原子力政策の失政の責任を追及されたくない経産省、東電への貸付や投資を回収したい三井住友銀行を中心とする金融業界、これに財務省が協力し、金融庁を黙らせ、民主党内閣を協力させて完成させた。
今回は、それはすべて国民負担であり、やがては国民資産のすべてがこの仕組みに食いつぶされると言う話。
官僚に手玉に取られた民主党閣僚
2011年の夏、東電の救済が「原子力損害賠償支援機構法」として法制化される(8月3日参議院本会議可決成立。8月10日公布、施行。)。
これに先立つ5月、実は官僚側と民主党内閣の間でバトルが繰り広げられていた。5月6日、当時の菅総理は浜岡原発の運転停止を中部電力に求め、5月18日には発送電分離に言及する。原子力推進を中心とするエネルギー基本計画の見直しも発表する。客観的に見ると、脱原発への振り子が大きく振れていた。その最中に、経産省、財務省、三井住友銀行の工作は進められていたのである。
彼らの標的にされたのは枝野官房長官(当時)である。もともと原発には慎重派であり、東電に対しても破綻処理を考えていた枝野長官に対し、失言を引き出しては包囲網を狭めていく。失言と言っても正論を言ったものだ。本来なら、その具体化を官僚がめざすべきところを、従来の経産省方針と違うと経産省幹部が怒ってみせるという、いわば官僚側の反乱みたいなものだ。ならば官僚を切れば良いものを、官僚との調整、意見のすり合せに入ってしまったようだ。政権発足当時の「政治主導」が「官僚の意見も聞かず突進」することとはき違えられて失敗し、今度は自分で調べる努力も怠って言いなりという形だ。
当時の官僚の「ご説明」がいくつか紹介されている。「当時、中小企業や海外の原油業者への支払いを怠ると、多くの中小企業の存続や原油の輸入に支障をきたすという屁理屈」を経産省官僚が政治家に根回ししていた。「東電を破綻処理すると、残存期間1年以上のものだけで2011年3月末に4兆4,255億円もの発行残高があった社債が債務不履行になり、社債市場全体が壊滅的な打撃を受ける」というのは財務省の刷り込みだ。いずれも真っ赤なウソだという。
こうして、枝野長官も「東電を支援する法案」を早急に国会で成立したいと発言するようになる。
税金を東電に流し込む原子力損害賠償支援機構法
この法律は菅内閣の重たい置きみやげだ。菅直人氏自身がこの法案の意味を理解していたら、とても成立には動かなかっただろう。理解できていなかったとしたら、総理大臣として失格だが、先に述べたように、官僚たちの「早くしないと日本経済が大変なことになる」という切迫観念の刷り込みに、冷静に対抗するすべを持たなかったのだろう。
表向きの立法主旨は「原賠法の保険金額(1200億円)を超える事態に備え、①賠償の迅速かつ適正な実施、②電気の安定供給を確保する」こと。「その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図る」という言葉もあり、将来的には原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)が事故の収束のための資金や廃炉のための費用を供出するなどの資金転用も可能な仕組みになっている。つまり、東電が今後必要な資金はすべて機構から流し込むという法律だ。
政府→機構→東電という流れで資金が注入されるが、政府から機構への資金は交付国債、機構から東電に入れる資金は交付金で、これは法律上は返還義務のないプレゼントである。本来は貸付とか融資の扱いにするべきだが、そうすると負債になり東電は一気に債務超過になり、破綻処理、法的整理という流れとなる。そうしないためには、湯水のようにお金をただ流し込むだけということだ。政府はこのために「会計法」まで改正している。
ちなみに交付国債は予算化しない政府支出だ。交付を受けた側が国債を現金化するときにだけ一般会計から支出するという。本当は借金なのだが、借金に見えないように見せかけた裏手形だ。最終的に支出はするのだから、政府財政に確実にダメージを与える。しかも最初の5兆円でとどまるはずがないのだ。
機構設置を演出した第三者委員会
機構から東電への支援金を入れる前提は、東電と機構がともにつくる「特別事業計画」である。損害賠償額や債務の支払い、経営状態などを判断した将来にわたる東電再建策という位置づけである。町田氏の著作が刊行されるまでに、特別事業計画策定は間にあわず、この著作の中での特別事業計画への言及はない。ただ大きな流れとして、野田内閣では枝野氏が官房長官から経産大臣への横滑りし、枝野氏がかつての法的整理路線から180度の変更で「実質国有化路線」に舵を切ったことがある。
枝野氏としては、法的整理方針をくつがえされたことの意趣返しという思いがあるのかもしれないが、実は底なし沼の裏手形構造をそのままに、最終破綻のつけまで国が引き受けるという帰結にもなりかねない危険な道だ。
それは、東電の抱える損害賠償や事故収束費用、除染費用などなどの負債総額を極端に小さく見誤っている可能性があるからだ。その負債総額を算出したのは「東京電力に関する経営・財務調査委員会」。町田氏の本では「第三者委員会」と書かれている。委員長が下河辺和彦弁護士。民主党の影の総理と呼ばれる仙谷由人氏が引っ張って来た人物だ。その後に機構の理事にもなり、6月の株主総会で東電の取締役会長となった。
この第三者委員会の最大の問題は賠償金額を過小に見積もったことだと言う。福島第一原発事故で避難している住民の損害や県内事業所の営業被害に限定し、それを超えるものを算定していない。たとえば漁業者、海運業者、航空運送時業者などを上げている。避難していない=避難させてもらえなかった住民の被害への損害も入ってはいない。除染費用も「合理的な損害額の算定は不可能」として、算定責任を放棄している。したがって4兆5千億円は少なすぎ、少なくとも20兆円は下らないという数字を上げている。
しかも4兆5千億円は事故から2年間の期間のものに過ぎない。3年目以降の事故収束費用、解体廃炉費用、除染費用など、とてつもない費用が発生してくるはずだ。
東電が被害者に支払った損害賠償金はまだ7,200億円程度である。まともに賠償協議に応じず、基本的に払わない姿勢を貫いている。東電は機構からの交付金を損害賠償金支払いに充てるのではなく、当面の債務超過の埋め草資金に使って、破綻を先延ばししているだけに見える。
損害賠償は今後係争になるものも数多くなるだろうし、事故収束のための費用も膨らんでいくだろう。今年度には大量の電力債の償還時期がやってきたし、汚染された土地の除染費用をまともに入れたら、その額は100兆円を下らないだろう。
実質国有化によって経営再建ができ、投下した資金の回収ができれば良いのだが、そもそもそんな仕組みにはなっておらず、さらに今後は東京電力の顧客は逃げていくだけである。電力の自由化、送電システムの改革などが進めば、東電離れはもっと如実になるだろう。電力販売による回収は不可能で、雪だるま式に増えていく機構の支出により、国民のものである国庫の資産そのものが失われていくのだ。
そんな状況だが、この東電国有化問題はいったんまとめておきたいということで続編をお示しする。
原子力損害賠償支援機構が「原発事故被害者の救済」ではなく、「加害者である東京電力を救済し存続させるための仕組み」であることは過去にも書いた。町田氏の著作は「こんな仕組みを考えたのは一体誰か」という、私自身の問いにある程度答える内容だった。
前回「その1」では、この仕組みを考えた「東電を守ろうとしたものたち」を町田氏の分析によって解明した。原子力政策の失政の責任を追及されたくない経産省、東電への貸付や投資を回収したい三井住友銀行を中心とする金融業界、これに財務省が協力し、金融庁を黙らせ、民主党内閣を協力させて完成させた。
今回は、それはすべて国民負担であり、やがては国民資産のすべてがこの仕組みに食いつぶされると言う話。
官僚に手玉に取られた民主党閣僚
2011年の夏、東電の救済が「原子力損害賠償支援機構法」として法制化される(8月3日参議院本会議可決成立。8月10日公布、施行。)。
これに先立つ5月、実は官僚側と民主党内閣の間でバトルが繰り広げられていた。5月6日、当時の菅総理は浜岡原発の運転停止を中部電力に求め、5月18日には発送電分離に言及する。原子力推進を中心とするエネルギー基本計画の見直しも発表する。客観的に見ると、脱原発への振り子が大きく振れていた。その最中に、経産省、財務省、三井住友銀行の工作は進められていたのである。
彼らの標的にされたのは枝野官房長官(当時)である。もともと原発には慎重派であり、東電に対しても破綻処理を考えていた枝野長官に対し、失言を引き出しては包囲網を狭めていく。失言と言っても正論を言ったものだ。本来なら、その具体化を官僚がめざすべきところを、従来の経産省方針と違うと経産省幹部が怒ってみせるという、いわば官僚側の反乱みたいなものだ。ならば官僚を切れば良いものを、官僚との調整、意見のすり合せに入ってしまったようだ。政権発足当時の「政治主導」が「官僚の意見も聞かず突進」することとはき違えられて失敗し、今度は自分で調べる努力も怠って言いなりという形だ。
当時の官僚の「ご説明」がいくつか紹介されている。「当時、中小企業や海外の原油業者への支払いを怠ると、多くの中小企業の存続や原油の輸入に支障をきたすという屁理屈」を経産省官僚が政治家に根回ししていた。「東電を破綻処理すると、残存期間1年以上のものだけで2011年3月末に4兆4,255億円もの発行残高があった社債が債務不履行になり、社債市場全体が壊滅的な打撃を受ける」というのは財務省の刷り込みだ。いずれも真っ赤なウソだという。
こうして、枝野長官も「東電を支援する法案」を早急に国会で成立したいと発言するようになる。
税金を東電に流し込む原子力損害賠償支援機構法
この法律は菅内閣の重たい置きみやげだ。菅直人氏自身がこの法案の意味を理解していたら、とても成立には動かなかっただろう。理解できていなかったとしたら、総理大臣として失格だが、先に述べたように、官僚たちの「早くしないと日本経済が大変なことになる」という切迫観念の刷り込みに、冷静に対抗するすべを持たなかったのだろう。
表向きの立法主旨は「原賠法の保険金額(1200億円)を超える事態に備え、①賠償の迅速かつ適正な実施、②電気の安定供給を確保する」こと。「その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図る」という言葉もあり、将来的には原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)が事故の収束のための資金や廃炉のための費用を供出するなどの資金転用も可能な仕組みになっている。つまり、東電が今後必要な資金はすべて機構から流し込むという法律だ。
政府→機構→東電という流れで資金が注入されるが、政府から機構への資金は交付国債、機構から東電に入れる資金は交付金で、これは法律上は返還義務のないプレゼントである。本来は貸付とか融資の扱いにするべきだが、そうすると負債になり東電は一気に債務超過になり、破綻処理、法的整理という流れとなる。そうしないためには、湯水のようにお金をただ流し込むだけということだ。政府はこのために「会計法」まで改正している。
ちなみに交付国債は予算化しない政府支出だ。交付を受けた側が国債を現金化するときにだけ一般会計から支出するという。本当は借金なのだが、借金に見えないように見せかけた裏手形だ。最終的に支出はするのだから、政府財政に確実にダメージを与える。しかも最初の5兆円でとどまるはずがないのだ。
機構設置を演出した第三者委員会
機構から東電への支援金を入れる前提は、東電と機構がともにつくる「特別事業計画」である。損害賠償額や債務の支払い、経営状態などを判断した将来にわたる東電再建策という位置づけである。町田氏の著作が刊行されるまでに、特別事業計画策定は間にあわず、この著作の中での特別事業計画への言及はない。ただ大きな流れとして、野田内閣では枝野氏が官房長官から経産大臣への横滑りし、枝野氏がかつての法的整理路線から180度の変更で「実質国有化路線」に舵を切ったことがある。
枝野氏としては、法的整理方針をくつがえされたことの意趣返しという思いがあるのかもしれないが、実は底なし沼の裏手形構造をそのままに、最終破綻のつけまで国が引き受けるという帰結にもなりかねない危険な道だ。
それは、東電の抱える損害賠償や事故収束費用、除染費用などなどの負債総額を極端に小さく見誤っている可能性があるからだ。その負債総額を算出したのは「東京電力に関する経営・財務調査委員会」。町田氏の本では「第三者委員会」と書かれている。委員長が下河辺和彦弁護士。民主党の影の総理と呼ばれる仙谷由人氏が引っ張って来た人物だ。その後に機構の理事にもなり、6月の株主総会で東電の取締役会長となった。
この第三者委員会の最大の問題は賠償金額を過小に見積もったことだと言う。福島第一原発事故で避難している住民の損害や県内事業所の営業被害に限定し、それを超えるものを算定していない。たとえば漁業者、海運業者、航空運送時業者などを上げている。避難していない=避難させてもらえなかった住民の被害への損害も入ってはいない。除染費用も「合理的な損害額の算定は不可能」として、算定責任を放棄している。したがって4兆5千億円は少なすぎ、少なくとも20兆円は下らないという数字を上げている。
しかも4兆5千億円は事故から2年間の期間のものに過ぎない。3年目以降の事故収束費用、解体廃炉費用、除染費用など、とてつもない費用が発生してくるはずだ。
東電が被害者に支払った損害賠償金はまだ7,200億円程度である。まともに賠償協議に応じず、基本的に払わない姿勢を貫いている。東電は機構からの交付金を損害賠償金支払いに充てるのではなく、当面の債務超過の埋め草資金に使って、破綻を先延ばししているだけに見える。
損害賠償は今後係争になるものも数多くなるだろうし、事故収束のための費用も膨らんでいくだろう。今年度には大量の電力債の償還時期がやってきたし、汚染された土地の除染費用をまともに入れたら、その額は100兆円を下らないだろう。
実質国有化によって経営再建ができ、投下した資金の回収ができれば良いのだが、そもそもそんな仕組みにはなっておらず、さらに今後は東京電力の顧客は逃げていくだけである。電力の自由化、送電システムの改革などが進めば、東電離れはもっと如実になるだろう。電力販売による回収は不可能で、雪だるま式に増えていく機構の支出により、国民のものである国庫の資産そのものが失われていくのだ。










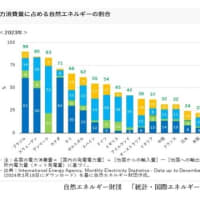


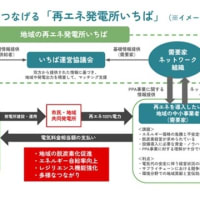






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます